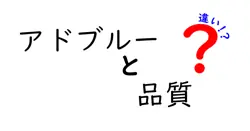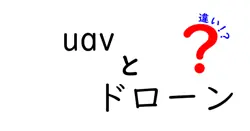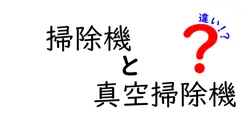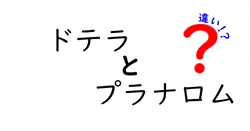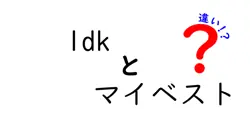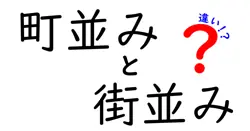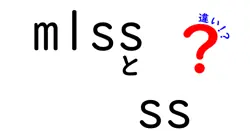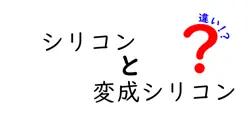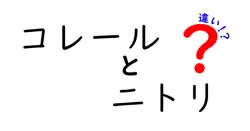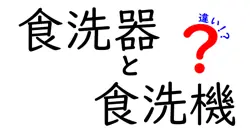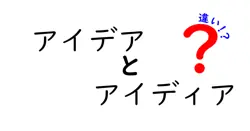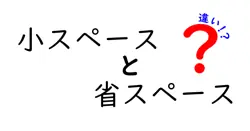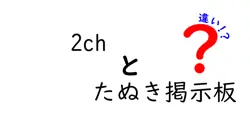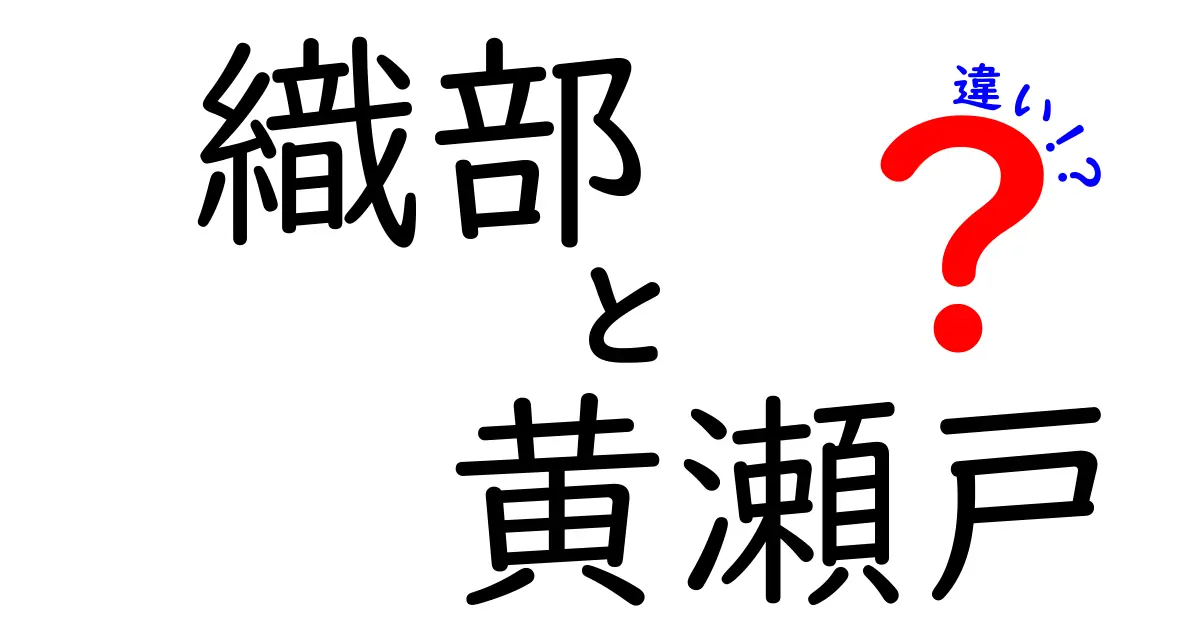
織部と黄瀬戸の違いを徹底解説!それぞれの特徴と魅力とは?
陶芸の世界には、多くの種類の焼き物があります。その中でも「織部」と「黄瀬戸」は特に人気のあるスタイルです。見た目や使われる技法に大きな違いがありますので、ここではその違いについて詳しく解説していきます。
1. 織部とは何か?
織部は、戦国時代から江戸時代にかけて日本で作られた陶器の一種です。その名前は、茶の湯のために使われたことから、有名な名人「織部正雪」に由来しています。緑色の釉薬が特徴で、装飾が豊かでユニークなデザインが多く見られます。
2. 黄瀬戸とは何か?
黄瀬戸は、織部と同じく日本の陶器ですが、主に愛知県で作られています。鮮やかな黄色の釉薬が特徴で、シンプルかつ洗練されたデザインが多いです。こちらも茶道の道具として使われることが多い焼き物です。
3. 織部と黄瀬戸の主な違い
| 項目 | 織部 | 黄瀬戸 |
|---|---|---|
| 釉薬の色 | 緑色 | 黄色 |
| 起源 | 戦国時代 | 江戸時代 |
| 装飾スタイル | 多様でユニーク | シンプルで洗練 |
| 主要産地 | 主に飛騨地方 | 愛知県 |
| 茶道での使用 | 茶碗・皿など | 茶碗・菓子器など |
4. なぜこの2つが人気なのか?
織部と黄瀬戸は、それぞれ異なる魅力を持っています。そのため、多くの人に愛されており、使う人のセンスを引き立てるアイテムとしても評価されています。どちらの焼き物も、使うことで料理やお茶をより楽しむことができます。
最後に、織部と黄瀬戸はただの焼き物ではなく、日本の陶芸文化の深さを感じさせてくれる素晴らしい作品です。それぞれの魅力を知ることで、より豊かな食生活や茶の文化を楽しむことができるでしょう。
ピックアップ解説
実は、織部焼きの中でも特に人気のある「織部茶碗」は、見た目が美しいだけでなく、使いやすさも考えられています
多くの茶道の先生たちが、織部茶碗を好んで使用しているのは、その実用性も一因です
織部焼きの独特な釉薬が、茶道の美しい所作を際立たせてくれるのです
いろんな織部焼きを試して、自分のお気に入りを見つける楽しみもありますよ
前の記事: « 才色兼備と文武両道の違いとは?その魅力を徹底解説!