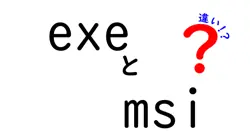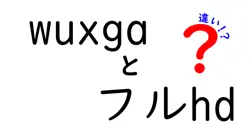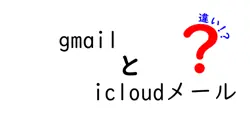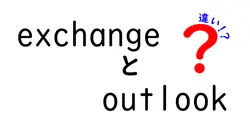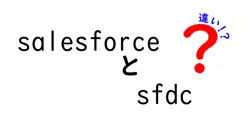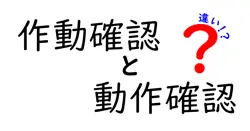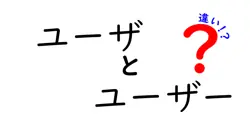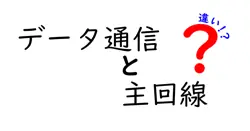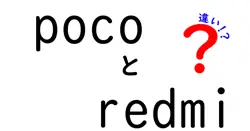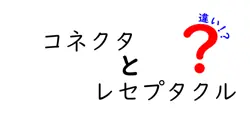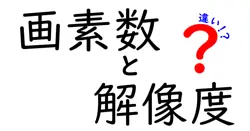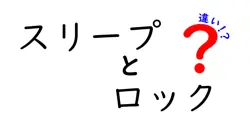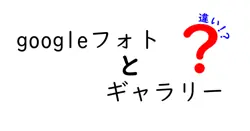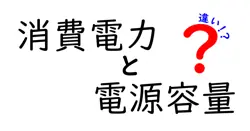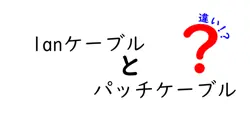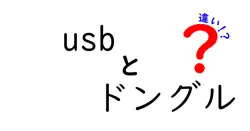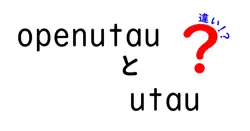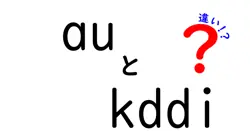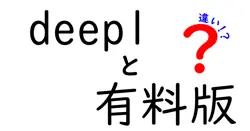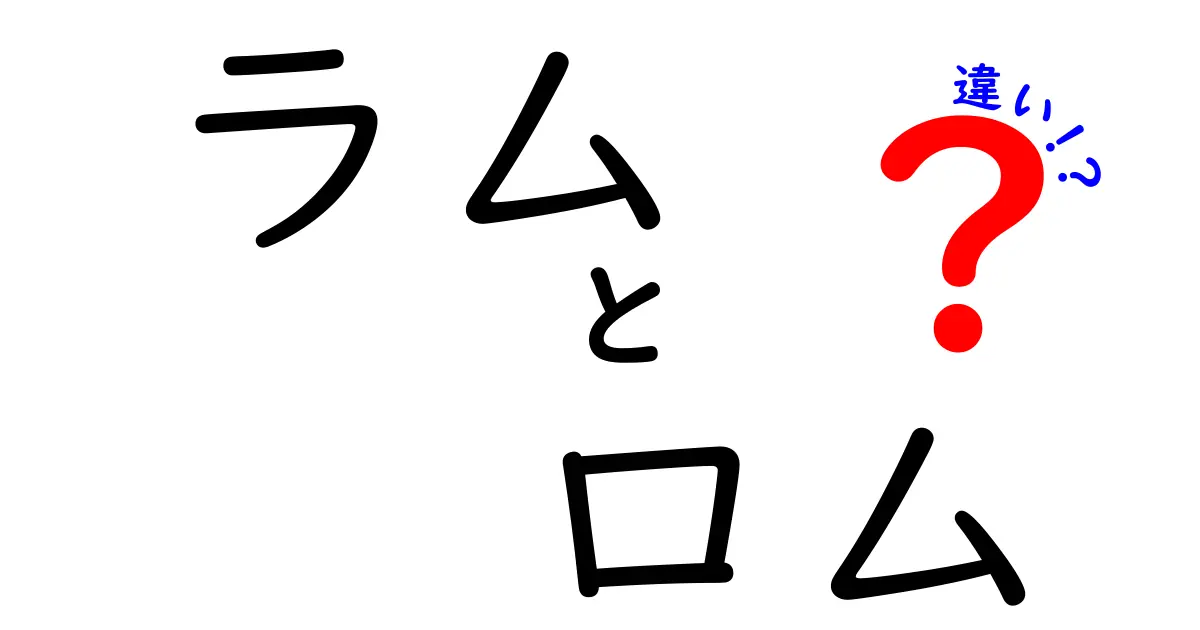
ラムとロムの違いを知ろう!
私たちの生活には、様々なデータの保存方法があります。その中でも「ラム」と「ロム」という言葉を聞いたことがある人も多いでしょう。今回は、この二つの単語が指すものやその違いについて詳しく説明します。
そもそもラムとロムって何?
まずはそれぞれの言葉の意味を確認しておきましょう。
- ラム(RAM): Random Access Memoryの略で、一般的には「作業用メモリ」として知られています。データの読み書きが非常に早いですが、電源を切るとデータが消えてしまう性質があります。
- ロム(ROM): Read-Only Memoryの略で、一度書き込まれたデータが電源を切っても消えないメモリのことです。主にデバイスの基本的な動作を保存するために使われます。
ラムとロムの主要な違い
次に、ラムとロムの違いを表形式でまとめてみましょう。
| 特徴 | ラム (RAM) | ロム (ROM) |
|---|---|---|
| データ保管 | 一時的(電源オフで消える) | 永久的(電源オフでも残る) |
| 書き換え可能性 | 書き換え可能 | 基本的には書き換え不可 |
| 主な用途 | コンピュータの作業データ | ファームウェアやBIOS |
まとめ
ラムとロムは、データの保存方法や使用目的が異なるため、選ぶ際には用途に応じた理解が必要です。例えば、速さを重視するコンピュータの作業にはラムが必要ですが、長期的な保存にはロムが適しています。このように、知識を持って利用することで、効率良くデバイスを使うことができるのです。
ピックアップ解説
ラムとロムの違いは簡単に言うと、データの消えるか消えないかにあります
ラムは一時的な作業場で、ロムは長期保存のための場所です
面白いのは、ここで使われる「ランダムアクセスメモリ」と「リードオンリーメモリ」の性質が、私たちの使うスマートフォンやパソコンの性能に大きく影響します
たとえば、ゲームをプレイする時、ラムが多ければ多いほどサクサク動きますが、ロムが多いと、データをたくさん保存できるというわけです
だから、デジタル家電を選ぶときは、このラムとロムのバランスを考えるのが重要です
前の記事: « モデル名と製品名の違いを徹底解説!どう使い分けるべき?
次の記事: d払いとおサイフケータイの違いとは?便利な使い方を徹底解説! »