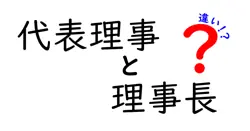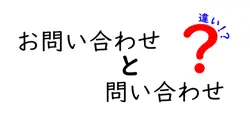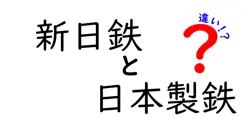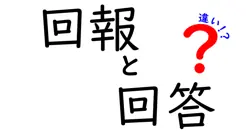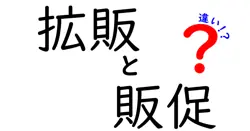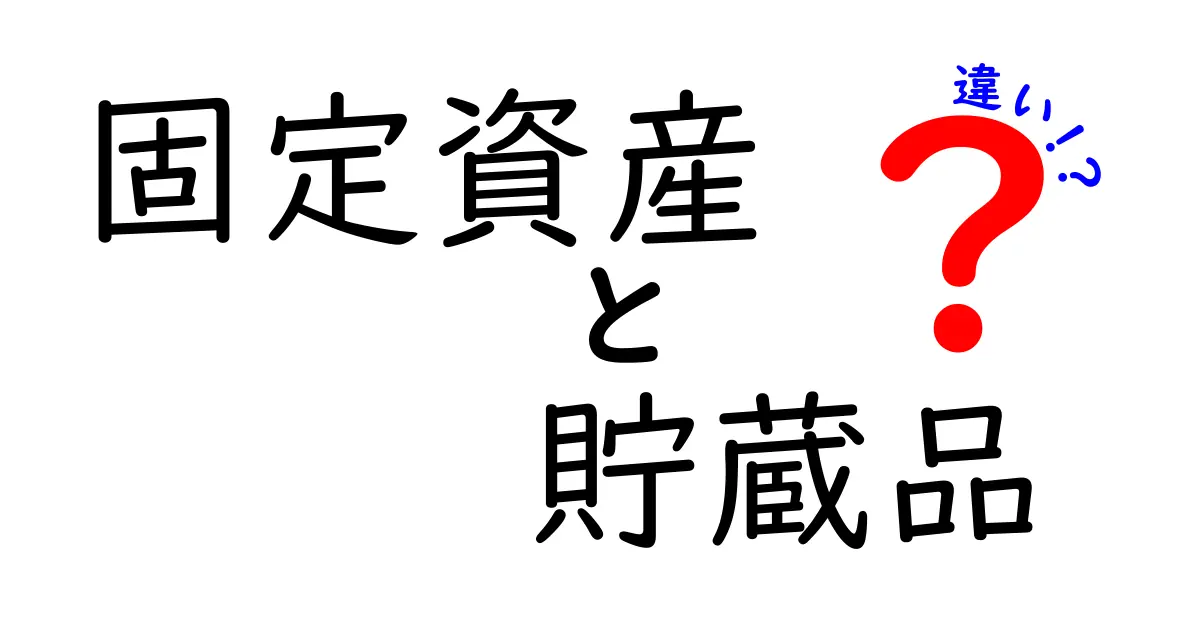
固定資産と貯蔵品の違いをわかりやすく解説!
私たちの生活には、さまざまな資産がありますが、その中でも「固定資産」と「貯蔵品」という言葉を聞くことがあります。でも、これらの言葉の意味が具体的にどう違うのかは、なかなか理解しづらいかもしれません。この記事では、この二つの言葉の違いについて詳しく説明していきます。
固定資産とは?
まず「固定資産」について考えてみましょう。固定資産とは、企業が長期間にわたって使うことができる資産のことを指します。たとえば、土地や建物、機械、車両などが該当します。これらは、使用することで価値が減少する(減価償却という考え方)ものですが、基本的には耐久性があり、容易には消費されません。
貯蔵品とは?
次に「貯蔵品」ですが、これは特定の目的のために蓄えている商品や原材料のことを指します。例えば、製造業では部品や材料を保管しておくことが貯蔵品となります。また、食品業界の場合、食料品を保存することも貯蔵品に該当します。貯蔵品は、特定の期間内に消費されることが目的です。
固定資産と貯蔵品の違い
| 項目 | 固定資産 | 貯蔵品 |
|---|---|---|
| 使用期間 | 長期間(1年以上) | 短期間(通常1年未満) |
| 価値の減少 | 減価償却がある | 消費されることが目的 |
| 例 | 土地、建物、機械 | 部品、食料品など |
まとめ
このように、固定資産と貯蔵品は、それぞれの特徴や役割が明確に異なります。企業においては、この違いを理解することが非常に重要です。しっかりと区別することで、資産管理がスムーズになります。必要なときに必要な資源を適切に管理し、効率的な運営を行うために、これらの知識をぜひ活用してください。
固定資産というと、会社が使う大きな建物や、製造に使う機械を思い浮かべる人が多いかもしれません
でも、実は固定資産には土地も含まれています
土地は一度買えばずっと使えますが、建物は古くなったり壊れたりしてしまいますよね
それに比べて、貯蔵品は主に製品や原材料です
たとえば、ラーメン屋さんでは、麺やスープの材料が貯蔵品です
このように、資産の種類によって、扱い方や管理の仕方が変わってくるのが面白いですね
前の記事: « 固定資産と販売用不動産の違いとは?それぞれの特徴を解説