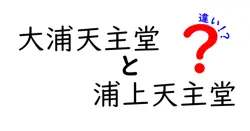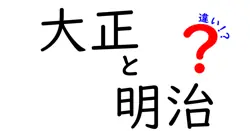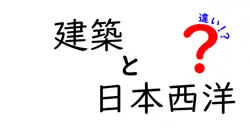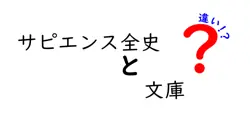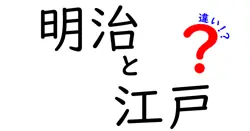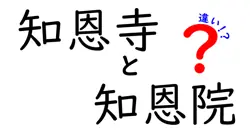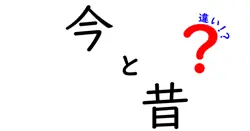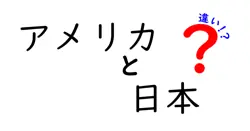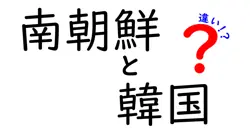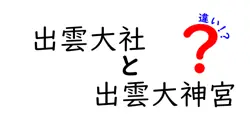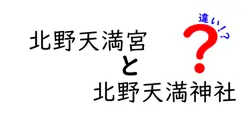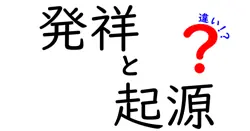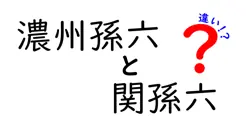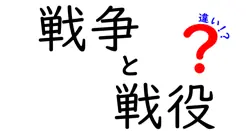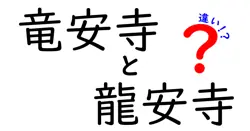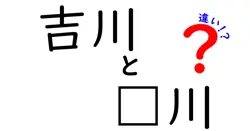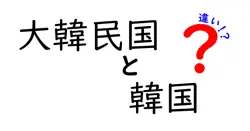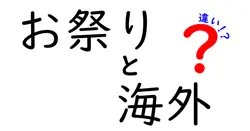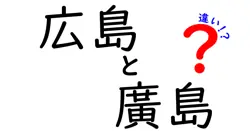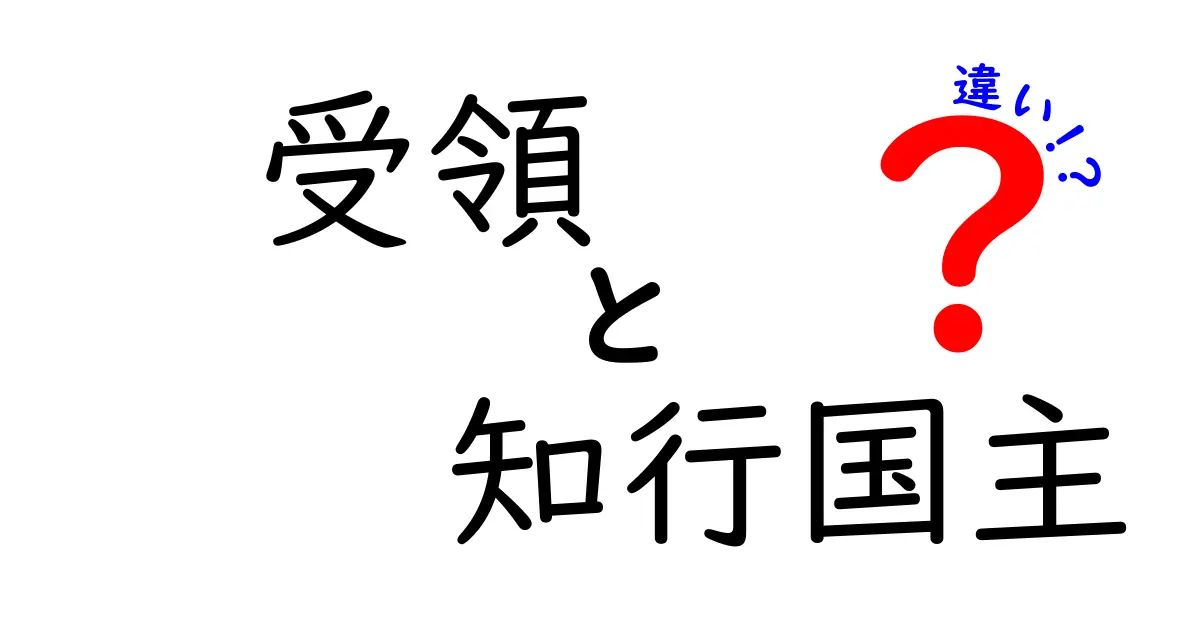
受領と知行国主の違いを徹底解説!あなたはどっちを知ってる?
日本の歴史において、特に中世や江戸時代に見られる言葉に「受領」と「知行国主」があります。これらの言葉、実際には何が違うのでしょうか?まず、どちらも当時の政治や土地管理に関わる重要な役職でしたが、役割や権限には違いがあります。
受領とは?
受領(じゅりょう)は、平安時代から用いられていた言葉で、特定の土地から得られる年貢や収入を受け取る役職を指します。受領は一般に、貴族や大名に属する人が任命され、実際の土地の管理は行わず、その代わりに年貢を受け取っていました。
知行国主とは?
一方で、知行国主(ちぎょうこくしゅ)は、より実権を持つ地位です。この役職は、主に土地を直接支配し、年貢の徴収や土地の管理を行う責任があります。知行国主は、自らの領地を持ち、実際にその国の統治を行うため、権限も広範囲です。
受領と知行国主の違い
| ポイント | 受領 | 知行国主 |
|---|---|---|
| 役割 | 年貢を受け取る | 土地を管理し徴収する |
| 権限 | 限定的 | 広範囲 |
| 関与度 | 間接的 | 直接的 |
まとめ
このように、受領と知行国主は役割や権限において大きな違いがあります。受領は年貢を受け取るに留まりますが、知行国主は土地の管理と実際の政治を行う立場です。歴史を学ぶ上で、これらの区別は非常に重要です。
ピックアップ解説
受領という言葉、実は平安時代の貴族たちが年貢を受け取るためにできた役職のことなんだ
そう考えると、昔の人たちがどうやって力を持っていたのかが見えてくるよね
受領が年貢を受け取るだけだったのに対し、知行国主はどんな土地を持っているのか、本来の意味で国を治める意味を理解する必要があるんだ
前の記事: « 受領と検収の違いとは?ビジネスシーンでの重要ポイントを解説!
次の記事: 受領と領収の違いとは?しっかり理解しよう! »