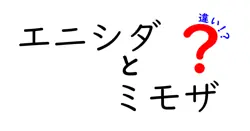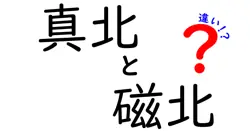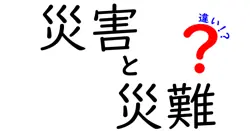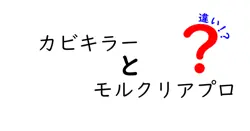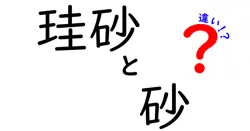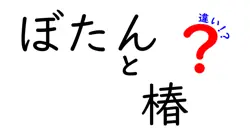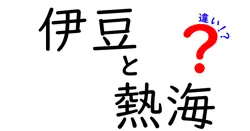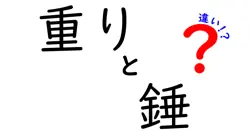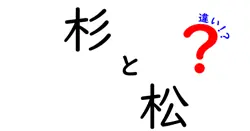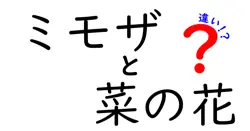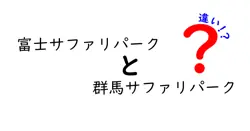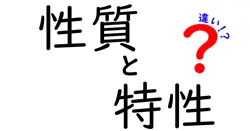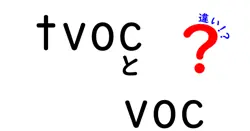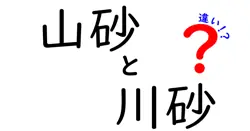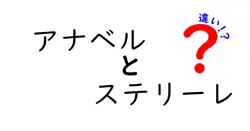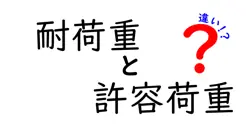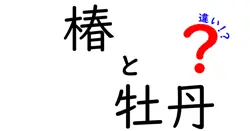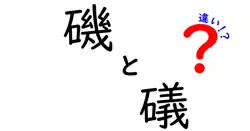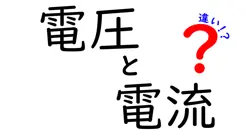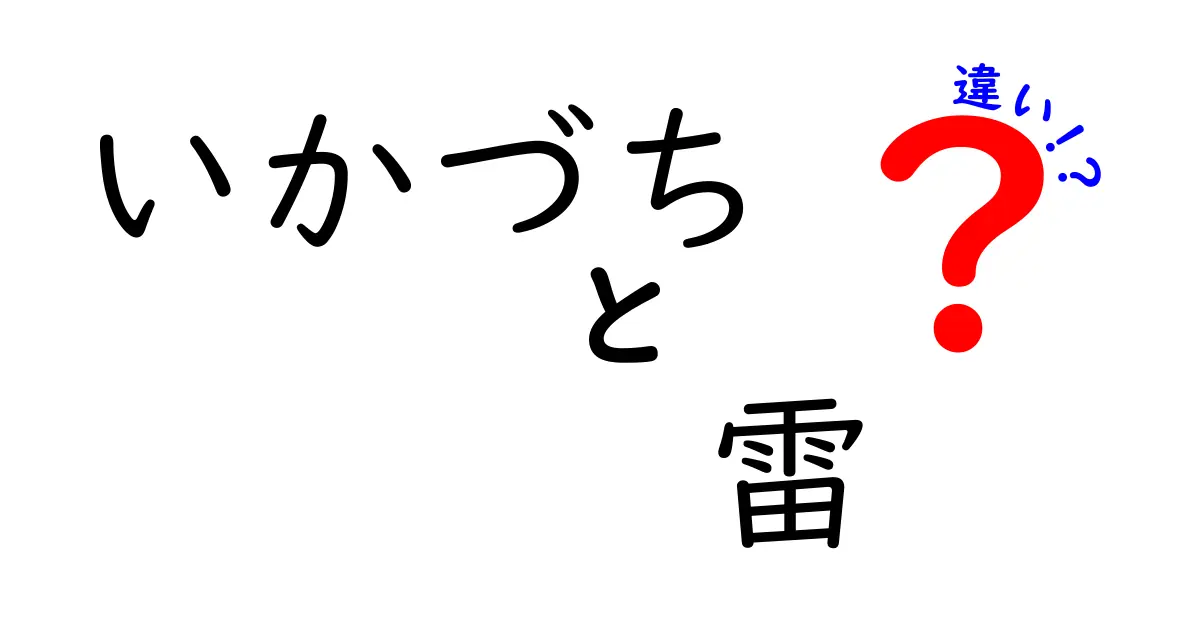
いかづちと雷の違いを徹底解説!知って驚く天候の秘密
「いかづち」と「雷」という言葉は、天候や自然現象について語る際によく使われますが、実はこれら2つには微妙な違いがあります。そこで、いかづちと雷の違いについて解説し、それぞれの意味や使い方、さらには関連する情報を紹介します。
いかづちとは?
「いかづち」という言葉は、日本語で「雷」を指す古語の一つです。この言葉の「いか」は「いかに」という意味から派生し、「づち」は「音」を意味します。つまり、いかづちは「いかに響く音」、つまり大きな音を伴う現象を示しています。
雷とは?
「雷」は、気象用語として非常に一般的に使われる言葉です。雷は、雷雲内の電気的な放電によって生じる光や音のことで、通常はエレクトリックな放電によって発生します。雷は、光と音の両方を伴う自然現象として知られています。
いかづちと雷の違い
| 項目 | いかづち | 雷 |
|---|---|---|
| 意味 | 古語での「雷」のこと | 現代日本語での「雷」のこと |
| 使用例 | 古典文学や神話 | 気象予報や一般的な会話 |
| 響きの強さ | 大きな音を強調 | 自然現象を客観的に形容 |
まとめ
このように、「いかづち」と「雷」は同じ現象を指しているものの、使われる場面や背景によって違いがあります。いかづちという言葉は文学的な面での使用が多く、雷は現代に通用する言葉です。これからの天候の話題で、ぜひ使い分けを意識してみてください。
ピックアップ解説
いかづちという言葉は、実は神道とも深い関係があるんだよね
日本の神々が雷を象徴することが多く、いかづちはその神々の力の象徴とも捉えられているんだ
雷が鳴ると、「神様が降りてきた」という感覚になるのは、そういった文化的な背景から来ているかもしれないね
自然現象の中には、こんな風に人間の信仰や時代背景が映し出されることがあるから面白いよね
前の記事: « OAタップと延長コードの違いとは?使い分けを徹底解説!
次の記事: たこ足配線と延長コード、何が違うの?それぞれの特徴を徹底解説! »