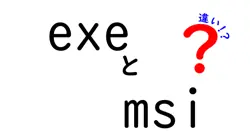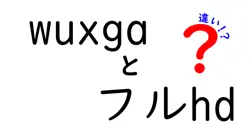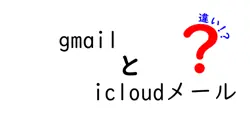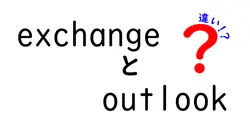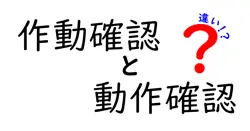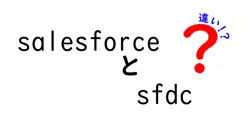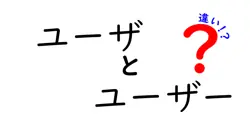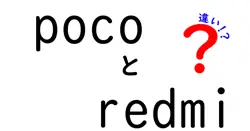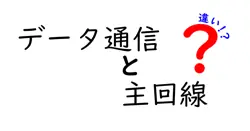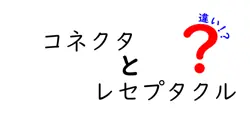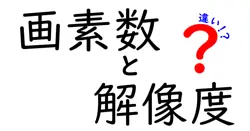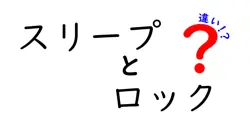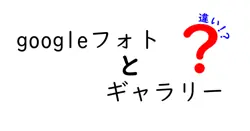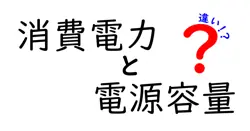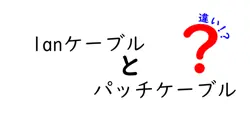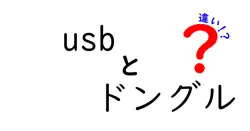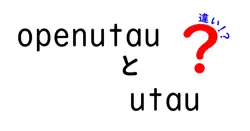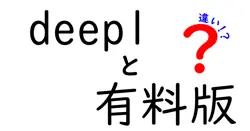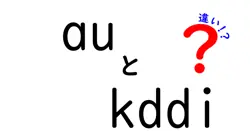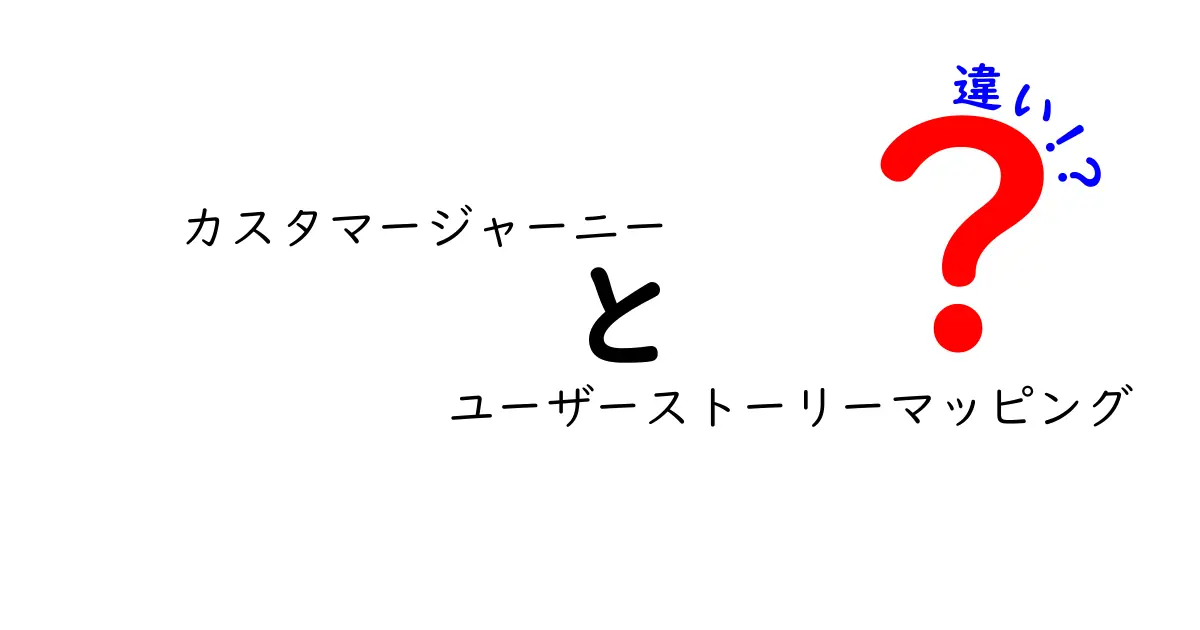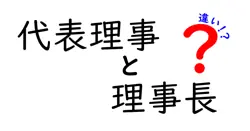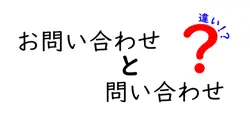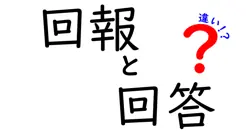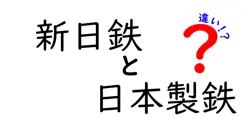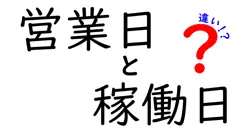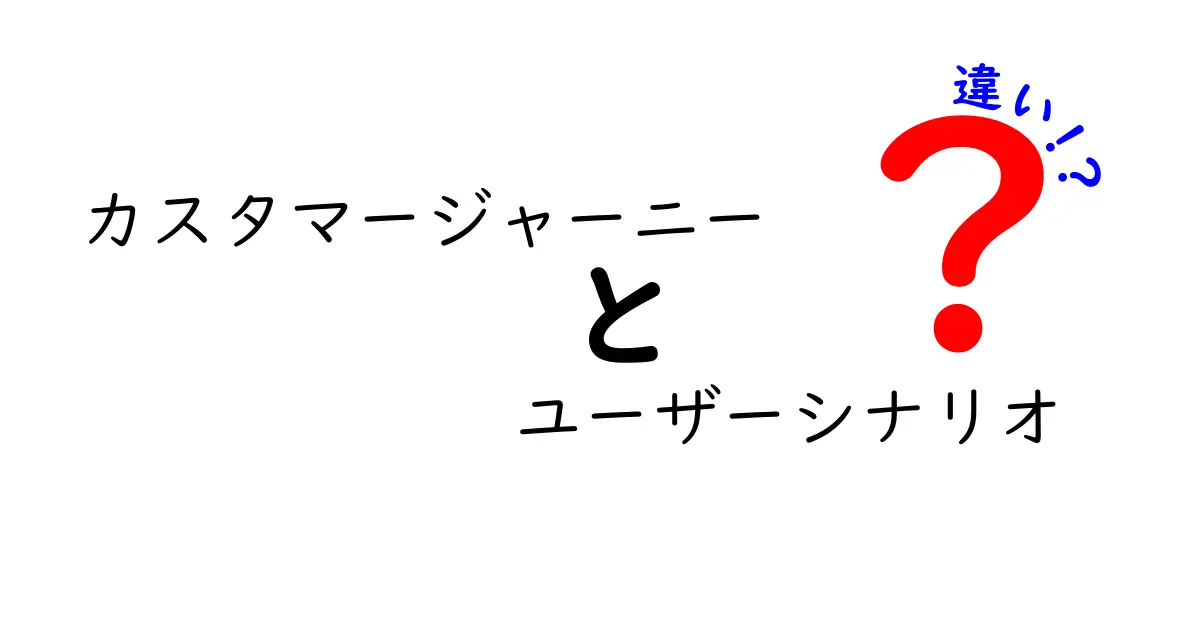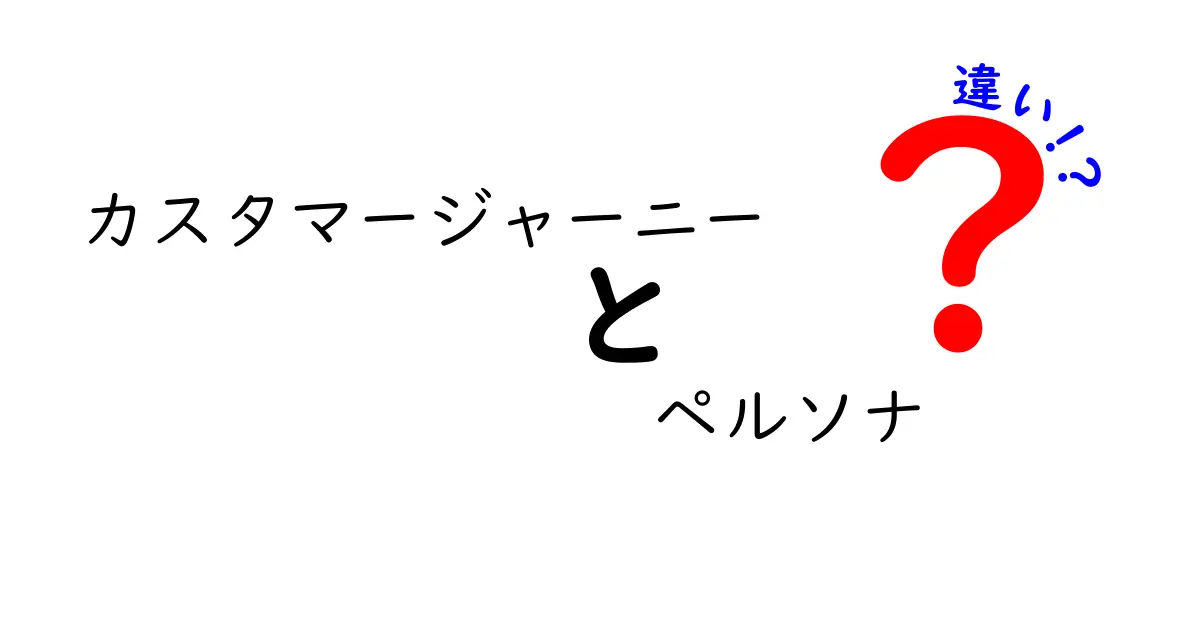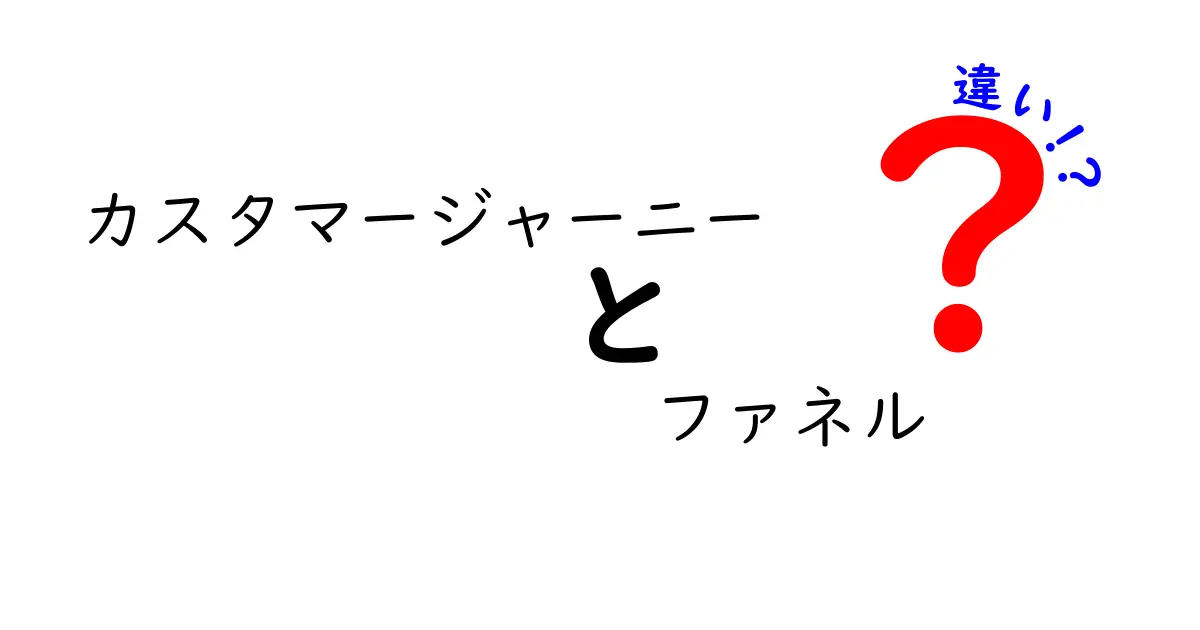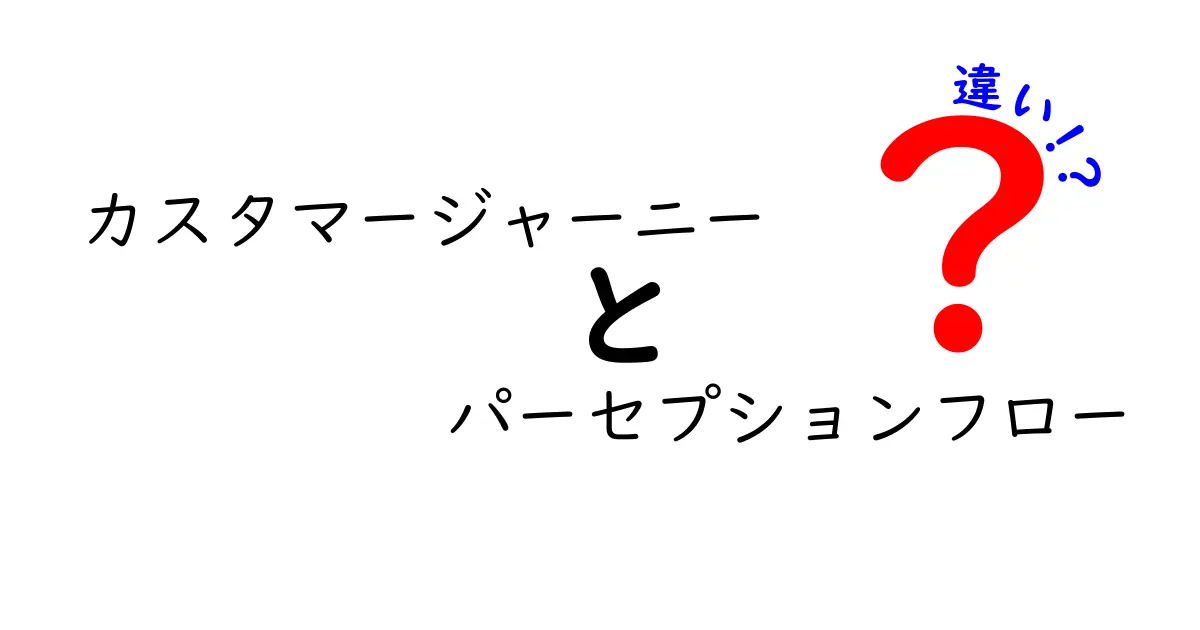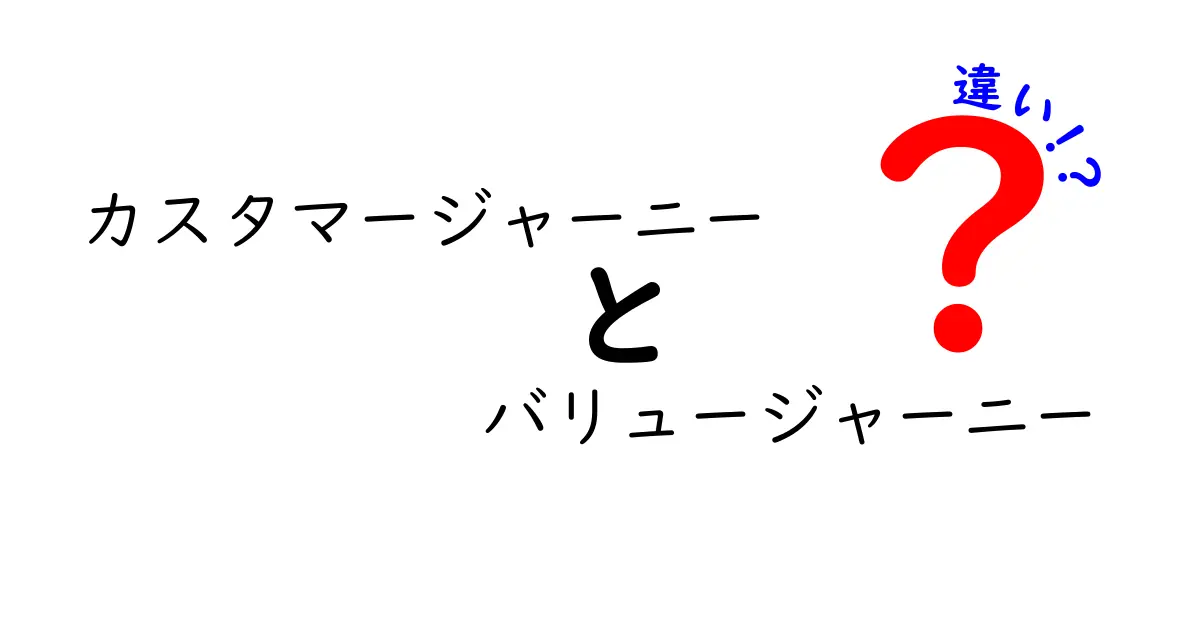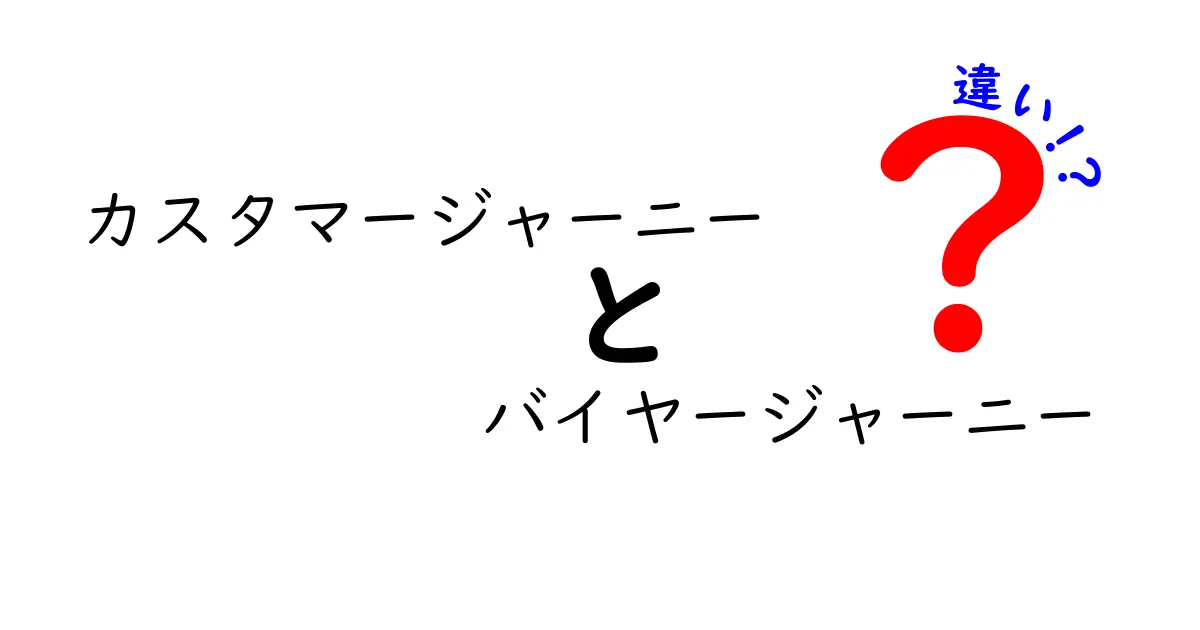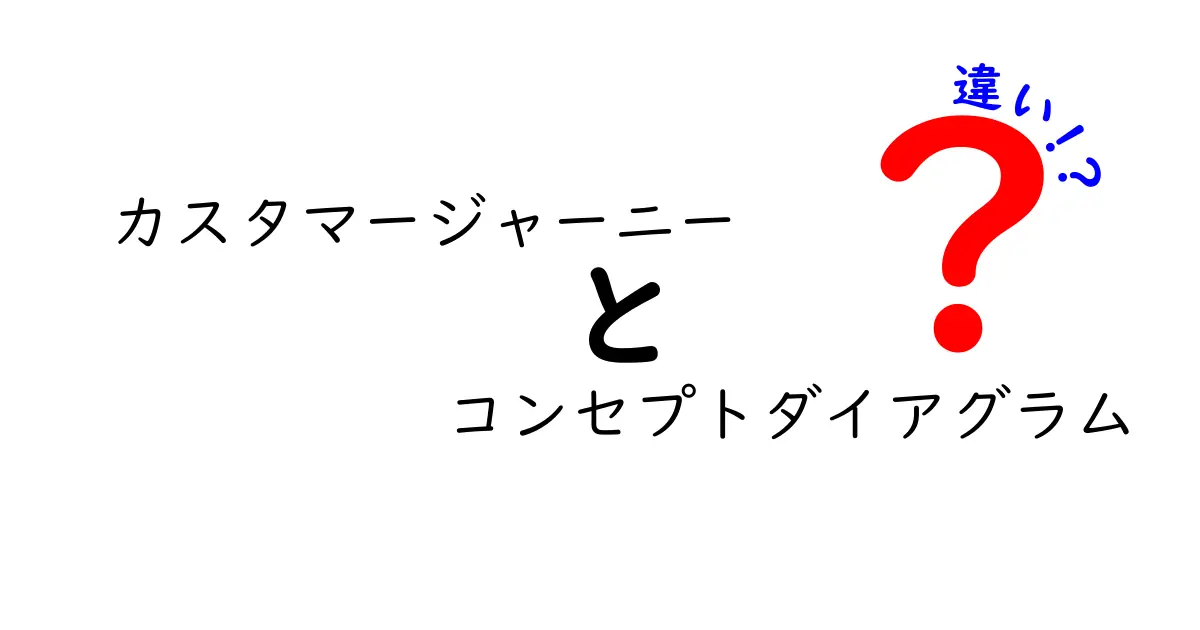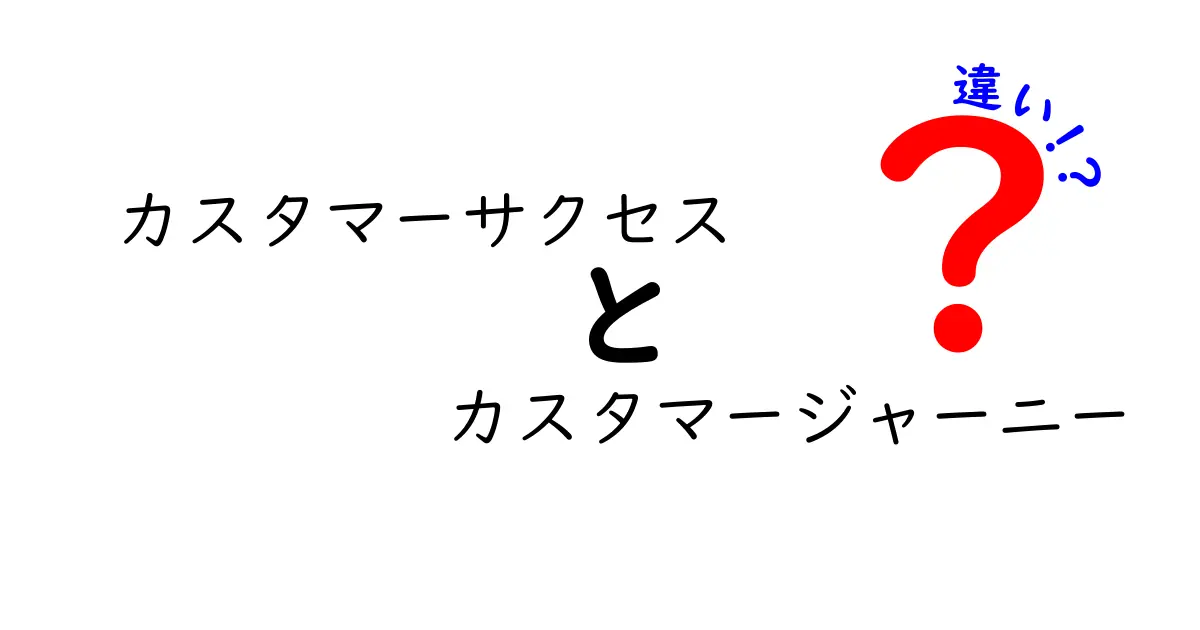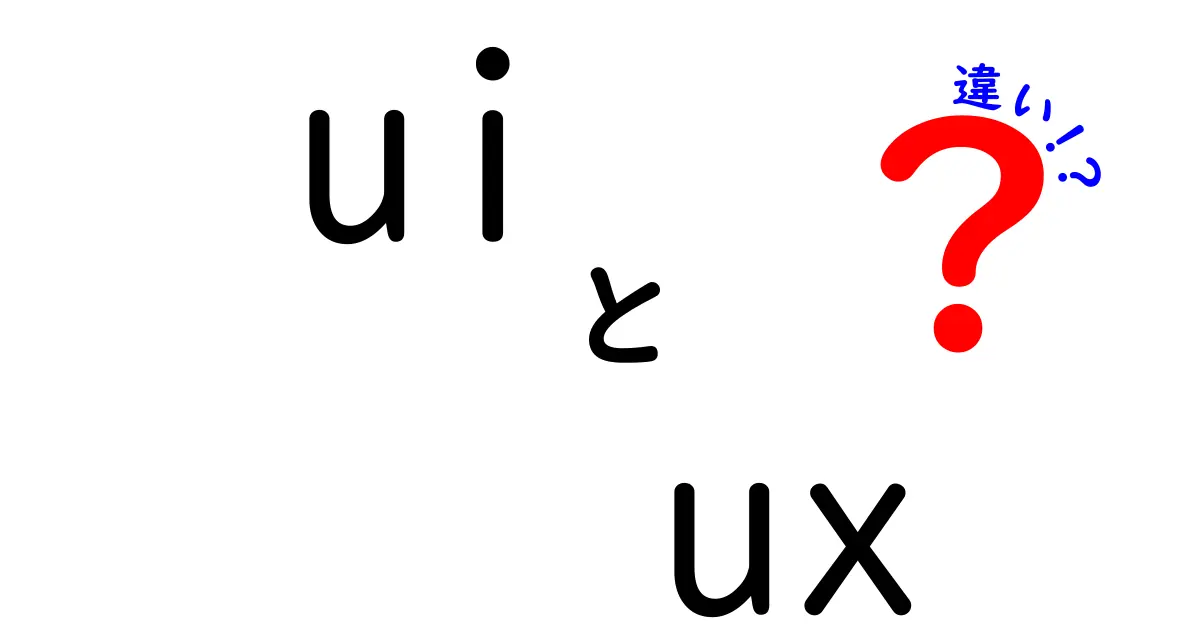
UIとUXの違いをわかりやすく解説!どちらも大切な理由とは?
最近、スマートフォンやパソコンを使っていると、「UI」や「UX」という言葉をよく耳にすることが多くなりました。でも、これらの言葉の違いって何だろうと疑問に思ったことはありませんか?今回は、UIとUXの違いについて、わかりやすく説明します。
UIとは?
UIは「ユーザーインターフェース」の略です。これは、ユーザーとコンピュータがやり取りする時の「見た目」や「操作」を指します。具体的には、ボタンのデザイン、色、アイコン、メニューの配置など、実際に目に見える部分です。皆さんがアプリやウェブサイトを使うときに触れる部分がUIです。

UXとは?
一方で、UXは「ユーザーエクスペリエンス」の略で、ユーザーが製品やサービスを使ったときの「体験」全体を意味します。たとえば、アプリを使ってみて「使いやすい」「楽しい」と感じることがUXにあたります。つまり、UXはユーザーがアプリやサービスを使った時の満足度や感情に関わる部分なのです。
UIとUXの違いを表で比較
| 項目 | UI | UX |
|---|---|---|
| 意味 | ユーザーインターフェース | ユーザーエクスペリエンス |
| 焦点 | 見た目や操作感 | 体験や感情 |
| 重要性 | デザインが重要 | 満足度が重要 |
なぜUIとUXが重要なのか?
UIとUXはどちらもユーザーにとって重要です。いいUIがあっても、そのアプリが使いにくいと感じたら、ユーザーは離れてしまいます。逆に、UXが良くても、見た目がよくないと使ってみようとは思わないかもしれません。つまり、UIとUXは相互に依存しているのです。
結論として、UIは見た目、UXは体験を意味しますが、どちらもユーザーにとって価値のあるものであることが大切です。これを理解することで、あなた自身のアプリやウェブサービスに対する見方が変わるかもしれません。感情的なつながりを持つことで、使い続けてもらえるようなデザインを目指しましょう。
そうそう、UIとUXって言葉の響きこそ似てるけど、実は全然違うんだよね
例えば、君が好きなゲームがあるとするよね
そのゲームでキャラクターがカッコよくデザインされていて操作もスムーズだったら、あれがUIの部分
でも、そのゲームをプレイした時のワクワク感やドキドキ感がUXなんだ
本当に楽しめるゲームは、UIもUXも両方ともいいからこそなんだよね!