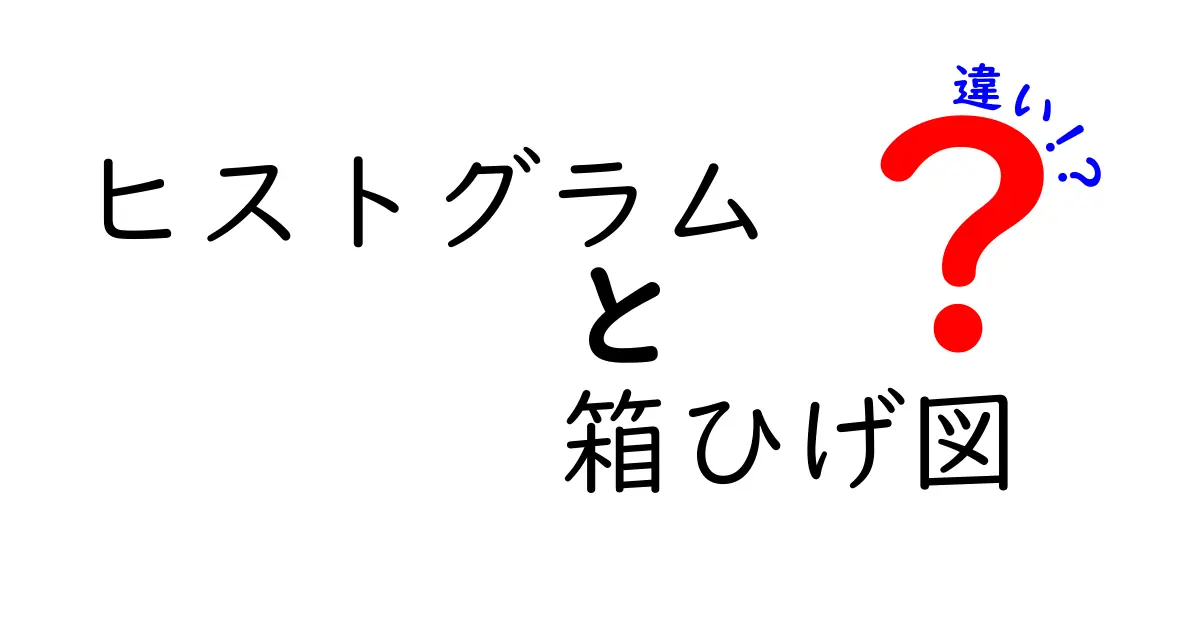
ヒストグラムと箱ひげ図の違いを徹底解説!どちらを使うべき?
データを視覚化する際に用いられるグラフにはさまざまな種類がありますが、特にヒストグラムと箱ひげ図は非常に人気があります。では、この2つのグラフはどのように異なるのでしょうか? 中学生でもわかりやすく解説していきます。
ヒストグラムとは?
ヒストグラムは、データの分布を視覚的に表現するためのグラフです。特に、連続した数値データを特定の幅の区間(ビン)に分けて、その区間に含まれるデータの数を棒グラフの形で表します。データの密度や分布を一目で確認するのにとても便利です。
ヒストグラムの作成手順
- データを集める
- データの範囲を決める
- 適切なビンの幅を決める
- 各ビンに含まれるデータの数を数える
- 棒グラフを作成する
箱ひげ図とは?
箱ひげ図(ボックスプロット)は、データの散らばり具合や中心値を示すグラフです。データを四分位数に分け、箱(ボックス)で表現します。箱の中にはデータの中央値が表示され、ひげ(ライン)はデータの最小値から最大値を示します。データの要約を簡潔に視覚化できます。
箱ひげ図の構成要素
- 箱:第1四分位数から第3四分位数までの範囲
- 中央値:箱の中の線で表示される
- ひげ:データの範囲(最小値から最大値まで)
ヒストグラムと箱ひげ図の違い
| 特長 | ヒストグラム | 箱ひげ図 |
|---|---|---|
| データの種類 | 連続データ | 数値データの要約 |
| 視覚化の方法 | 棒グラフ | 箱とひげ |
| 用語 | ビン | 四分位数 |
| 中心値の表示 | なし | 中央値あり |
| 分布の確認 | 可視化可能 | 可視化可能 |
どちらを使うべき?
ヒストグラムと箱ひげ図は、それぞれ異なる目的のために使用されます。データの分布や偏りを詳細に確認したいときはヒストグラムが適しています。一方、データの要約を簡単に視覚化したい場合は箱ひげ図がベストです。使いたい情報に応じて選ぶと良いでしょう。
ヒストグラムは、特に学生の皆さんにとってはデータ分析の神様のような存在です
実際、学校の授業でもよく使われますが、データの分布を理解することで問題を解く助けにもなりますよね
例えば、テストの点数をヒストグラムにすると、どの範囲の点数が多いのか、一目で分かります
これ、ミステリー小説の伏線みたいに、どの辺りでつまずいているのかを示してくれるんです!データ分析を楽しくするためには、ヒストグラムの活用が非常に重要なんですよ
前の記事: « ヒストグラムと確率密度関数の違いをわかりやすく解説!
次の記事: 数理統計学と統計学の違いをわかりやすく解説! »





















