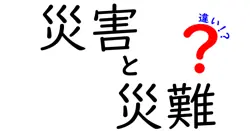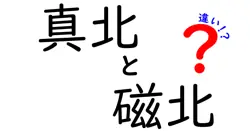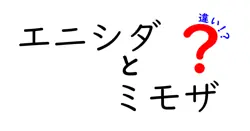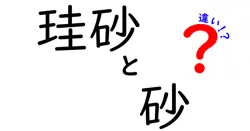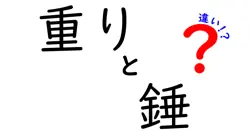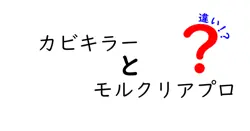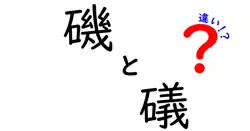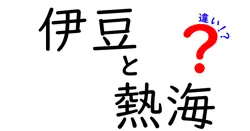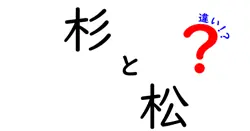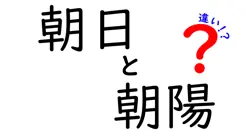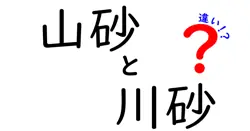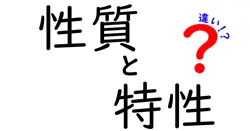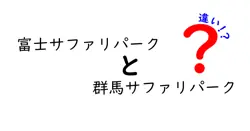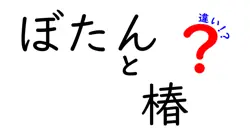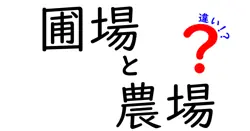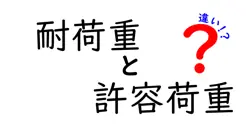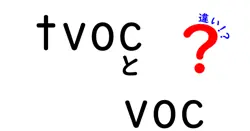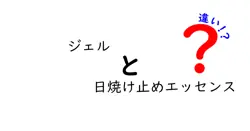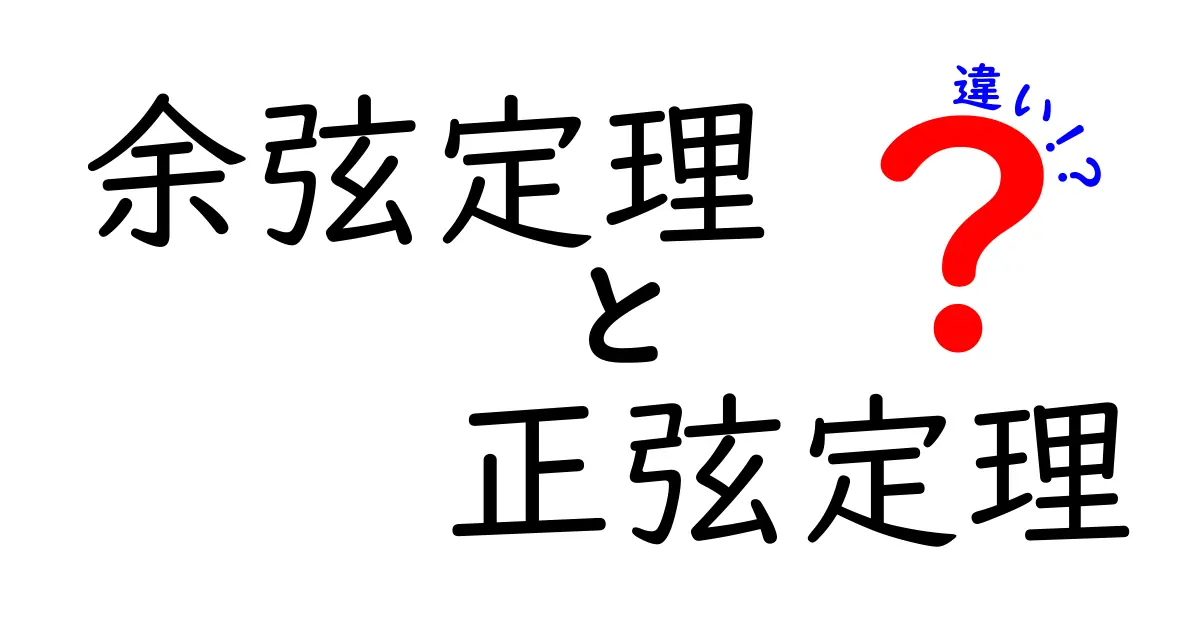
余弦定理と正弦定理の違いをわかりやすく解説!
数学の授業で出てくる「余弦定理」と「正弦定理」。これらは三角形の性質を理解するために非常に重要なものです。でも、具体的にどんな違いがあるのか、頭が混乱してしまうこともありますよね。今回は、余弦定理と正弦定理について詳しく解説し、最後には違いを分かりやすく整理してみます。
余弦定理とは?
余弦定理は、任意の三角形において、三辺の長さとその中にある角度との関係を表すものです。具体的には、三角形の各辺の長さをa、b、c、角度をA、B、Cとしたとき、次のような式が成り立ちます。
| 式 | 説明 |
|---|---|
| a² = b² + c² - 2bc・cos(A) | 辺aの二乗は、辺bとcの二乗の和から、辺bとcの長さと角度 |
正弦定理とは?
正弦定理は、三角形の各辺の長さとその対角の正弦に関する関係を示すものです。三角形の辺a、b、cと角度A、B、Cに対して、以下のような式が成り立ちます。
| 式 | 説明 |
|---|---|
| a / sin(A) = b / sin(B) = c / sin(C) | 辺aを、その対角の正弦で割ったものは、他の辺に対しても同じ値になる。 |
余弦定理と正弦定理の違い
では、余弦定理と正弦定理の違いを整理してみましょう。
- 扱う内容: 余弦定理は辺の長さと角度の関係、正弦定理は辺の長さと対角の正弦の関係。
- 使用する場面: 余弦定理は角度や辺の内訳を知っているときに使い、正弦定理はどれか一つの辺とその対角を知っている時によく使われる。
- 公式の形: 余弦定理は二次式、正弦定理は比例式の形を持つ。
このように、余弦定理と正弦定理はそれぞれ異なる側面から三角形を捉えています。どちらも理解すれば、三角形の性質を大いに利用できるため、一緒に覚えてしまいましょう!
ピックアップ解説
余弦定理の興味深い点の一つは、三角形の角度をサイドの長さから計算できることです
もし、長さがわかっていれば、数学の問題だけでなく、日常生活でも役立つことがありますよ
例えば、建物の高さを測るときに、三角形の性質を使って間接的に高さを求めることができるんです
頭を使って実生活につなげてみると、数学がもっと楽しくなりますよ!
前の記事: « 加法定理と和積の公式の違いをわかりやすく解説!
次の記事: 回旋と旋回の違いを徹底解説!その意味と使い方に迫る »