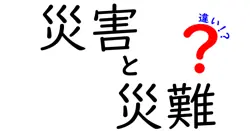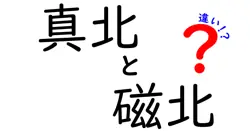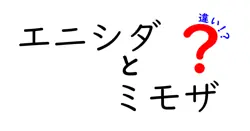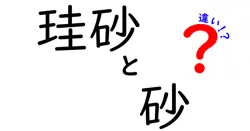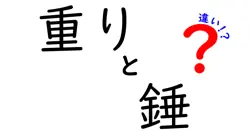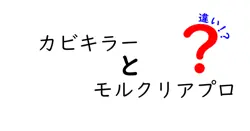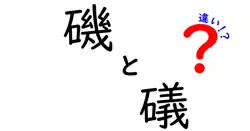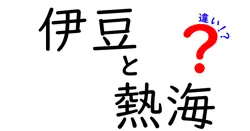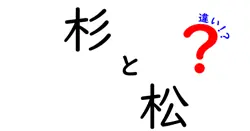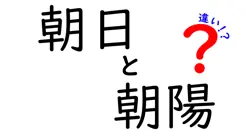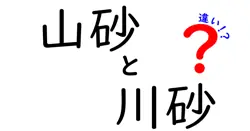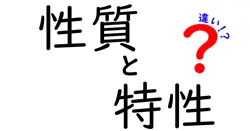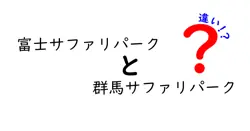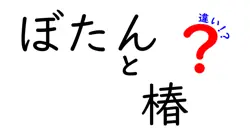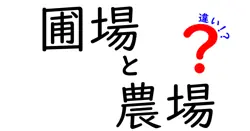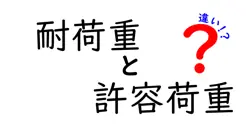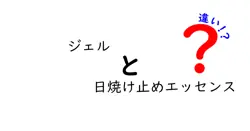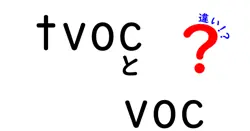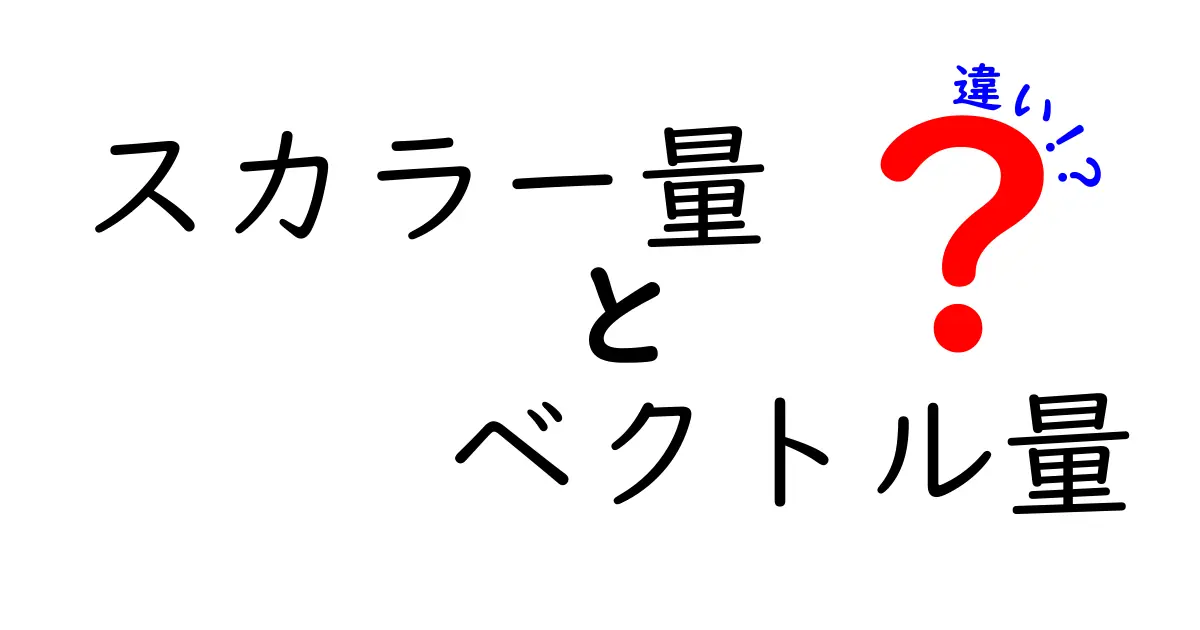
スカラー量とベクトル量の違いをわかりやすく解説!
こんにちは!今回は、物理や数学でよく出てくる「スカラー量」と「ベクトル量」についてお話しします。これらの言葉は、数や量を表現するために使われますが、それぞれの特性には大きな違いがあります。さっそく見ていきましょう。
スカラー量とは?
スカラー量は、数値と単位だけで完全に表される量です。つまり、スカラー量は大きさ(量)だけを持っていて、方向を持たないのが特徴です。一般的な例としては、温度、質量、時間、エネルギーなどがあります。
ベクトル量とは?
一方、ベクトル量は大きさだけでなく、方向も持つ量です。つまり、ベクトル量は「どれくらい」の情報と「どの方向」の情報を合わせて持っています。代表的な例は、速度、加速度、力などです。たとえば、「速さが5メートル毎秒」というだけではスカラー量ですが、「5メートル毎秒北向き」となるとベクトル量になります。
スカラー量とベクトル量の違いを表で見る
| 特性 | スカラー量 | ベクトル量 |
|---|---|---|
| 大きさ | あり | あり |
| 方向 | なし | あり |
| 例 | 温度、質量 | 速度、力 |
まとめ
スカラー量は単に数量だけを表し、ベクトル量は数量に方向も加えた複雑な情報です。この違いを理解することで、物理や数学の問題に対するアプローチも変わってきます。これからの勉強にぜひ役立ててくださいね!
ピックアップ解説
スカラー量の代表的な例として「温度」を考えてみましょう
温度はたとえば「20度」といった具合に表されますね
ですが、実際には「20度」は「どこでの20度」かという方が重要です
例えば、海の中と外気では体感温度が違います
また、温度は時間帯によっても変わります
だから、スカラー量であってもコンテキストが大事だなぁと感じます
これが科学の面白いところですね!
次の記事: セマンティックモデルとデータフローの違いをわかりやすく解説! »