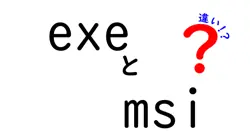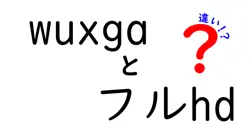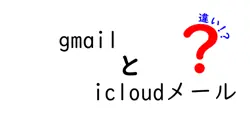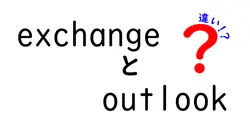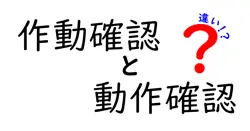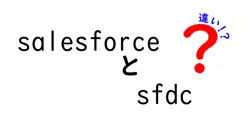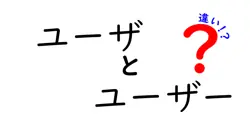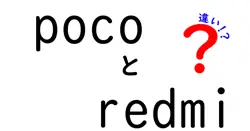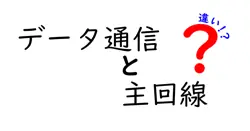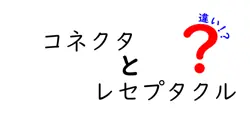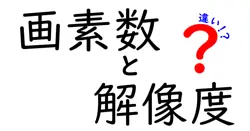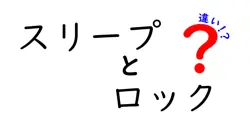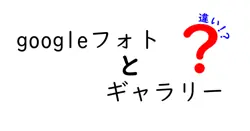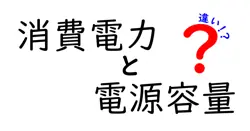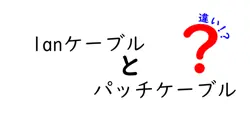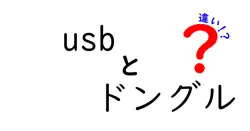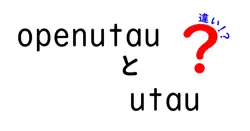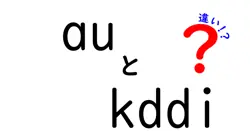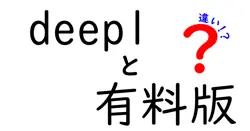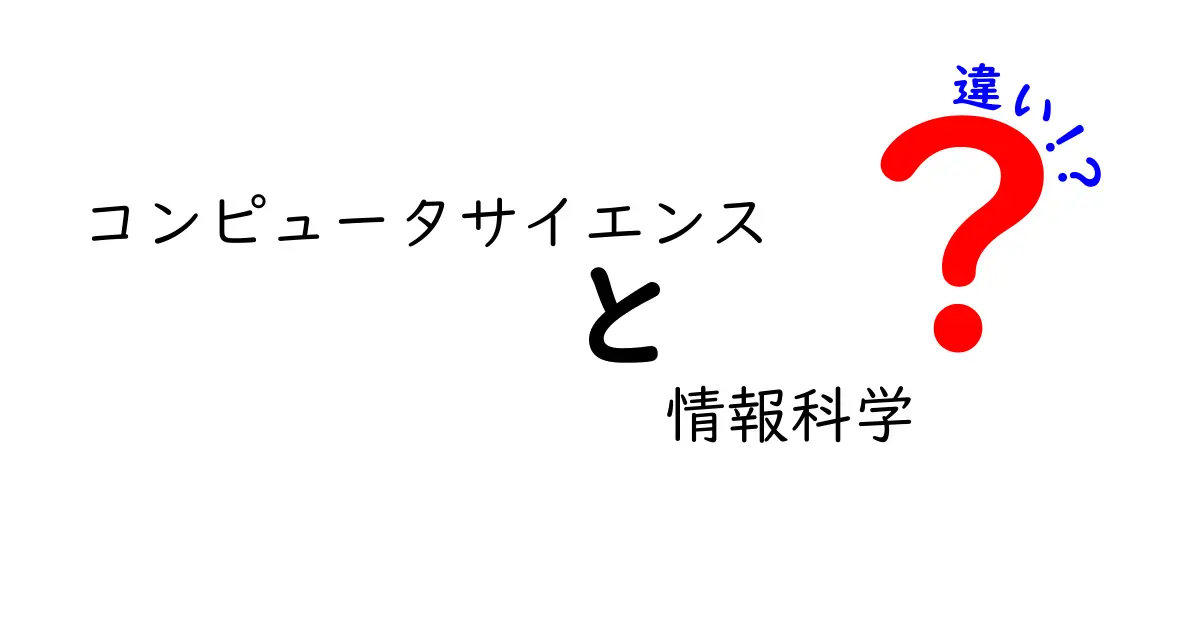
コンピュータサイエンスと情報科学の違いをわかりやすく解説!
コンピュータサイエンス(Computer Science)と情報科学(Information Science)という言葉を耳にしたことはありますか?この2つは似ている部分もありますが、実は異なる点も多いんです。今回は、中学生にもわかりやすくこの違いを解説します。
コンピュータサイエンスとは?
コンピュータサイエンスとは、コンピュータの働きやその原理について学ぶ学問です。プログラミングやアルゴリズム、データ構造などを中心に、ソフトウェアやハードウェアに関する知識を深めていきます。
情報科学とは?
一方、情報科学は、情報の収集、整理、保存、伝達、利用に関する学問です。情報をどのように効率よく扱うことができるか、また情報が持つ価値について考えるのが主な目的です。
| 特徴 | コンピュータサイエンス | 情報科学 |
|---|---|---|
| 主な研究対象 | プログラムやシステム | 情報の流れや価値 |
| 関連技術 | プログラミング言語、アルゴリズム、AI | データベース、情報検索、ヒューマンコンピュータインタラクション |
| 活用分野 | ソフトウェア開発、システム設計 | 情報管理、図書館学、ビジネスインテリジェンス |
コンピュータサイエンスと情報科学の違い
コンピュータサイエンスが主に技術的な側面に焦点を当てているのに対し、情報科学は情報そのものやその利用法に目を向けています。たとえば、コンピュータサイエンスではプログラムを作る方法を学びますが、情報科学ではそのプログラムがどのように情報を処理し、役立てるかに注目します。
まとめ
いかがでしたでしょうか?コンピュータサイエンスと情報科学は密接に関連していますが、学ぶ内容やアプローチが異なります。興味のある分野を深めて、自分に合った学問を見つけてみてください!
情報科学という言葉を聞いたことがありますか?この分野は、図書館学やビジネスにとても関わっているんです
例えば、企業が持つデータをどう活用して競争力を高めるか、そんなことを考えるのが情報科学の役割です
そして、最近ではAIやビッグデータも注目されています!
前の記事: « DXとロボティクスの違いとは?デジタル革命と未来の技術を探る
次の記事: システム科学と情報科学の違いとは?わかりやすく解説! »