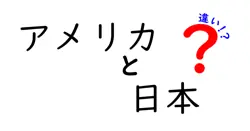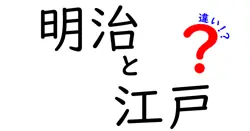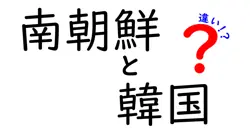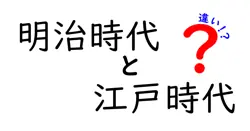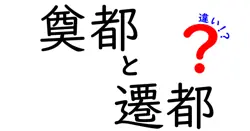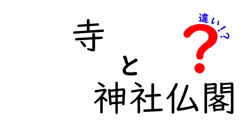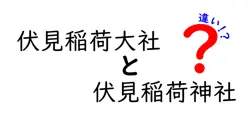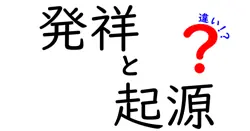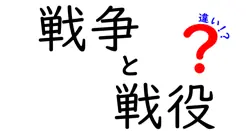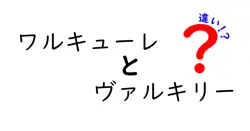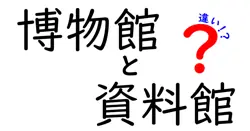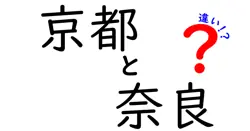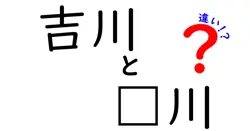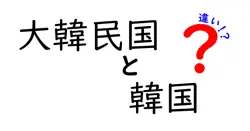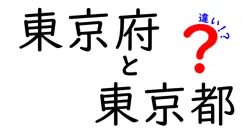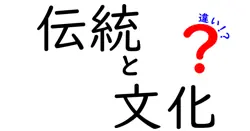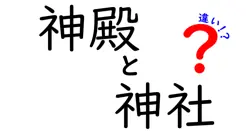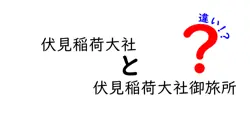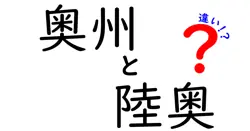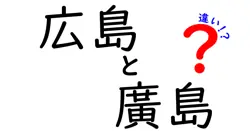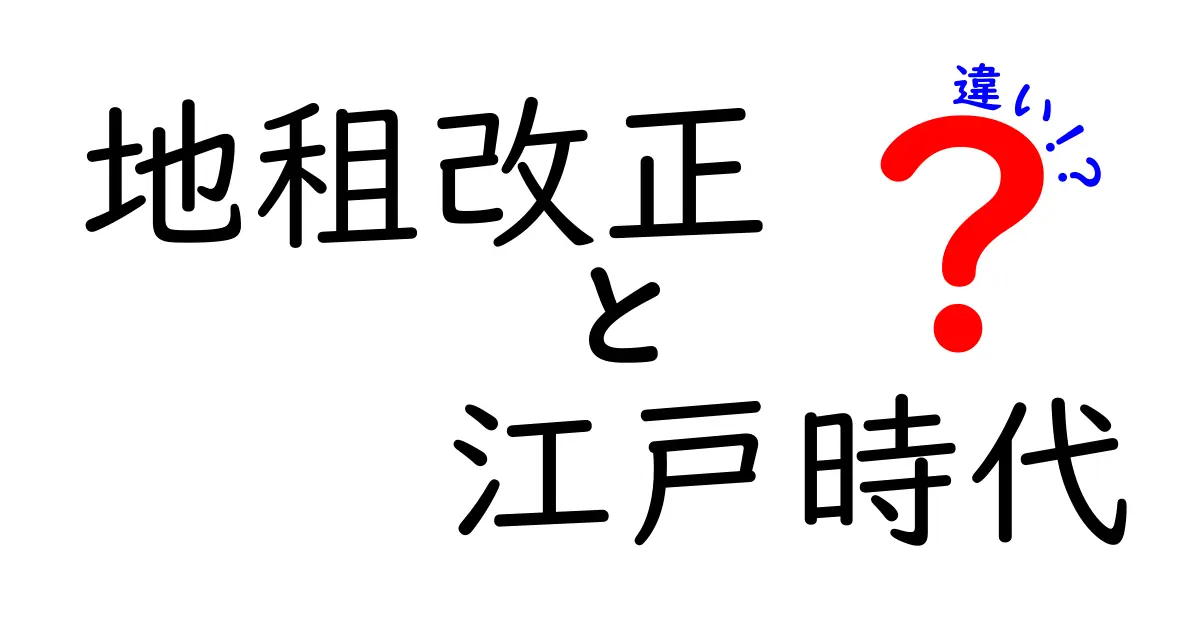
地租改正と江戸時代の違いを解説!近代化の鍵とは?
日本の歴史には、多くの重要な出来事がありますが、地租改正と江戸時代の違いは特に興味深いテーマです。ここでは、それぞれの特徴や背景、重要性についてわかりやすく解説します。
江戸時代の特徴
江戸時代は、1603年から1868年までの約260年間にわたる時代です。この時代は、平和で安定した時代とされ、商業や文化が発展しました。また、武士や町人、農民など、さまざまな身分制度が存在していました。江戸時代には、士農商の三つの階級が定められ、農業を基本とした経済が主流でした。
地租改正の背景
地租改正は、明治時代初期に実施された税制改革です。特に明治4年(1871年)から始まりました。この改革の目的は、近代的な国家の形成を目指すことでした。それまでの税制は、農民が支払う米などの物納税が多く、国の財政は不安定でした。
江戸時代と地租改正の主な違い
| 特徴 | 江戸時代 | 地租改正 |
|---|---|---|
| 時代背景 | 鎖国・平和な時代 | 近代国家の形成期 |
| 経済システム | 主に物納税 | 金納制度の導入 |
| 農民の地位 | 身分制度に基づく制約 | 地租を負担する一個人として |
| 目的 | 安定した社会の維持 | 近代化と財政基盤の強化 |
地租改正の影響
地租改正によって、農民は地租を現金で支払うことになり、経済活動がより活発化しました。また、地租改正により土地の所有権が明確になり、農民が土地を売買できるようになったため、農業の発展にもつながりました。
まとめ
地租改正は、明治時代に入ってからの日本の近代化を象徴する重要な改革です。一方、江戸時代は日本の伝統的な社会構造を形成した時代です。これら二つの時代は、日本の歴史を理解する上で欠かせない要素です。
地租改正という言葉を聞くと、明治時代の税制改革を思い浮かべる人が多いでしょう
でも、実はこの地租改正の背景には、日本が近代国家に向かうための大きな変化があったのです
もともとは、農民たちは米を納める物納税が一般的でしたが、地租改正によって現金での納税が求められるようになりました
これにより、農民たちの生活はどう変わったのでしょうか?農民は土地を売買できるようになり、経済活動に参加するチャンスが広がったのです
見方によっては、農民を一人の経済主体として扱う新しい時代の幕開けでもありましたね
前の記事: « 一条工務店と群馬の地域特性の違いとは?
次の記事: 「大分」と「大夫」の違いを知ろう!日本の言葉の奥深い世界 »