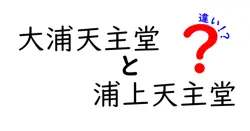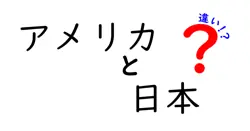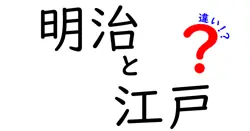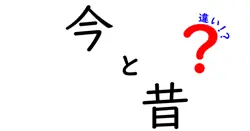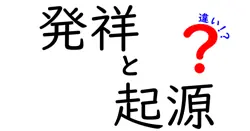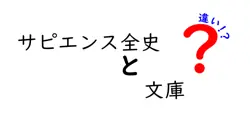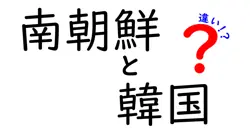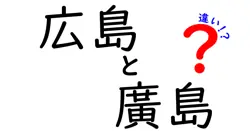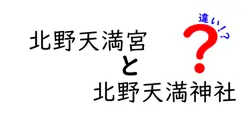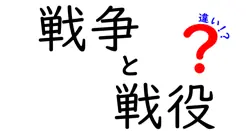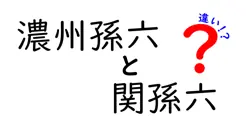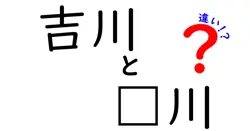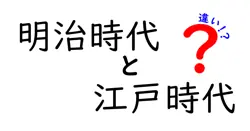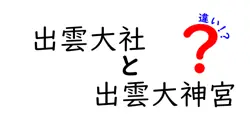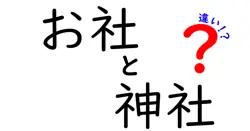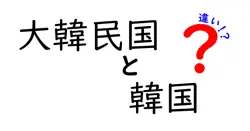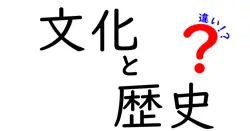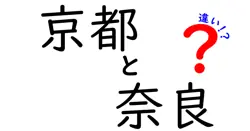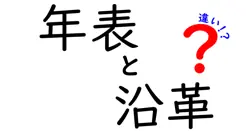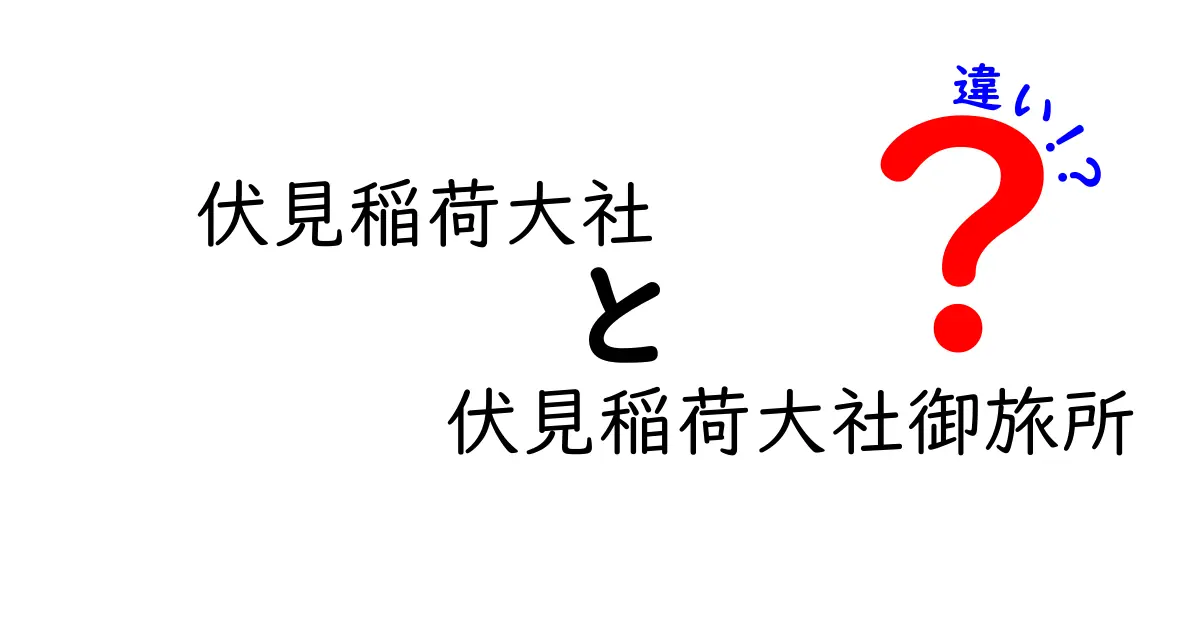
伏見稲荷大社と伏見稲荷大社御旅所の違いを詳しく解説!
日本の文化や歴史を知るためには、多くの神社や寺院について理解を深めることが大切です。特に京都には美しい神社がたくさんあります。その中でも、伏見稲荷大社は非常に有名です。しかし、伏見稲荷大社御旅所という場所も存在します。この二つの違いについて、わかりやすく解説していきます。
伏見稲荷大社とは?
伏見稲荷大社(ふしみいなりたいしゃ)は、京都市伏見区にある神社で、全国の稲荷神社の総本社です。創建は708年で、主祭神は宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ)です。この神社は、特に商売繁盛や五穀豊穣を祈るために多くの人々に訪れられています。特徴的なのは、朱色の鳥居が連なる「千本鳥居」で、訪れた人々が感動する美しい景観を楽しむことができます。
伏見稲荷大社御旅所とは?
一方、伏見稲荷大社御旅所(ふしみいなりたいしゃ おたびしょ)は、伏見稲荷大社の神様が出かける際に一時的に滞在する場所として設けられています。通常、神社とは異なる役割を持ち、特に祭りの際に重要視されます。御旅所は神様の移動を補助するための場所と考えられ、多くは大社の近くに位置しています。
二つの場所の主な違い
| 特徴 | 伏見稲荷大社 | 伏見稲荷大社御旅所 |
|---|---|---|
| 創建年 | 708年 | 特定なし(祭りの時に使用) |
| 主祭神 | 宇迦之御魂大神 | 同じく、祭りの際に関連 |
| 主な目的 | 商売繁盛、五穀豊穣を祈る | 祭りの際に神様の一時的な宿所 |
| 訪問する人々 | 多くの参拝者が訪れる | 主に祭りに参加する人々 |
まとめ
神社の役割や歴史を理解することで、日本の文化をより深く楽しむことができます。伏見稲荷大社と伏見稲荷大社御旅所、両方の場所の違いを知ることで、訪問時にそれぞれの意味や役割をしっかりと感じ取ることができるでしょう。次回の京都訪問の際には、ぜひ両方の場所を訪れて、その雰囲気を味わってみてください。
伏見稲荷大社と言えば、何といっても「千本鳥居」が有名ですよね
実は、この鳥居は参拝者が「お礼」と「お祈り」に寄付したものなんです
ですので、一つ一つの鳥居にはそれぞれのストーリーがあると言えるでしょう
このように、訪れると歴史や感謝の気持ちを感じられる場所なんですね
そんな中、御旅所は神様が一時的に滞在するところですが、これは古くからの習慣で、祭りや特別な儀式の際に大切にされています
神社の中でも特別な役割を持つ場所で、神様をもっと身近に感じることができますね