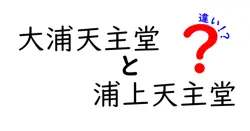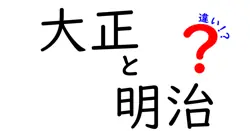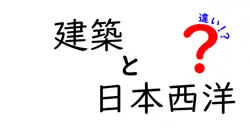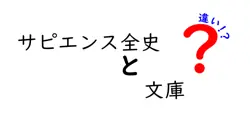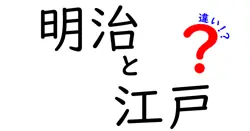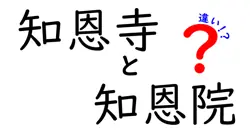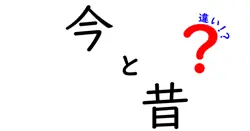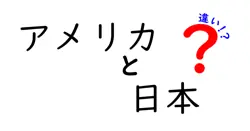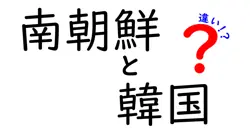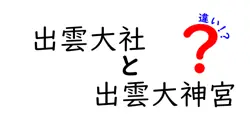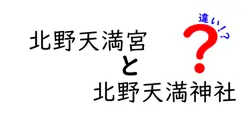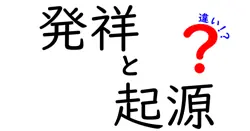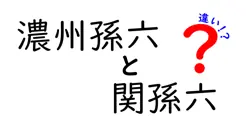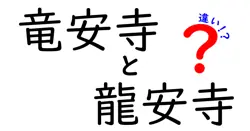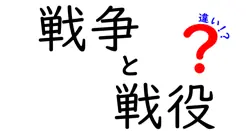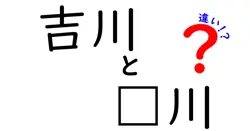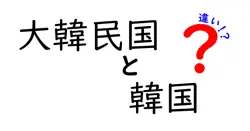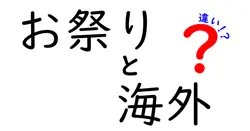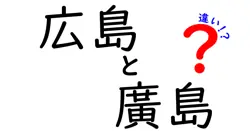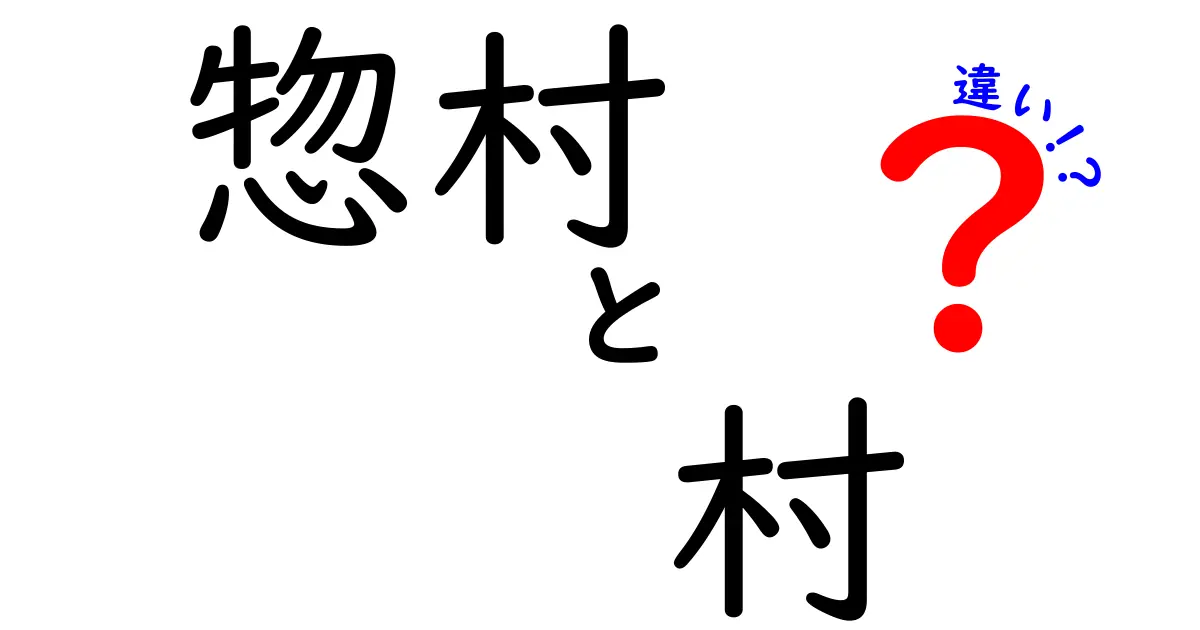
惣村と村の違いをわかりやすく解説!歴史的背景から見る特徴とは
日本の歴史や地理を学ぶ中で、時々「惣村」という言葉を耳にすることがあります。しかし、「村」という言葉とどう違うのか、正確には分からない人も多いのではないでしょうか?今回は、惣村と村の違いについて、歴史的な背景を交えながら分かりやすく解説します。
惣村とは?
惣村とは、中世の日本において、特に戦国時代から江戸時代初期にかけて存在した集落の一形態です。惣村は、農民たちが共同で土地を耕作し、村内の経済や防衛を協力して行うことを目的としていました。惣村では、村人全員が参加する合議制など、共同体としての特性が強く、人々は互いに助け合いながら生活していました。
村とは?
一方、村は現代の自治体の単位として広く知られています。村は、ある一定の面積に住む人々が集まり、地域社会を形成している場所を指します。現在の村は、行政上の区分であり、名や面積、住民数によって分類されます。村は個々の家庭や農業が基盤となっており、地域の特性によって異なる文化や風習があります。
惣村と村の違い
| 特徴 | 惣村 | 村 |
|---|---|---|
| 形式 | 戦国時代から江戸時代初期の共同体 | 現代の自治体単位 |
| 経済 | 共同での農作業や防衛 | 個々の家庭や農業 |
| 組織 | 合議制などの共同体的特性 | 行政的な管理・運営 |
| 時代背景 | 中世から近世 | 近現代以降 |
まとめ
今回は惣村と村の違いについて解説しました。惣村は中世の共同体としての特性が強いのに対し、村は現代の行政的な区分として機能しています。この違いを理解することで、日本の歴史や地域社会の成り立ちについて、より深く学ぶことができるでしょう。
皆さんは「惣村」に聞きなれたことがありますか?惣村は、特に中世の日本で見られた農民の共同体です
同じ土地で生活する村人たちが助け合い、時には防衛を備えたりもしていました
面白いのは、単に農業というだけでなく、そこでの人間関係が村の運営や文化に深く影響を与えていたことです
村の中での自分の役割がどれほど大切だったか、現代の私たちにも学ぶべきことが多いですね
前の記事: « 弾丸旅行と日帰り旅行の違いを徹底解説!あなたはどっち派?
次の記事: 教具と教材の違いは?わかりやすく解説します! »