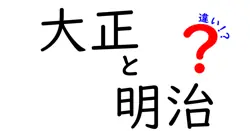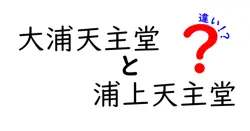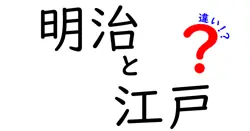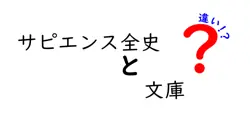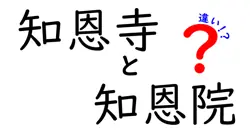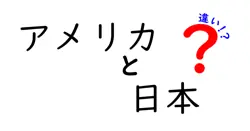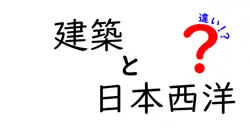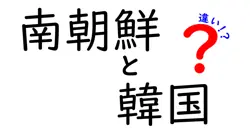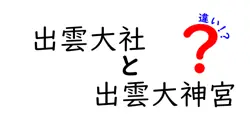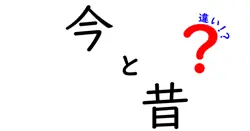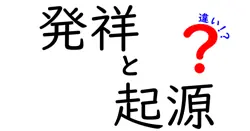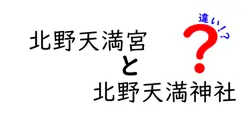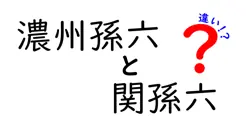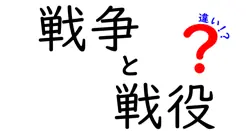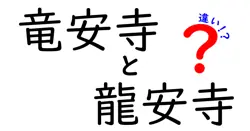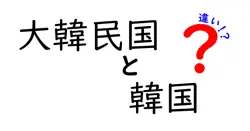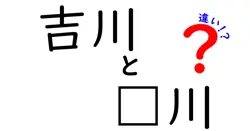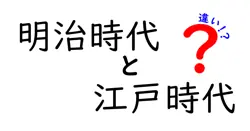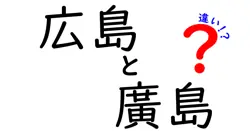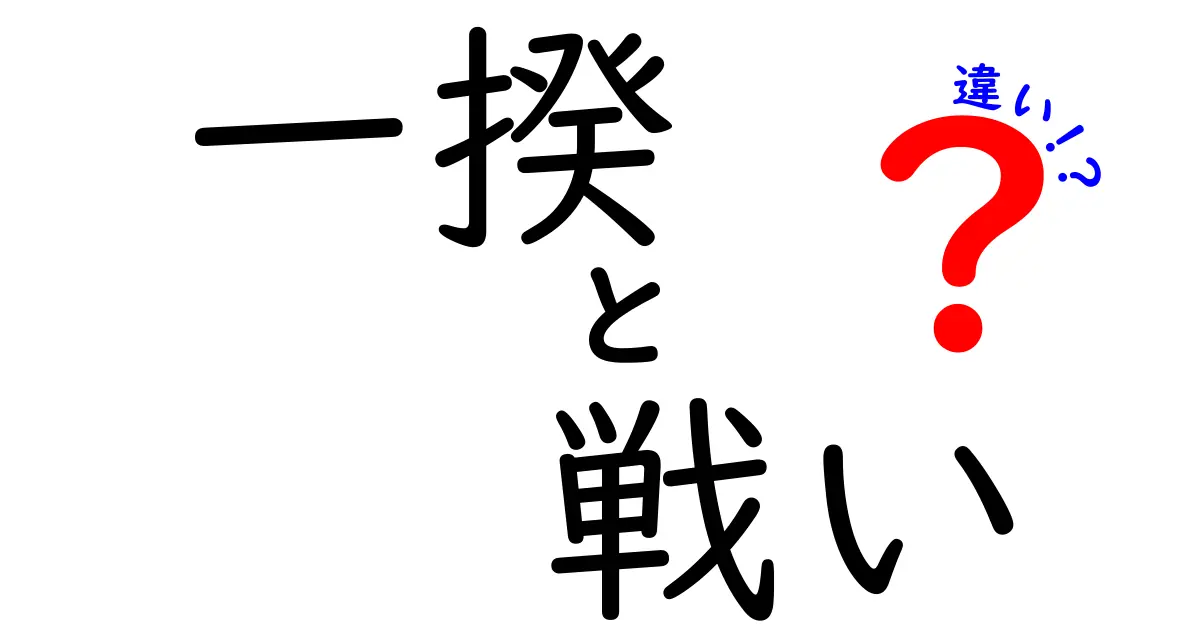
一揆と戦いの違いとは?歴史の中の意味と背景を探る
日本の歴史には、多くの戦争や反乱がありました。その中でも特に「一揆」と「戦い」という言葉は、しばしば混同されがちです。しかし、これらは異なった意味を持っており、それぞれ独自の背景があります。
一揆とは?
一揆は、主に農民や町人などの一般市民が、特定の目的を持って集まって抗議する運動のことを指します。日本の歴史の中で多く見られ、特に戦国時代や江戸時代に農民たちが土地の支配者に対して反発するときに行われました。
戦いとは?
戦いは、一般的に軍隊同士の戦闘を指します。敵対する勢力が、武器を用いて直接対決するものです。戦いは、大規模な軍事行動として行われ、国家や軍団単位での戦争に発展することもあります。
一揆と戦いの主な違い
| 項目 | 一揆 | 戦い |
|---|---|---|
| 参加者 | 一般市民(農民、町人など) | 軍隊(武士や兵士) |
| 目的 | 権利の主張や不満の解消 | 敵対勢力の征服や防衛 |
| 規模 | 比較的小規模 | 大規模な軍事行動 |
| 結果 | 権力者との交渉や和解が多い | 明確な勝敗がある |
歴史における一揆と戦いの例
日本の歴史には、一揆や戦いに関する多くの事例があります。たとえば、1569年に起こった「天正一揆」は、信長の支配に反対する農民たちが立ち上がった事例であり、この一揆によって土地の再分配が求められました。一方、戦いの例としては、1600年の「関ヶ原の戦い」が有名で、徳川家康が豊臣政権を覆すきっかけとなりました。
まとめ
一揆と戦いは、その参加者や目的、規模、結果において大きく異なります。歴史を学ぶ際には、それぞれの違いや背景を理解することが重要です。このような違いを認識することで、日本の歴史に対する理解がより深まることでしょう。
一揆って、普通の市民が立ち上がる運動なんだよね
でも、時代によっていろんな形があったんだ
たとえば、江戸時代の末期には、黒船来航の影響で民衆も大きな不満を感じていた
そんな時期に農民たちが集まって、新しい社会を求めて戦ったりした
これが「一揆」と呼ばれるもので、ただ単に暴力的に戦うわけではなく、もっとさまざまな背景や目的があった
もし一揆が起こらなかったら、今の政治や社会も全く違ったものになっていたかもしれないね
前の記事: « 災害と被害の違いを徹底解説!知っておくべき基本知識
次の記事: 争いと戦いの違いとは?理解を深めよう! »