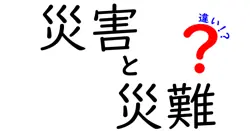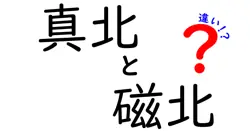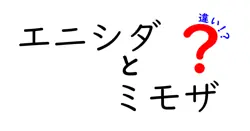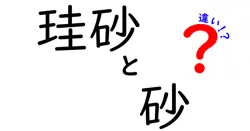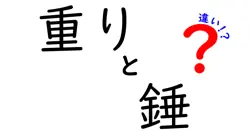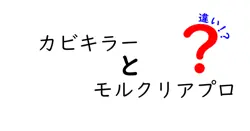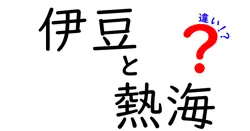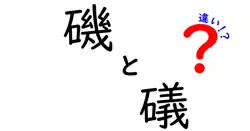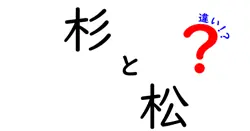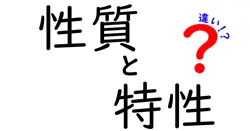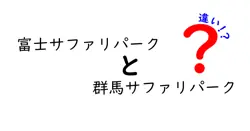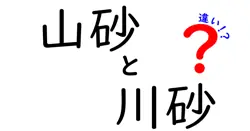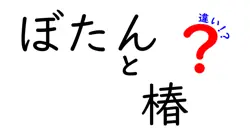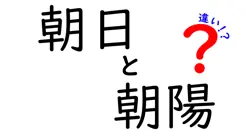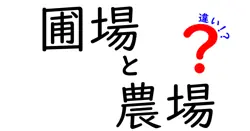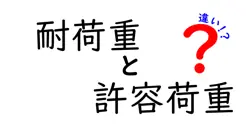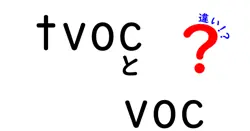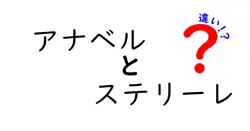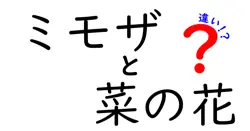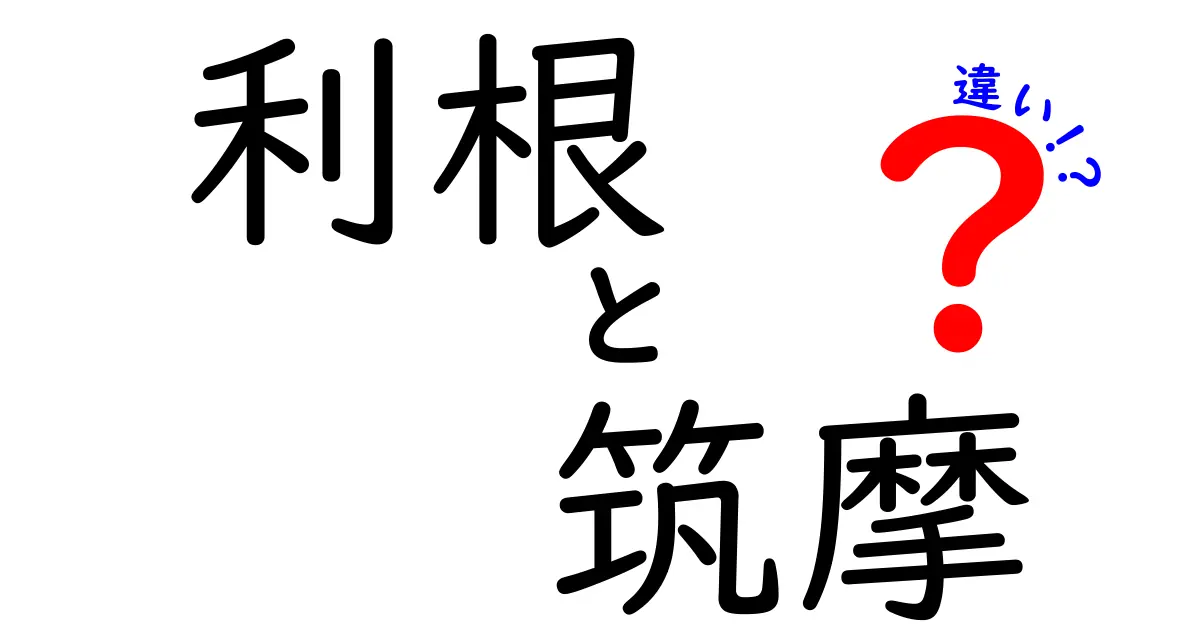
利根と筑摩の違いとは?それぞれの特徴を徹底解説
「利根」と「筑摩」と聞いて、どちらも聞いたことがある方も多いと思います。これらは日本においてとても重要な意味を持つ言葉ですが、具体的に何が違うのでしょうか?この記事では、利根と筑摩の特徴や違いをわかりやすく解説します。
利根とは
利根(とね)は、主に「利根川」を指すことが多いです。利根川は関東地方を流れる日本最大の川で、長さは約322キロメートルあります。利根川は、上流を群馬県で始まり、下流は茨城県で太平洋に流れ込みます。この川は、その大きさから多くの人々の生活に影響を与えており、農業や水運、発電などに利用されています。
筑摩とは
一方、筑摩(ちくま)は、主に「筑摩川」を指します。筑摩川は長野県を流れる川で、信州の大自然の中を流れています。筑摩川は、その美しい風景や清流で知られており、観光地としても人気があります。また、筑摩は同じく長野県の地域名や筑摩町、筑摩書房などでも使われており、その文化とも深い関わりがあります。
利根と筑摩の違いを表にまとめる
| 項目 | 利根 | 筑摩 |
|---|---|---|
| 所在地 | 関東地方 | 長野県 |
| 長さ | 約322キロメートル | 約96キロメートル |
| 主な利用 | 農業、水運、発電 | 観光、自然保護 |
| 文化的側面 | 地域の生活に深く根付いている | 美しい景観と親しみやすい文化 |
まとめ
利根と筑摩は、それぞれ異なる地域や文化を持つ重要な川です。利根川はその規模や利用方法から多くの人々の生活に影響を与え、筑摩川は自然環境や観光資源としての価値があります。どちらも日本の大切な資源ですが、その特徴や使われ方は非常に異なります。これらの違いを理解することで、それぞれの重要性がよりわかりやすくなるでしょう。
利根川の流域には多くの歴史的な出来事があったことを知っていましたか?特に、利根川は江戸時代に農業の発展に大きく寄与しました
それまでの下流の水害を防ぐために堤防が築かれたり、干拓が進められたりしました
その結果、広大な農地が生まれ、米作りが盛んになったのです
このように、利根川はただの川ではなく、かつての人々の生活に大きな影響を与えた存在なのです
次の記事: 延長コードと電源タップの違いをわかりやすく解説! »