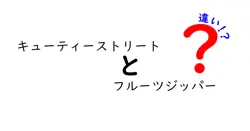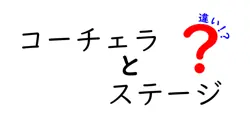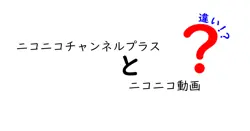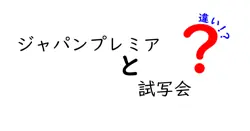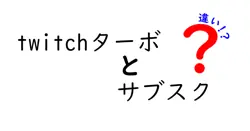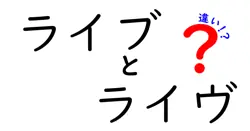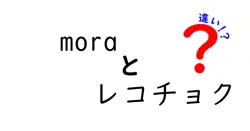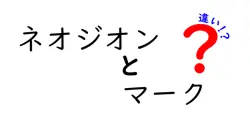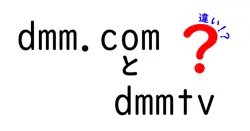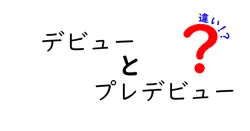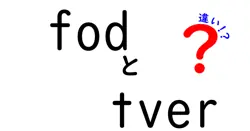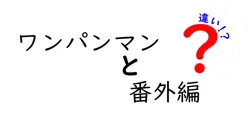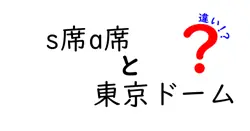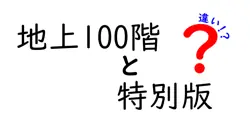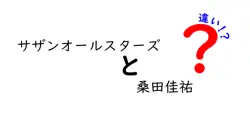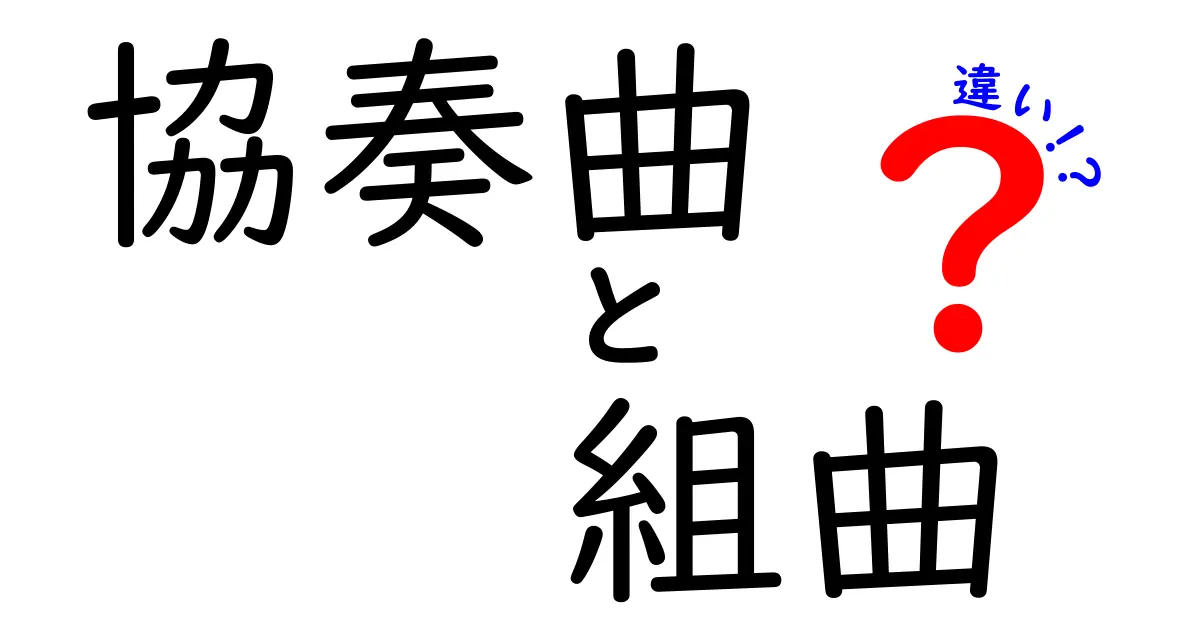
協奏曲と組曲の違いを徹底解説!音楽の世界を理解しよう
音楽にはさまざまな形式があり、私たちの耳を楽しませてくれます。その中でも「協奏曲」と「組曲」という用語は、特にクラシック音楽でよく耳にしますが、実際の違いは何なのでしょうか?今回はこの二つの音楽形式の違いについて、中学生でもわかりやすく解説します。
協奏曲とは?
協奏曲は、一般的に「オーケストラ」と「ソリスト(独奏者)」が互いに協力して演奏する音楽の形式を指します。協奏曲の特徴的な要素は以下の通りです:
- ソリストが主役となり、オーケストラがそれを引き立てる役割を果たす。
- 楽曲は通常、複数の楽章から構成されており、速い楽章や遅い楽章が組み合わされることが多い。
たとえば、バイオリンの協奏曲では、バイオリンが独奏部分を演奏し、その間にオーケストラが伴奏を行います。これにより、独奏者とオーケストラとの対話が生まれ、ダイナミックな演奏が実現するのです。
組曲とは?
組曲は、複数の独立した楽曲が集まって構成される音楽の形式です。主に以下の特徴があります:
- いくつかの楽章が順番に演奏され、それぞれが独立した楽曲である。
- 多くの場合、各楽章には異なるリズムやメロディーがある。
組曲は、特に舞踏音楽や劇音楽でよく利用されます。バッハやヘンデルなどの作曲家が多くの組曲を作成しており、各楽章は異なる感情や雰囲気を表現しています。
協奏曲と組曲の違いは?
さて、協奏曲と組曲の違いは明確です。協奏曲はソリストを中心とした作品で、オーケストラとの対話を楽しむ形式。一方、組曲は複数の楽曲の集まりであり、独立した楽章それぞれの表現が楽しめる形式です。
| 項目 | 協奏曲 | 組曲 |
|---|---|---|
| 中心的な演奏者 | ソリスト(独奏者) | オーケストラ全体 |
| 構成 | 主に3つの楽章 | 複数の独立した楽章 |
| 楽曲の関係 | 対話的 | 独立性 |
まとめ
協奏曲と組曲は、音楽の世界において重要な形式ですが、それぞれの特徴と違いを理解することで、より深く音楽を楽しむことができます。次回の音楽鑑賞の際には、ぜひこの知識を活かしてみてください!
「協奏曲」は音楽ではソリストが主役となる形式で、オーケストラと共に演奏します
面白いのは、ソリストの表現力によって曲の雰囲気が大きく変わる点です
たとえば、同じ曲でも演奏する人によって全く違った印象になりますし、その実力やスタイルが如実に表れます
実際、協奏曲を演奏するソリストは、非常に高い技術と感受性が求められます
そこが、この形式の奥深い部分であり、私たち聴き手が楽しむ要因にもなっています!
前の記事: « スウィングとブギウギの違いを徹底解説!どちらが楽しい?