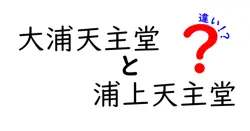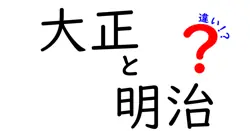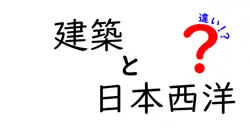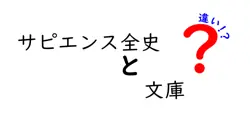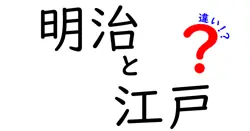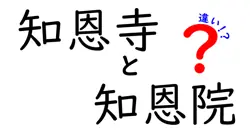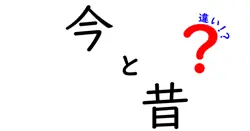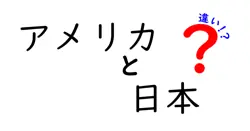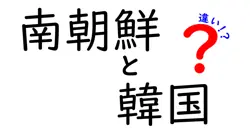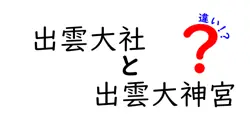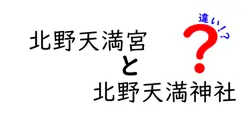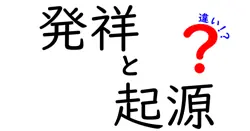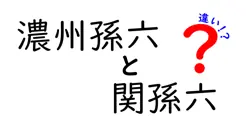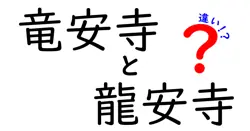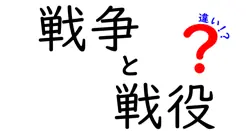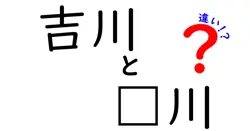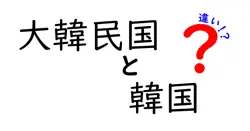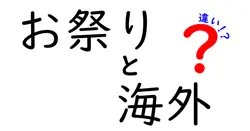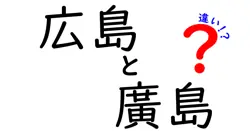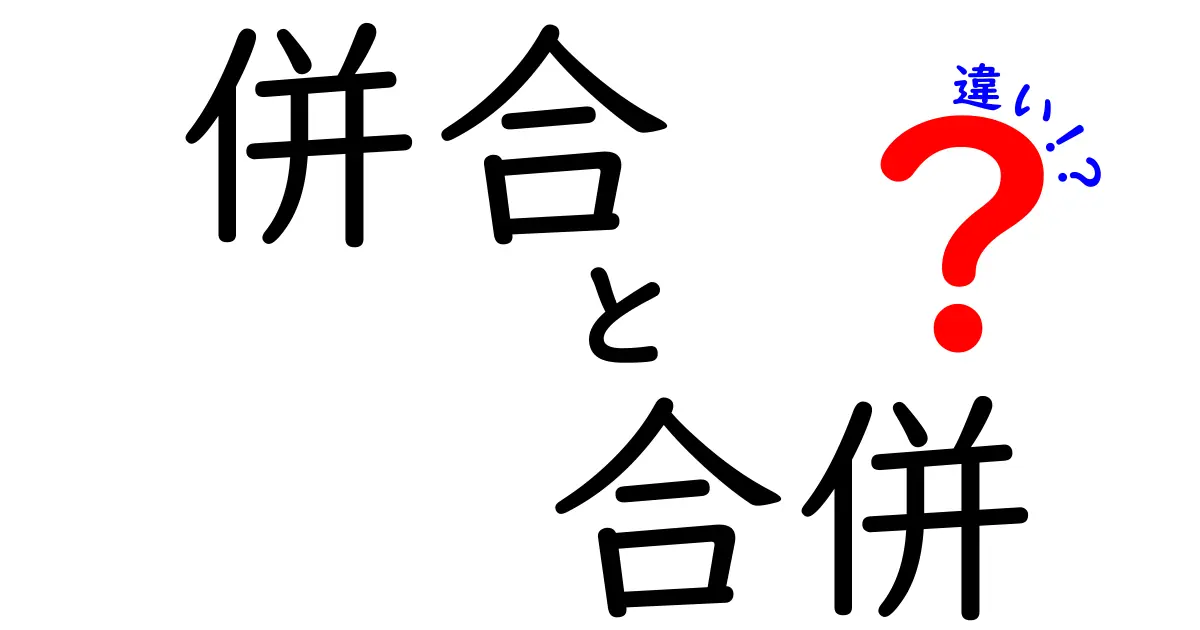
併合と合併の違いを徹底解説!その意味と使い分け
「併合」と「合併」という言葉、よく聞くけれど、実はその意味には大きな違いがあります。特にビジネスや歴史の文脈で使われることが多いため、混同しがちです。今回は、これらの違いについて詳しく見ていきましょう。
併合とは
「併合」とは、主に国や地域の統合を指します。例えば、ある国が他の国を自国に取り込む場合、「併合」という言葉が使われることが多いです。歴史的には、明治時代の日本による台湾や朝鮮半島の併合が有名ですね。併合された側は、もともとの独立した状態を失い、併合した国の一部として扱われます。
合併とは
一方で、「合併」は企業や団体が統合されることを指します。合併では、二つ以上の法人が一体となって新しい法人を形成することが一般的です。たとえば、A社とB社が合併して、C社を設立するという形です。合併は、経営の効率化や市場競争力の向上を目的として行われることが多いです。
併合と合併の違い
| 特徴 | 併合 | 合併 |
|---|---|---|
| 目的 | 国や地域を統合 | 企業や団体の統合 |
| 結果 | 一方が消失 | 新しい法人が設立 |
| 主な使用場面 | 歴史的な背景 | ビジネス上の戦略 |
まとめ
「併合」と「合併」はその目指すゴールも含めてだいぶ性質が異なります。国同士の関係を考えるときには「併合」を、ビジネス関連の話をする際には「合併」を使うことが大切ですね。これで、二つの用語の使い分けができるようになるでしょう!
ピックアップ解説
「併合」という言葉には歴史的な背景が多く含まれています
例えば、日中戦争の際に日本が中国の一部を併合したことがよく知られています
これにより、文化や社会が大きく変わる影響がありました
このような出来事は単なる国の統合だけでなく、その後の国際関係にも大きな影響を与えることがあるため、併合という言葉の理解は重要です
前の記事: « 事業譲渡と合併の違いをわかりやすく解説!
次の記事: 併発と合併の違いとは?分かりやすく解説します! »