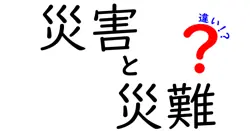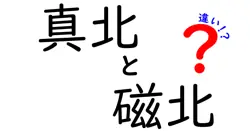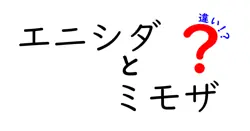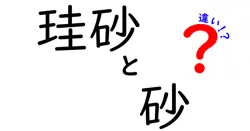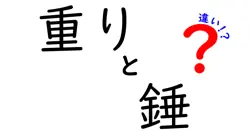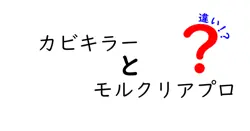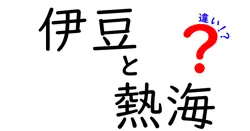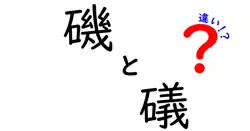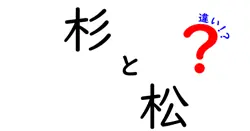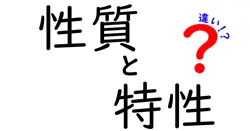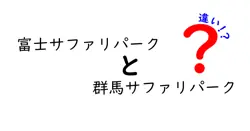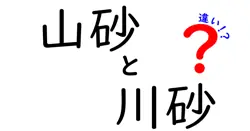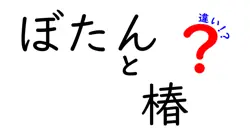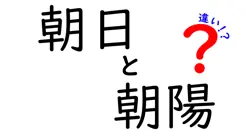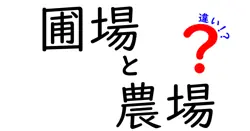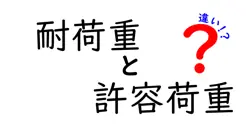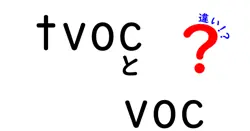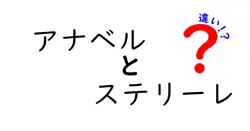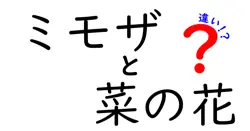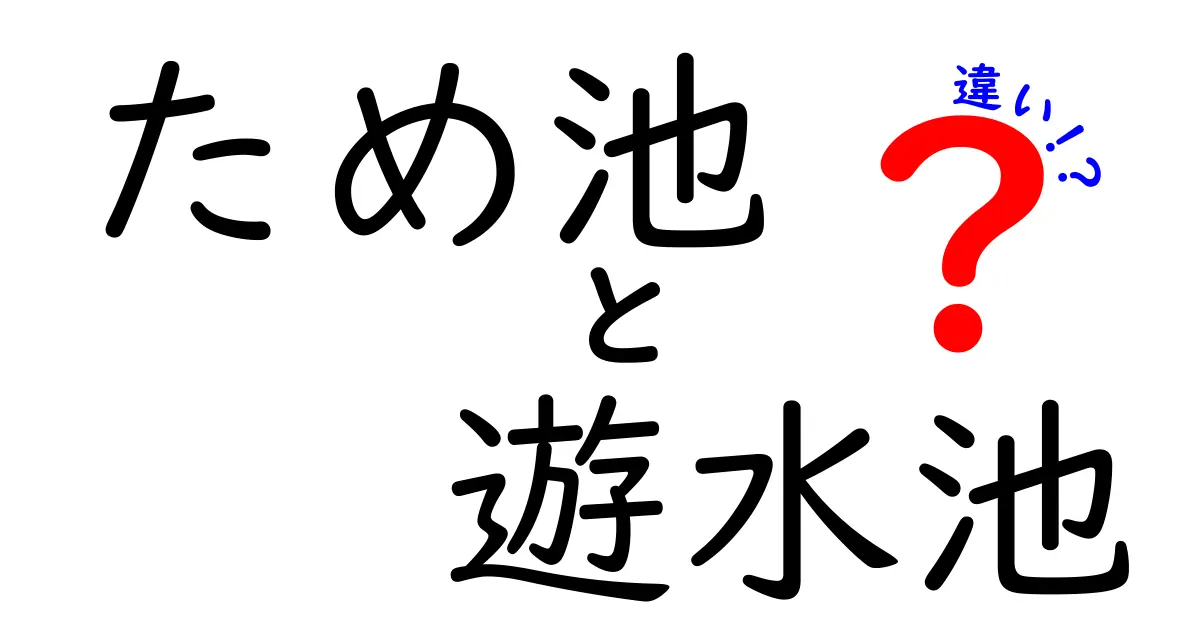
ため池と遊水池の違いを知ろう!それぞれの役割と特徴
日本の風景には、さまざまな水の貯蔵施設があります。その中でも「ため池」と「遊水池」はよく耳にする言葉ですが、具体的に何が違うのかを知っている人は少ないかもしれません。今回は、ため池と遊水池の違いについて詳しく解説していきます。
ため池とは?
ため池は、主に水田などで農業用水を供給するために作られた人工的な貯水池です。山や丘の上に作られることが多く、降雨によって集まった水を貯めておき、必要に応じて農作物に水を供給します。日本全国には約30,000か所のため池があり、地域によってその大きさや形はさまざまです。
遊水池とは?
一方、遊水池は、主に洪水対策として作られる貯水施設です。大雨が降ったときに一時的に水を貯め、河川の氾濫を防ぐ役割があります。遊水池は一般的に広くて浅く、雨が降った後には速やかに水が流れ出るように設計されています。これにより、周辺地域の浸水被害を軽減することができます。
ため池と遊水池の違い
ため池と遊水池は、役割と用途が異なります。ため池は農業用水の供給を目的とし、遊水池は洪水の防止が目的です。また、ため池は通常、農作物のために水を安定的に貯めることが重視されますが、遊水池は急な大雨に備えて一時的な水を貯めることが重視されます。
まとめ
| 項目 | ため池 | 遊水池 |
|---|---|---|
| 目的 | 農業用水供給 | 洪水対策 |
| 設計 | 深く、安定して水を貯める | 広くて浅く、一時的に水を貯める |
| 水の流れ | 農作物用に徐々に配分 | 雨水を迅速に排出 |
このように、ため池と遊水池は似ているようで全く異なる役割を持っています。私たちの生活や自然環境において大切な存在であり、それぞれの役割を理解することで、より良い環境づくりに繋がるかもしれません。
ため池は、その歴史も非常に興味深いんです
実は、ため池は奈良時代から作られており、当初は自然の水を貯めるために作られたんですよ
今では農業を支える重要なインフラとして成長しました
地方によってはため池の維持管理が地域の人々の協力によって行われていることもあり、地域愛や伝統とも深く結びついています
それに、ため池の周りには自然が豊かで、釣りやバードウォッチングを楽しむ人も多いんです!
前の記事: « ため池と貯水池の違いを徹底解説!あなたの知らない水の世界