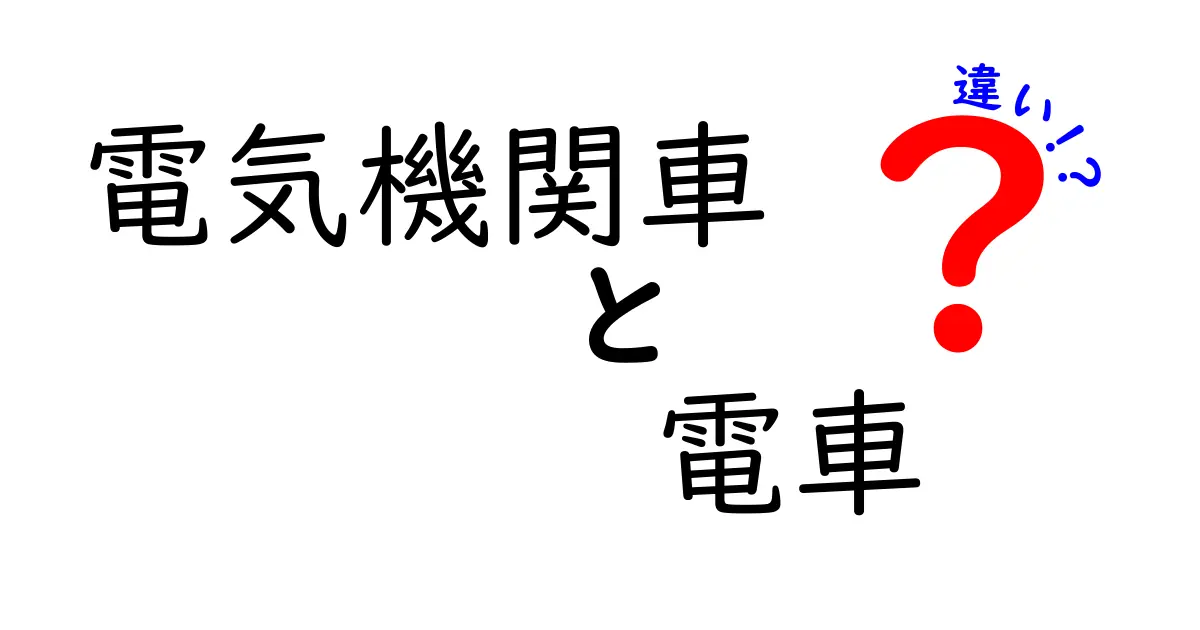
電気機関車と電車の違いを徹底解説!どちらも電気を使うけれど…
電気機関車と電車は、どちらも電気で動く乗り物ですが、その役割や構造には明確な違いがあります。この違いを理解することで、より深く鉄道について知ることができるでしょう。
電気機関車とは?
電気機関車は、主に列車を牽引(けんいん)するために使用される車両です。貨物列車や特急列車などを引っ張る役割を持っています。電気機関車は、電気を動力源として動き、架線から電力を取得します。また、電気機関車は通常、車両の一部ではなく、前後に他の車両を引く形で連結されています。
電車とは?
電車は一般的に、旅客を運ぶために設計された車両のことです。電気で駆動する電車は多くの種類がありますが、高速電車や通勤電車、地方の私鉄の電車など様々です。電車は自らが動力を持っており、他の車両を連結することもありますが、主に自分自身で乗客を運ぶために使われます。
電気機関車と電車の違い
| 項目 | 電気機関車 | 電車 |
|---|---|---|
| 主な機能 | 列車を牽引する | 旅客を運ぶ |
| 運転方法 | 他の車両を引く | 自ら運転 |
| 構造 | 動力車両 | 動力車両(電車単体) |
| 使用される場面 | 貨物列車や特急の牽引 | 通勤や観光のための旅客輸送 |
このように、電気機関車と電車は異なる目的に応じて設計されています。そのため、同じ電気を使っていても、その機能と構造には大きな違いがあるのです。
まとめ
今回は電気機関車と電車の違いについて解説しました。電気機関車は主に列車を牽引するためのものであり、電車は旅客を運ぶための車両です。これらの違いを理解することが、鉄道の世界をより楽しむことにつながるでしょう。
電気機関車に使われる架線は、日本の多くの鉄道路線に設置されていますが、特に新幹線や特急列車に多く見られます
これらの電気機関車は、通常、効率よく電気を受け取るためのパンタグラフという装置を使っています
パンタグラフがしっかり架線に触れることで、スムーズに電力を供給され、速い速度で列車を運行できるのです
運転席から見る、架線が近くにある風景は、電気機関車ならではの特別な景観ともいえるでしょう
前の記事: « 汽車と電車の違いを徹底解説!あなたはどちらを選びますか?





















