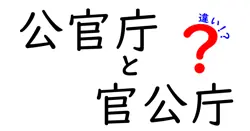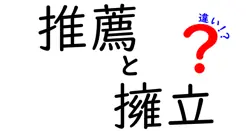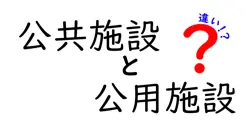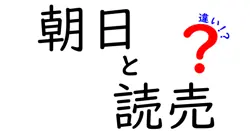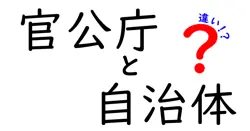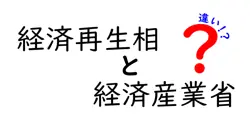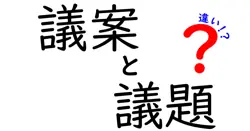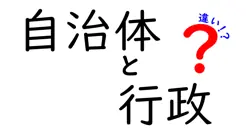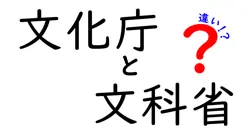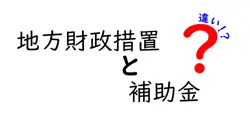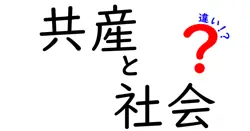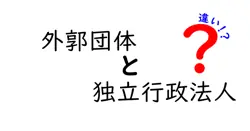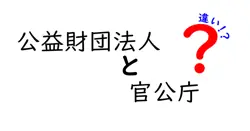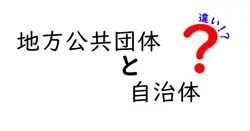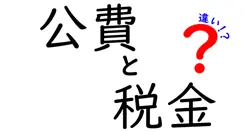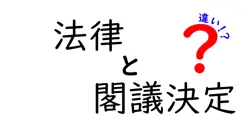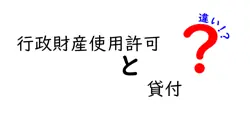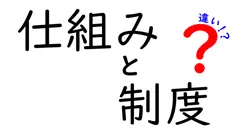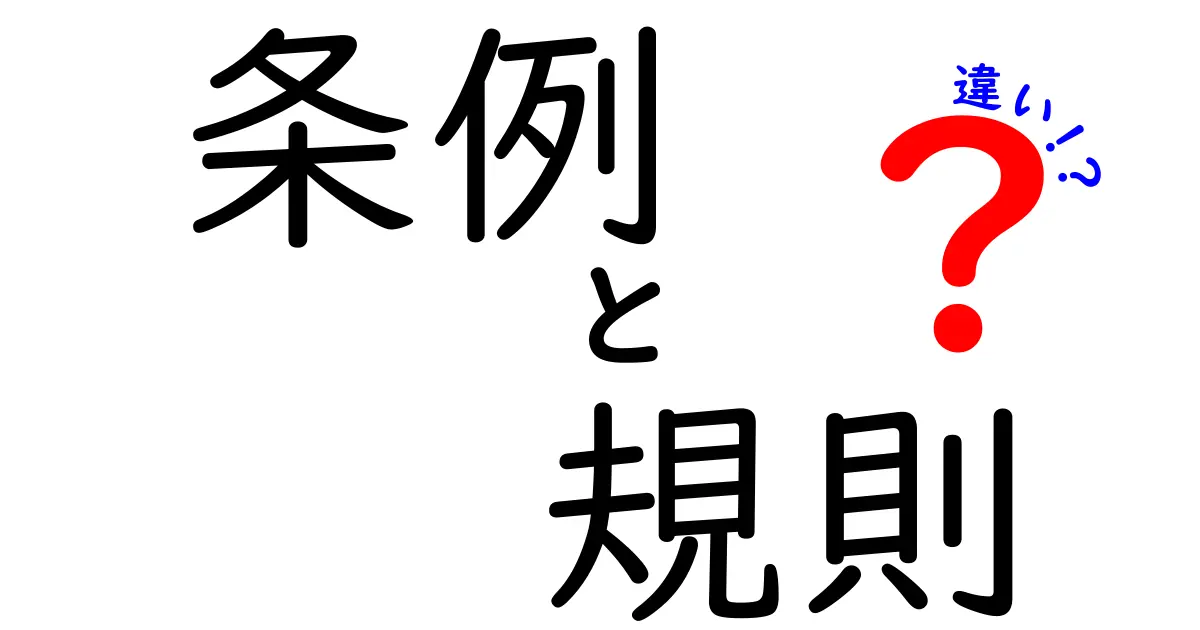
条例と規則の違いをわかりやすく解説!あなたの生活に影響を与える法律の世界
日常生活を送る中で、「条例」や「規則」という言葉に出くわすことがあるでしょう。しかし、これらの言葉の意味や違いについて、詳しく知っている人は少ないかもしれません。そこで、今回は「条例」と「規則」の違いについて、中学生でもわかりやすく解説します。
条例とは?
条例とは、地方自治体が制定する法律の一種です。都道府県や市町村が、その地域の特性や事情に応じて定めるルールのことを指します。例えば、ゴミの分別や公共施設の利用に関するルールが条例で決められることが多いです。
規則とは?
一方、規則とは、一般的に組織や団体が定めるルールや決まりごとのことです。たとえば、学校や企業にはそれぞれ独自の規則が存在します。これらはその組織内での行動をゲーム感覚で決定し、円滑な運営を助けるために設けられています。
条例と規則の違い
| 項目 | 条例 | 規則 |
|---|---|---|
| 制定者 | 地方自治体 | 組織・団体 |
| 法的効力 | 法律としての効力を持つ | 組織内での効力 |
| 対象範囲 | 地域全体 | 特定の組織や団体 |
| 例 | 騒音防止条例 | 学校の校則 |
まとめ
条例と規則は、同じ「ルール」という意味合いを持っていますが、制定者や内容、効力などに違いがあります。私たちの生活に直結するルールであるため、理解しておくことはとても重要です。これからも、法律やルールについて学んでいきましょう!
条例という言葉を聞いたことがある人は多いですが、実際にその内容を意識している人は少ないかもしれません
条例は市区町村などの地方自治体が地域に合ったルールを作るものです
例えば、ある町では、犬の飼い方や騒音の出し方に関する条例が定められているかもしれません
一方、規則は企業や学校などの内部で定めるもの
校則が厳しすぎると学生がつらい思いをすることもありますね
このように、条例と規則は私たちの生活に日々影響を与えていますが、どちらもその場その場に合った形で作られていることを忘れないようにしましょう
前の記事: « 方程式と関数の違いをわかりやすく解説!
次の記事: 正四面体と立方体の違いを徹底解説!形状と特性を徹底比較 »