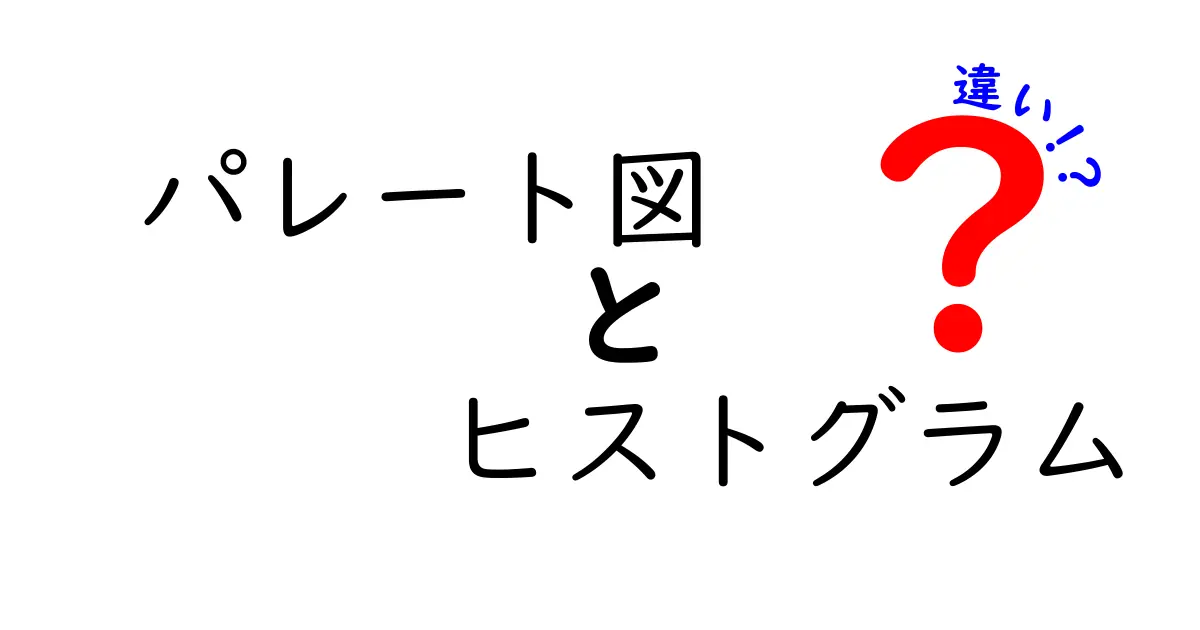
パレート図とヒストグラムの違いとは?初心者にも分かる使い方解説!
データを視覚化するための方法はたくさんありますが、今回は「パレート図」と「ヒストグラム」という二つの図について解説します。この二つの図は似ているようで、実は用途や目的が違うのです。それぞれの特徴を見ていきましょう。
パレート図とは?
パレート図は、データを特定の順序で表示するグラフです。具体的には、ある問題の原因や影響がいくつあるのかを判断するために使います。通常、パレート図は棒グラフと折れ線グラフを組み合わせて、左側に数量、右側に累積割合を示します。この図は、ヴィルフレド・パレートが提唱した80対20の法則(パレートの法則)に基づいています。
ヒストグラムとは?
ヒストグラムは、データの分布を示すための図です。たとえば、テストの点数や身長、体重など、連続した数値データを一定の範囲(ビン)に分けて、その範囲ごとにデータの数(度数)を示すことができます。横軸にデータの数値、縦軸にその数値がどれだけの頻度で出現したかを表します。
パレート図とヒストグラムの違い
| 項目 | パレート図 | ヒストグラム |
|---|---|---|
| 目的 | 問題の原因や影響を特定 | データの分布を理解 |
| 表示形式 | 棒グラフと折れ線グラフ | 棒グラフのみ |
| データの種類 | カテゴリーデータ | 連続データ |
| 例 | クレームの原因分析 | 身長や体重の分布 |
まとめ
パレート図は、問題の優先順位をつけるために役立ち、ヒストグラムはデータの分布を把握するために有用です。どちらもデータ分析には欠かせないツールですが、使い方が異なるため目的に応じて使い分けることが大切です。
パレート図は、実際に業務の現場でも頻繁に利用されています
たとえば、製品のクレームがどのような理由で発生しているかを分析するとき、パレート図を使うと「80%のクレームの原因は20%の事項から来ている」という事実が見えやすくなります
これを使うことで、限られたリソースをどこに優先的に投資すれば良いかが一目でわかるんですよ
前の記事: « データマイニングと機械学習の違いをわかりやすく解説!
次の記事: 統計学と統計科学の違いをわかりやすく解説! »





















