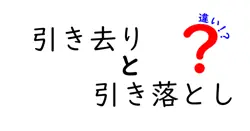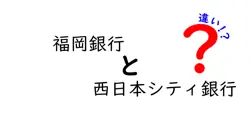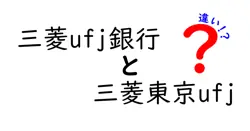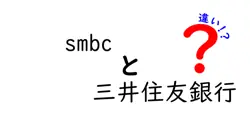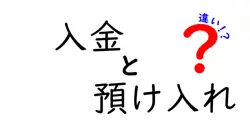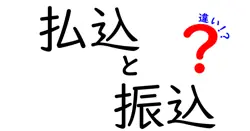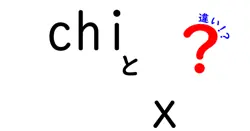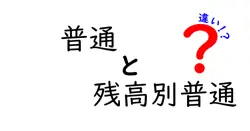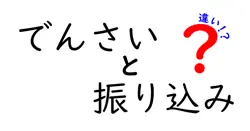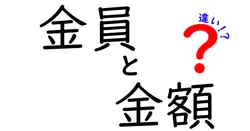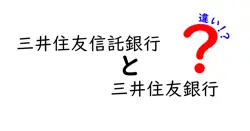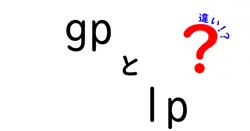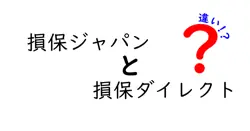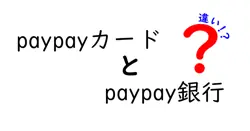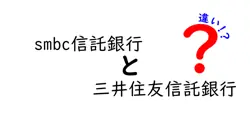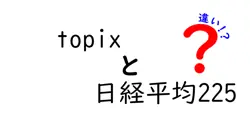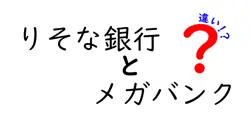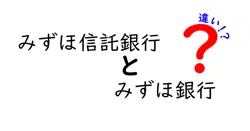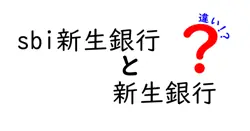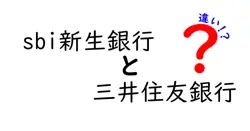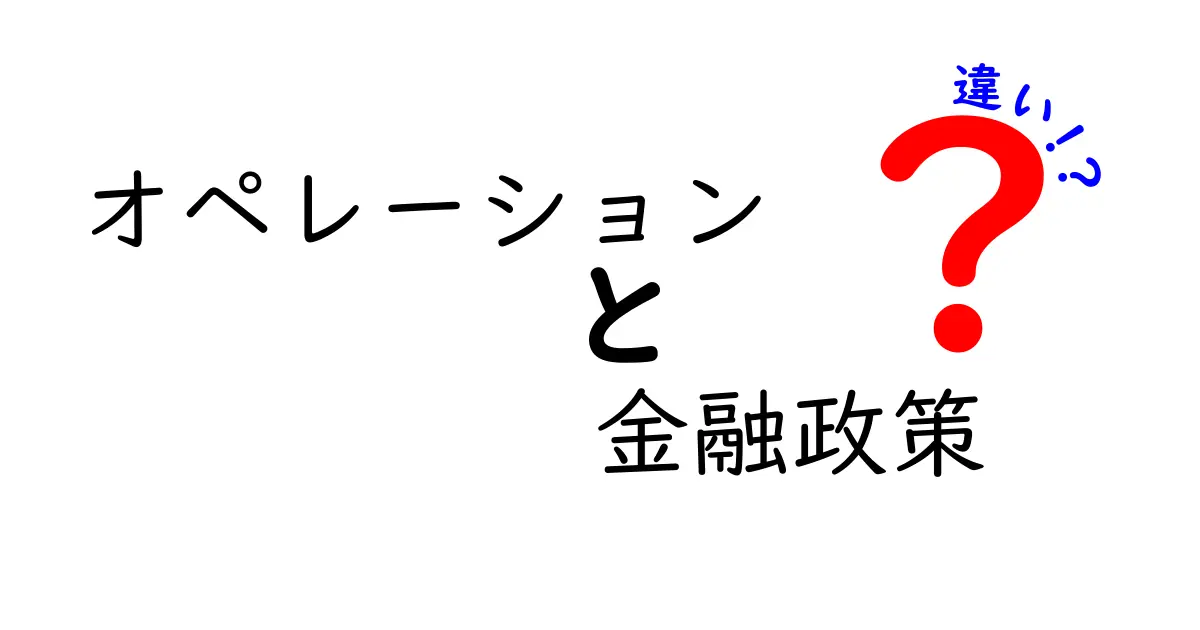
オペレーションと金融政策の違いとは?知っておきたい基本知識
私たちが普段聞く「オペレーション」と「金融政策」という言葉。これらは経済や金融に関する重要な概念ですが、その意味や役割は異なります。今回は、これらの違いについてわかりやすく解説します。
オペレーションとは?
オペレーションという言葉は一般的に「操作」や「運営」という意味で使われますが、金融の世界では特に「中央銀行が金融市場で行う取引」を指します。例えば、中央銀行が金利を下げたり、通貨供給量を調整したりすることがこれにあたります。
オペレーションの種類
| 種類 | 説明 |
|---|---|
| 公開市場操作 | 中央銀行が国債などを売買することで、金融市場の流動性を調節する行為。 |
| 金利操作 | 基準金利を変更することで、借入れや投資のコストに影響を与える。 |
金融政策とは?
金融政策は、中央銀行が経済の安定や成長を目的に行う一連の政策のことを指します。具体的には、金利の調整や通貨の供給量の増減を通じて、インフレーションやデフレーションをコントロールします。また、雇用の最大化を目指すこともあります。
金融政策の二つの主な手段
- 拡張的金融政策:経済を活性化するために金利を下げたり、通貨を増やしたりする政策。
- 引き締め的金融政策:インフレーションを抑制するために金利を上げたり、通貨を減らしたりする政策。
オペレーションと金融政策の違い
では、オペレーションと金融政策はどのように異なるのでしょうか?
- 目的の違い:オペレーションは具体的な取引や操作を指しますが、金融政策はもっと大きな目標、つまり経済全体の安定や成長を目指します。
- 実施の範囲:オペレーションは金融政策の一部であり、具体的な手段の一つです。
まとめると、金融政策は経済全体を見据えた政策全般を指し、オペレーションはその実行手段の一つとして位置づけられます。これらの違いを理解することで、経済や金融のニュースもより深く理解できるようになるでしょう。
オペレーションと金融政策の関係を考えると、面白い事実があります
金融政策の実施においては、オペレーションが非常に重要なのです
たとえば、金利を調整して経済を刺激する際に、中央銀行はまずオペレーションを通じて市場の流動性を管理します
そのため、オペレーションが上手くいけば、金融政策の効果も高くなると言えます
逆にオペレーションが不十分だと、金融政策も効果を発揮しづらくなるのです
こうした仕組みを理解することで、金融の世界がもっと身近に感じられるようになるでしょう
前の記事: « FRBと中央銀行の違いとは?その役割と機能を徹底解説
次の記事: サラ金と信販会社の違いを分かりやすく解説!どっちが自分に合うの? »