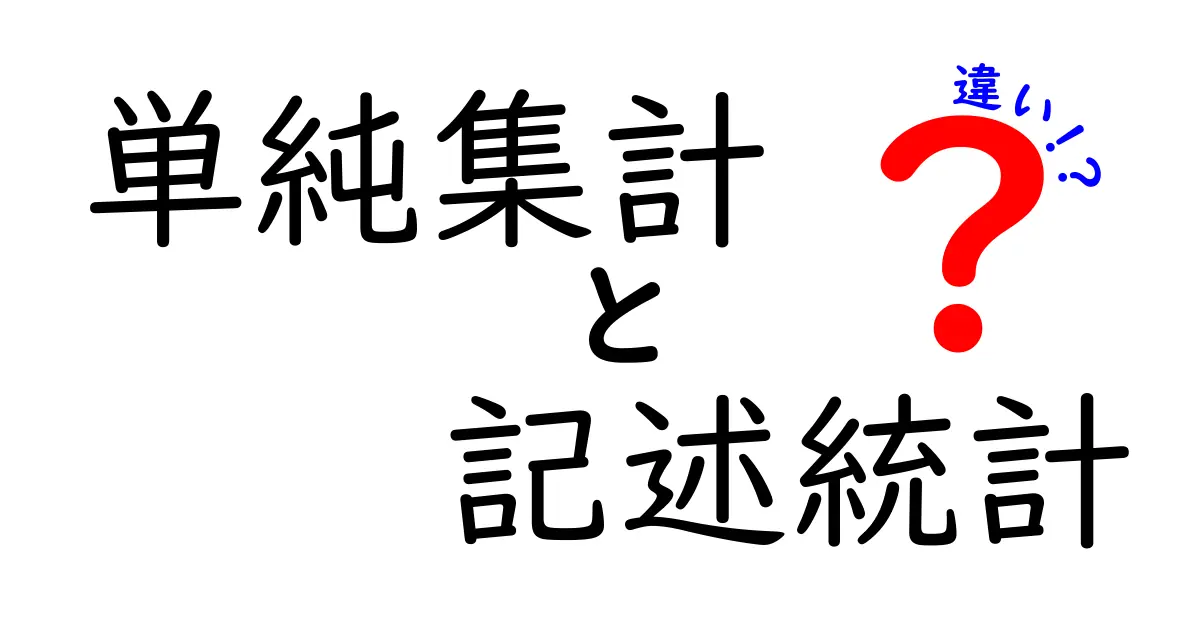
単純集計と記述統計の違いをわかりやすく解説!
統計学は、さまざまなデータを扱うための重要なツールです。特に、データを整理し、分析する方法として、単純集計と記述統計の2つがあります。これらは似ているように思えますが、実は大きな違いがあります。今回の記事では、この2つの違いについて、わかりやすく解説します。
単純集計とは?
単純集計とは、特定のデータを数えたり、合計したりすることです。例えば、クラスの生徒の好きな果物を調査し、いくつの生徒がリンゴ、バナナ、オレンジを選んだかを数えることが、単純集計にあたります。これはデータを単純に集約して、わかりやすくする作業です。
| 果物 | 生徒数 |
|---|---|
| リンゴ | 10人 |
| バナナ | 5人 |
| オレンジ | 3人 |
記述統計とは?
一方、記述統計は、データの特徴をまとめて、理解しやすくするための手法です。集計したデータをもとに、平均値、中央値、範囲、標準偏差などの統計量を計算し、データの傾向を示すことができます。記述統計は、データの全体像を把握するのに非常に役立ちます。
単純集計と記述統計の違い
- 単純集計:データを数えたり、足したりすることに焦点を当てている。
- 記述統計:データの特徴を分析し、要約するための計算を行う。
単純集計はデータを「数える」という作業ですが、記述統計はデータの「意味を理解する」ための広範な分析手法です。例えば、さまざまな果物の人気を単純集計で調べた後、記述統計でそのデータの平均的な人気や分布を考察することができます。
まとめ
単純集計と記述統計は、データを扱う上で非常に重要な概念です。集計が済んだデータを記述統計でより深く分析することで、より多くの情報を得ることができます。これらの違いを理解することで、統計学を効果的に活用できるようになります。
単純集計は本当にシンプルで、例えば、好きな色を調査して15人中5人が青が好きと言ったら、その結果をただ数えるだけです
一方で、記述統計に進むと、全体の好きな色の「傾向」が見えてきます
例えば、青が5人、赤が3人、緑が7人だとしたら、どうやって「人気の傾向」を考察しますか?平均を出したり、分布を考えたりする深堀りが始まるんですね
単純集計で「数」を数える楽しさもありますが、記述統計で「理解」を深める楽しさにも気づけるといいですね!
次の記事: 要約統計と記述統計の違いをわかりやすく解説! »





















