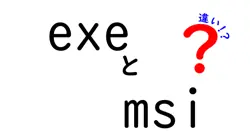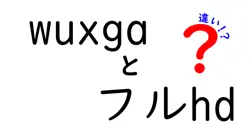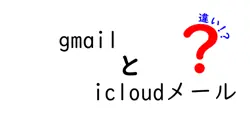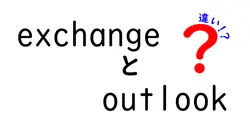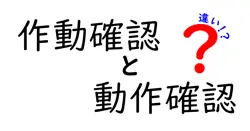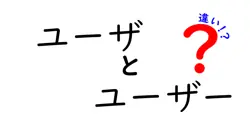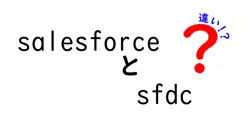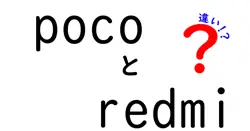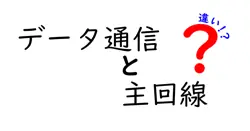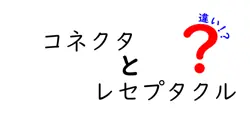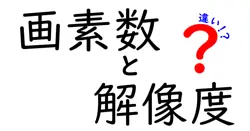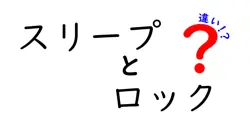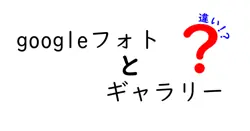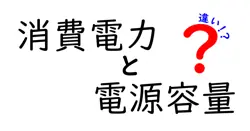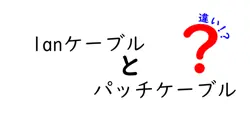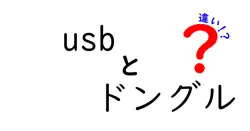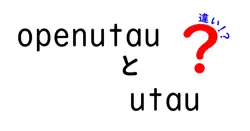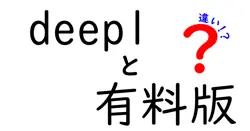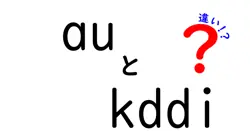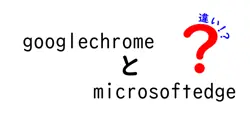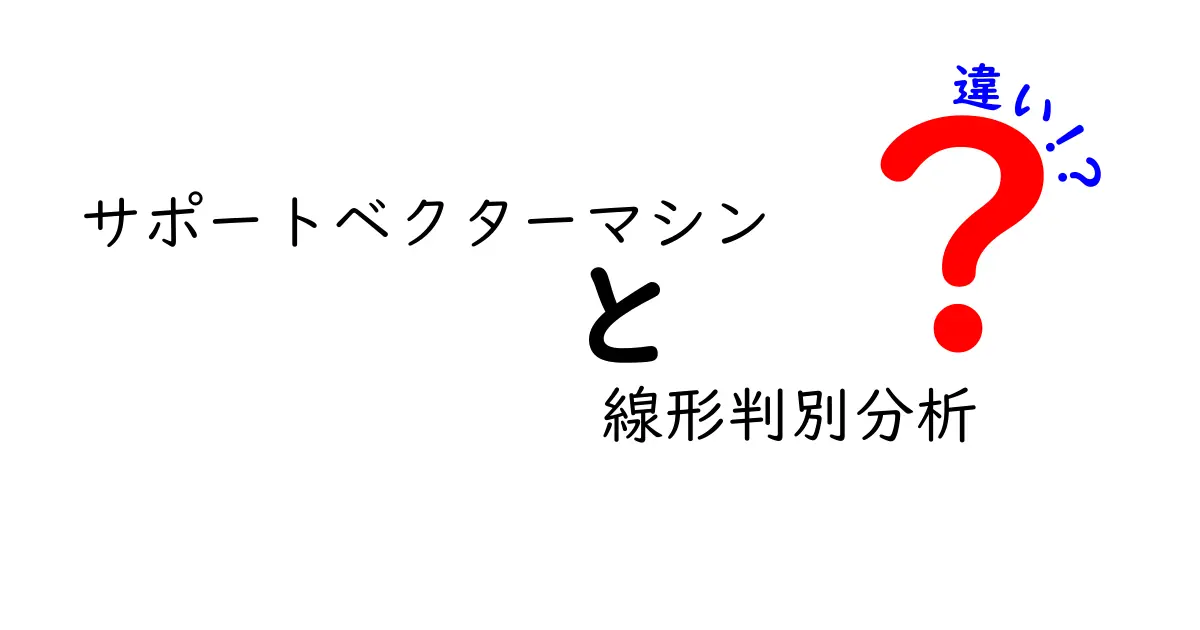
サポートベクターマシンと線形判別分析の違いを徹底解説!
データ分析や機械学習の分野でよく耳にする言葉、サポートベクターマシン(SVM)と線形判別分析(LDA)。これらはどちらもデータを分類するための方法ですが、実はそのアプローチや考え方は異なります。今回はこの二つの手法の違いについてわかりやすく解説していきます。
サポートベクターマシン(SVM)とは?
サポートベクターマシン(SVM)は、データを分けるための最適な境界線(またはハイパープレーン)を見つける手法です。この境界線は、できるだけ多くのデータポイントから離れた位置に配置されます。SVMの特徴は、“サポートベクター”と呼ばれる、一番境界線に近いデータポイントを基にしていることです。これによって、分類の精度が向上し、過学習を防ぐことができます。
線形判別分析(LDA)とは?
一方、線形判別分析(LDA)は、異なるクラスのデータを最適に分離するための線形変換を用いた手法です。LDAは、クラス間の分散を最大化し、クラス内の分散を最小化することを目指します。これによって、各クラスが明確に分けられるような新しい空間を作り出します。
サポートベクターマシンと線形判別分析の比較
| 特徴 | サポートベクターマシン(SVM) | 線形判別分析(LDA) |
|---|---|---|
| 目的 | 最大のマージンを持つ境界線を見つける | クラス間の分散を最大化する |
| データの扱い | サポートベクターを基にする | 全データを使用する |
| 適用範囲 | 非線形問題にも対応可能 | 線形問題に特化 |
| 計算の複雑さ | 比較的高い | 比較的低い |
まとめ
サポートベクターマシンと線形判別分析はどちらも有用な分類手法ですが、それぞれのアプローチには明確な違いがあります。SVMはデータのエッジに焦点を当て、一方でLDAはデータ全体の分散を考慮します。用途に応じて、どちらの手法を使うかを選ぶことがポイントです。
サポートベクターマシン(SVM)は、ただのデータの分け方だけではなく、実はデータを扱う際に「マージン」が大事です
マージンとは、境界線から最も近いデータポイントまでの距離のこと
この距離が大きいほど、その分類が正確であることを意味します
だから、SVMでは「近い」データを意識して分析をするのです
面白いのは、SVMの後ろには最適化問題が隠れていて、最小限のエラーでデータを分類できるように数学的に工夫されているところです
データを扱うときにはこうした視点も大切です!