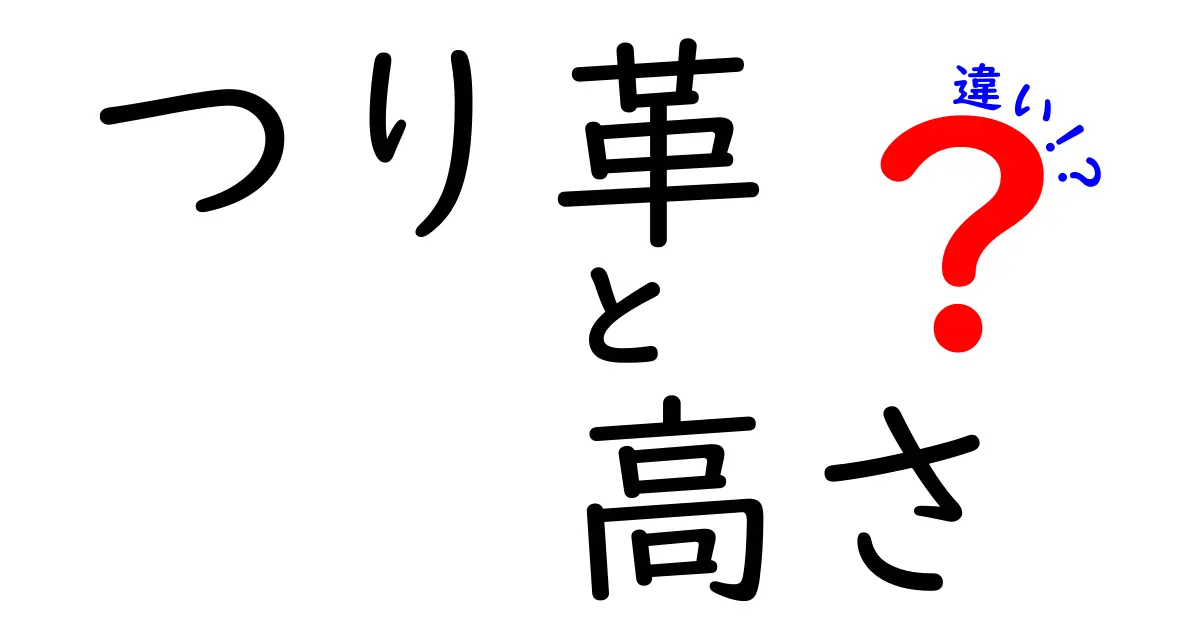
知って得する!つり革の高さの違いとその影響とは?
通勤や通学で毎日利用する電車やバス。そこで目にする「つり革」。このつり革の高さには実はさまざまな違いがあります。あなたはその違いを知っていますか?つり革の高さには、利用者の身長や年齢、さらには使用する車両の種類など、多くの要因が影響しています。ここでは、つり革の高さの違いについて詳しく解説していきます。
つり革の高さが違う理由
まず、つり革の高さが違う理由について考えてみましょう。一般的に、つり革は車両の設計によって高さが異なります。また、利用者の身長を考慮し、つり革は比較的手が届きやすい位置に設置されていますが、これは大人だけでなく子どもや高齢者も考慮に入れた設計となっています。
各交通機関のつり革の高さ比較
| 交通機関 | つり革の高さ(cm) |
|---|---|
| 普通電車 | 210~235 |
| 新幹線 | 200~220 |
| バス | 180~210 |
| 地下鉄 | 190~230 |
つり革の高さがもたらす影響
つり革の高さが合っていないと、体格や身長に関わらず、つり革を使うのが不便になります。例えば、子どもや背の低い人にとっては高すぎるつり革は使いにくく、逆に高齢者にとっては低すぎるつり革では姿勢を崩してしまう可能性があります。そのため、適切な高さで設計することが重要です。
まとめ
つり革の高さには様々な違いがあり、交通機関によっても異なります。それぞれの交通機関がどのような利用者を想定しているのかを理解することで、より快適な移動ができるようになるでしょう。次回、電車やバスに乗るときには、つり革の高さにも注目してみてください。
つり革の高さは、実は利用者の身長や年齢によって変わります
例えば、電車では210~235cmですが、バスでは180~210cmと少し低めです
これは、つり革を使う人が手を伸ばしやすいように考慮されているからです
高齢者の方や背が小さい子どもでも使いやすい設計が大切ですね
また、例えば満員電車でつり革が高すぎると、持つことができずにバランスを崩すこともあります
そんな細やかな配慮があるんですね!





















