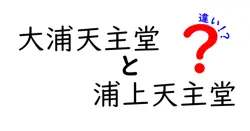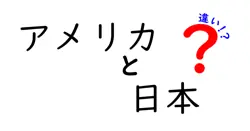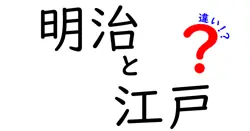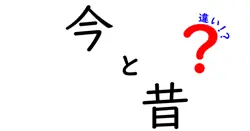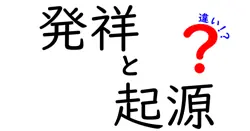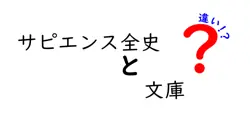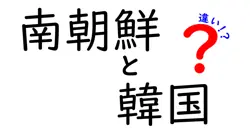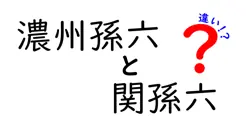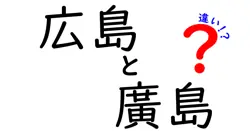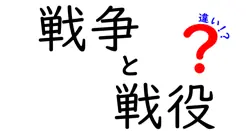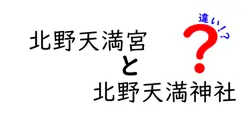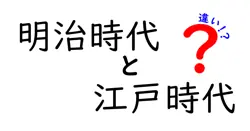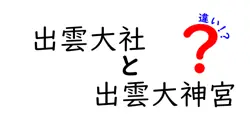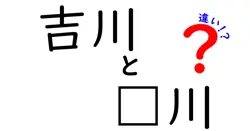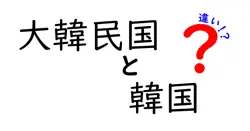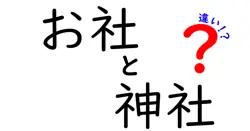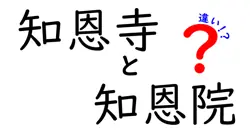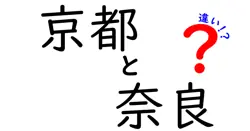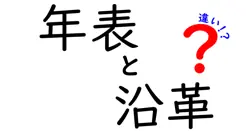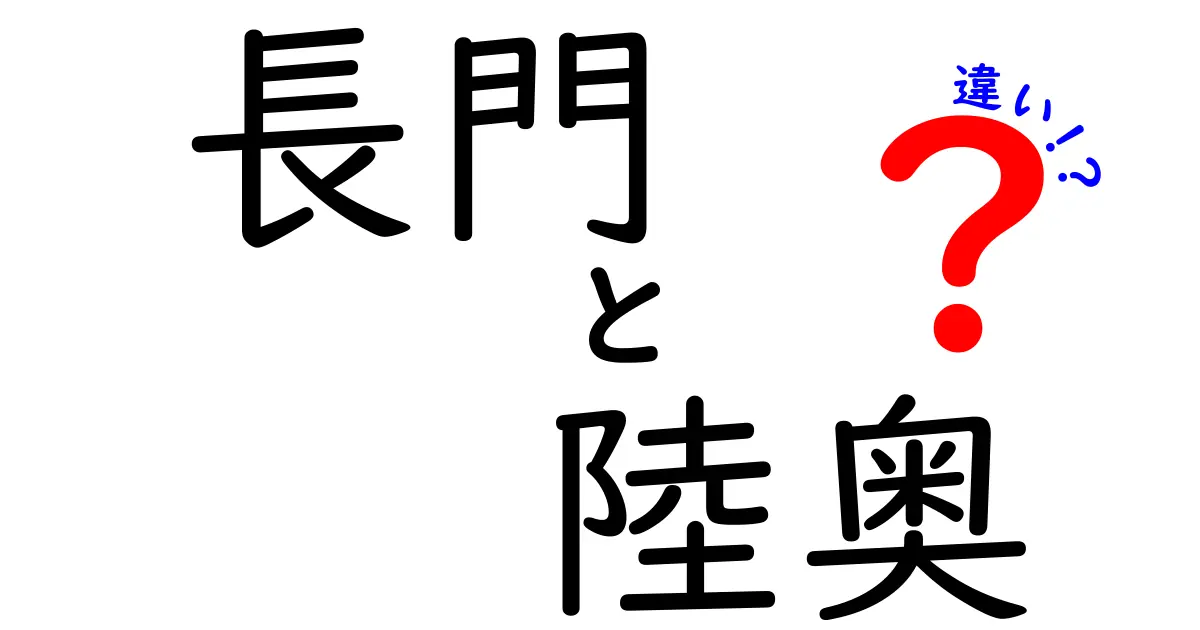
長門と陸奥の違いを徹底解説!歴史や特徴を分かりやすく紹介
日本の艦船の中には、「長門」と「陸奥」という名前の艦があります。これらはどちらも戦艦であり、同じ時期に造られたためしばしば混同されがちですが、それぞれに独自の特徴があります。
長門と陸奥の基本情報
| 艦名 | 進水年 | 排水量 |
|---|---|---|
| 長門 | 1917年 | 35,000トン |
| 陸奥 | 1917年 | 35,000トン |
歴史的背景
「長門」と「陸奥」は、共に大日本帝国海軍の戦艦として建造されました。長門が進水したのは1917年であり、その後、陸奥も同じ年に進水しました。この時期は第一次世界大戦の影響を受け、日本の艦船も進化を遂げていました。
主な違い
長門と陸奥にはいくつかの違いがあります。まず、艦名の由来ですが、長門は「長門国」から、陸奥は「陸奥国」から名付けられています。また、設計思想にも違いがあり、長門は速度重視の設計、陸奥は装甲重視の設計でした。
運命の違い
運用歴にも大きな違いがあります。長門はその後、太平洋戦争にも参加し、複数の戦闘で名を馳せました。一方、陸奥は1943年に中破し沈没してしまいます。これにより、戦艦としての運命には大きな差が生まれました。
まとめ
長門と陸奥の違いは、名前や設計の思想、歴史の背景にあります。それぞれの艦船が持つ特徴を知ることで、より深い理解が得られるでしょう。
ピックアップ解説
「長門」は近代戦艦の一つで、太平洋戦争での活躍が目立ちますが、その名でも融通無碍に扱われた艦船です
興味深いのは、艦名そのものが地域名に由来していること
実際、長門は山口県に、陸奥は青森県に存在した古代の国名なんですよ
こうした名前の背景を知ると、それぞれの艦の理由や歴史にもっと関心がわいてきますね
前の記事: « 清水と純水の違いを徹底解説!あなたはどちらを選ぶべき?
次の記事: あぶりと清水の違いとは?知られざる特徴と楽しみ方を解説! »