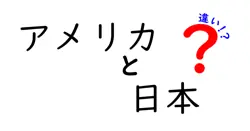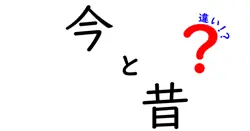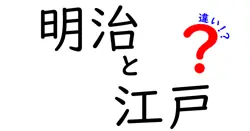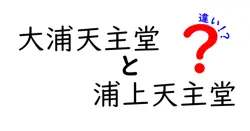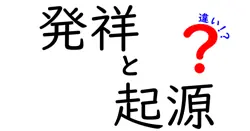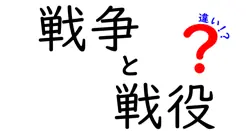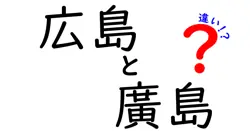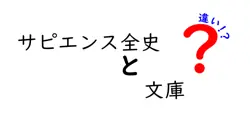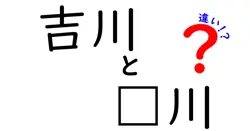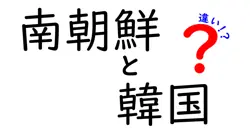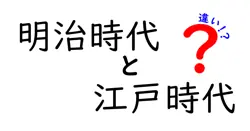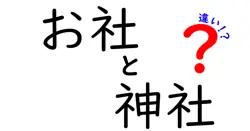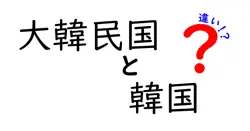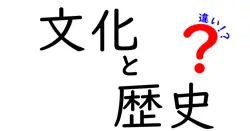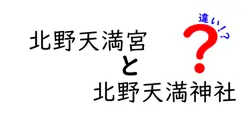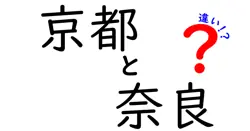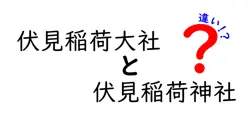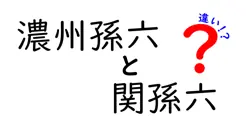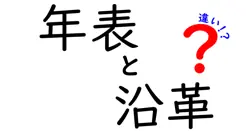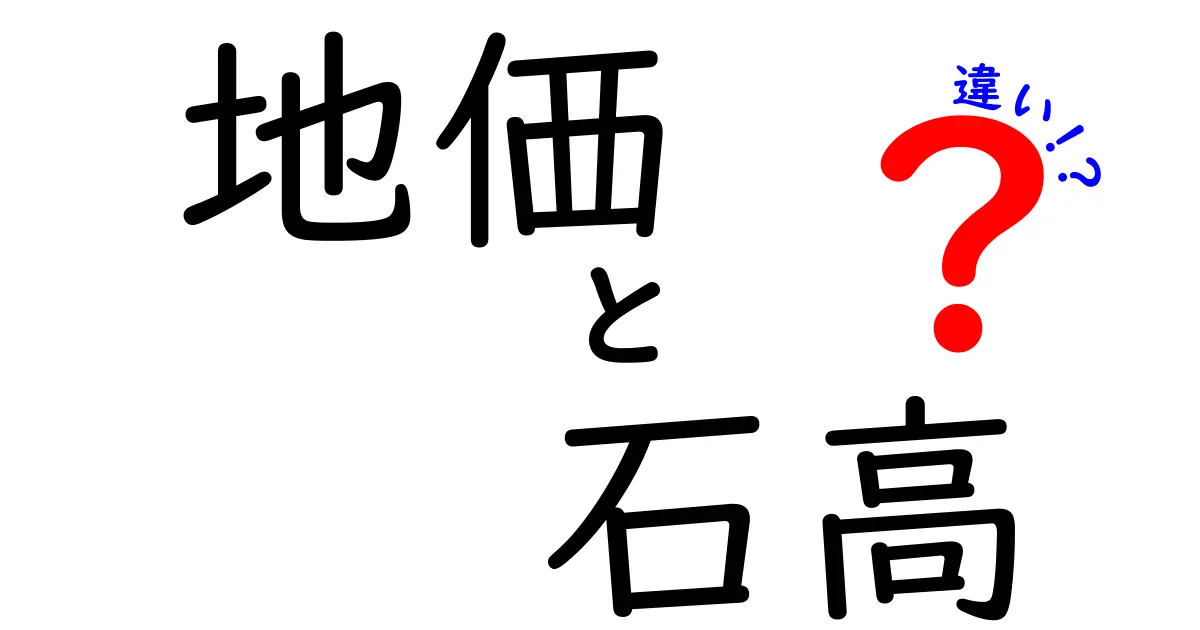
地価と石高の違いを分かりやすく解説!土地の価値を知る鍵
地価と石高という言葉、みなさんは聞いたことがありますか?土地に関する重要な指標ですが、どちらも似ているようで違うものです。今日は、この二つの違いについて分かりやすく解説していきます。
地価とは?
まず、地価(ちか)について説明します。地価とは、「土地の価格」や「土地の値段」を意味します。一般的には土地の売買や貸借において、どれくらいの金額で取引されているかを示すものです。たとえば、田舎の土地と都会の土地では、地価は大きく異なることが多いです。
石高とは?
次に、石高(いしだか)について見てみましょう。石高は、主に江戸時代の日本で使われた言葉です。農地の生産性を示す指標で、「その土地で一年間に収穫できる米の量」を表します。つまり、1石(こく)は約180リットルの米に相当します。この値が多いほど、その土地が豊かであることを示します。
地価と石高の違いを見える化する
| 項目 | 地価 | 石高 |
|---|---|---|
| 意味 | 土地の価格 | 農地の生産性 |
| 使用時期 | 現代 | 江戸時代 |
| 基本単位 | 金額(円) | 容量(石) |
| 適用範囲 | 全国的 | 主に農地 |
地価は主に売買や貸借に関わるもので、石高はその地がどれくらい農作物を生産できるかを示す指標であることが分かります。つまり、地価は「土地の市場価値」、石高は「土地の生産性」を示しているのです。
まとめ
地価と石高は、土地に関する重要な指標ではありますが、それぞれ異なる意味を持っています。地価はお金の観点から、石高は生産性の観点から土地を理解するために役立ちます。土地に関心がある方は、ぜひこの二つの違いを覚えておきましょう!
地価と石高は、土地に関連する言葉ですが、実は時代背景が違うんです
地価は現代の土地の値段を指しますが、石高は江戸時代に使われた生産性の指標
じつは、石高が高い土地は江戸時代は大名にとって、戦の資源としても大切な存在でした
土地によっては、米がたくさん取れる場所は、豊かな暮らしを支える一番の鍵だったんですね
今の地価はその名残のようにも思えますね!
前の記事: « 地価と坪単価の違いを徹底解説!不動産を理解する鍵とは?
次の記事: 借地と底地の違いを知って不動産を賢く活用しよう! »