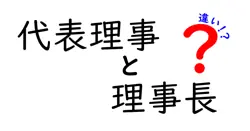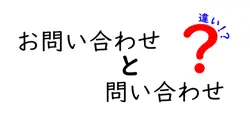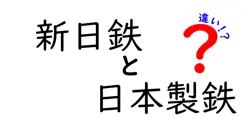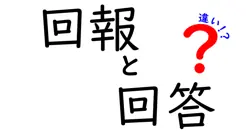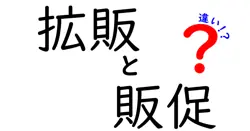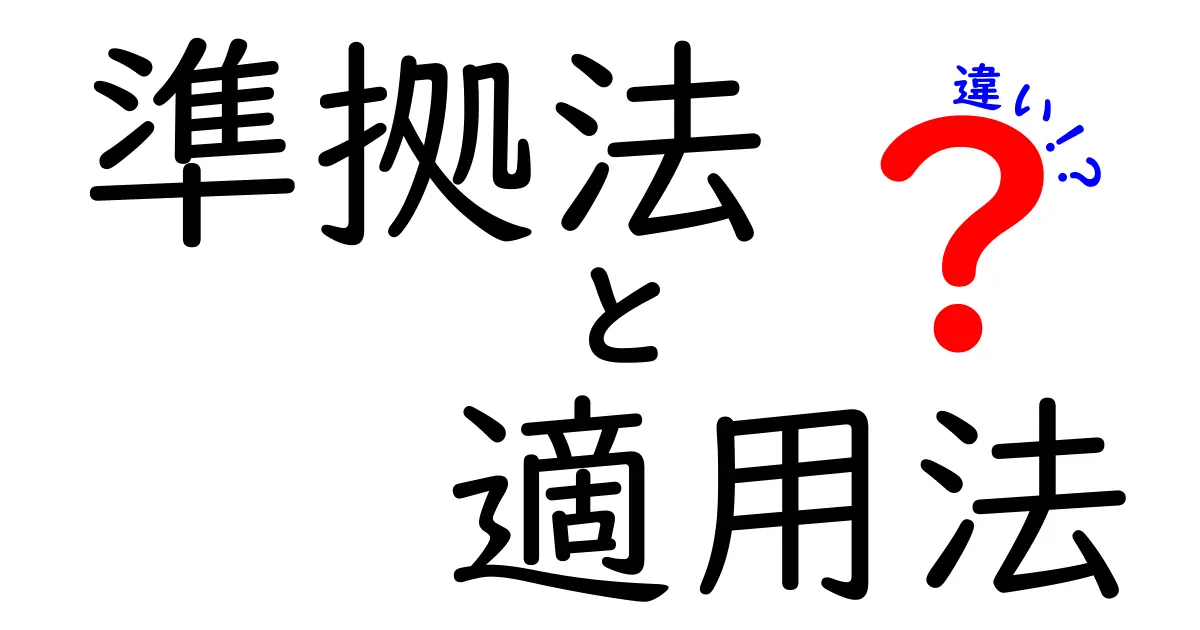
準拠法と適用法の違いを徹底解説!法律の世界をわかりやすく理解しよう
法律に関する用語には、様々なものがありますが、特に「準拠法」と「適用法」は非常に重要な概念です。このふたつの法律用語は、しばしば混同されることがありますが、実は異なる意味を持っています。今日は、その違いを中学生でもわかりやすく説明していきます。
1. 準拠法とは?
準拠法とは、ある契約や法律関係がどこの法律に基づいているかを示すものです。つまり、準拠法は、当事者が合意した法律のことを指します。例えば、AさんとBさんがある契約を結ぶときに、『この契約は日本の法律に基づくものとする』と記載した場合、日本の法律がその契約の準拠法になるのです。
2. 適用法とは?
一方、適用法とは、具体的な事例において適用される法律のことです。これは、準拠法のもとで実際に適用される法律ということになります。例として、もしAさんとBさんの契約が日本の法律によるものである場合、日本の民法がその契約に適用される法律、つまり適用法となります。
3. 準拠法と適用法の違い
| 項目 | 準拠法 | 適用法 |
|---|---|---|
| 定義 | 契約などの基準となる法律 | 具体的に適用される法律 |
| 例 | ある契約が日本の法律に基づく場合 | その契約に対して民法が適用される場合 |
| 役割 | 法律関係を明確にする | 具体的なトラブルに対処する |
このように、準拠法と適用法は互いに関連しつつも、その役割や意味は異なります。法律を学ぶ際には、この二つをしっかりと区別することが大切です。
4. まとめ
準拠法と適用法の違いを理解することで、法律に対する理解が深まります。法律の世界は複雑ですが、こうした用語を知ることで、日常生活でも役立つ場面が増えるかもしれませんね。
準拠法や適用法の話をすると、法律家になった気分になれますよね
法律って、実はわかりにくいようで案外身近なんです
例えば、学校の規則も一種の準拠法とも言えます
もし学校で何か問題が起きたとき、その規則がどう適用されるのかを考えることができれば、法律の感覚も身につくかも
意外と」を感じたら、法律に興味を持つ良いきっかけになるかもしれません
次の記事: 調達と購買の違いを徹底解説!仕事の世界をスッキリ理解しよう »