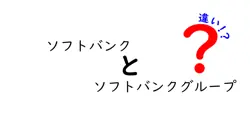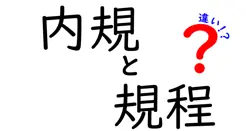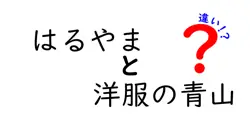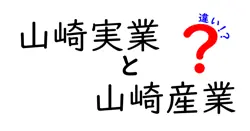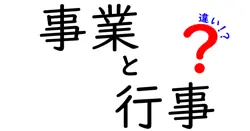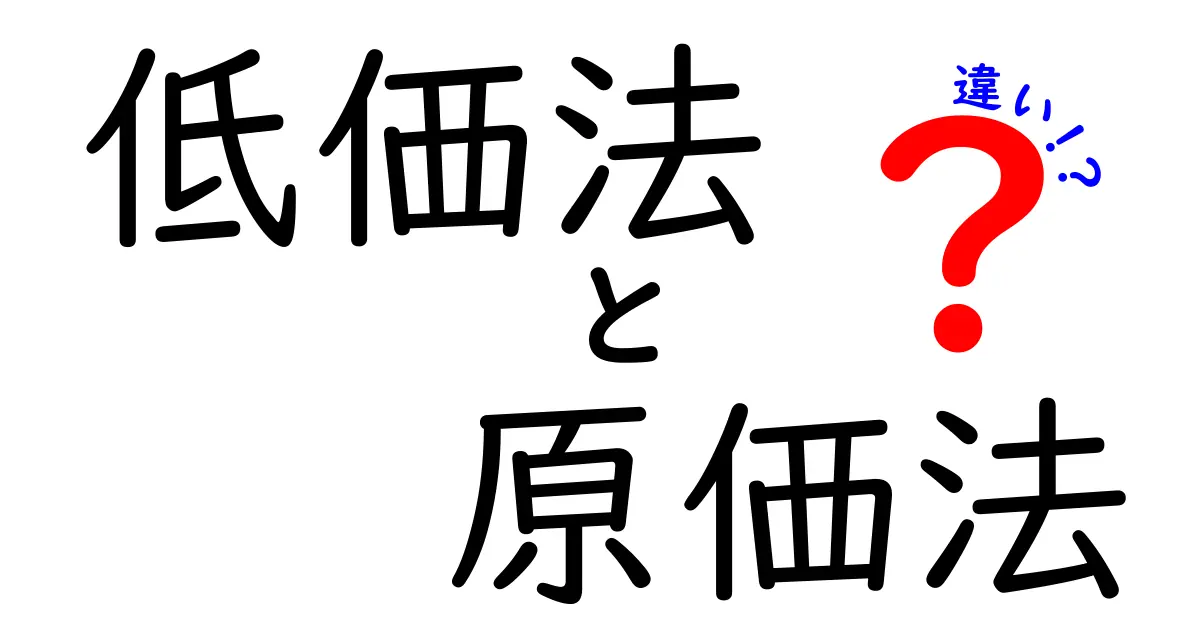
低価法と原価法の違いをわかりやすく解説!どっちが企業にとってメリット?
企業が商品の価格を決める際には、いくつかの方法があります。その中でも、特によく聞くのが「低価法」と「原価法」です。これらの方法は、どちらも商品やサービスの価格設定に関わりますが、その考え方や計算方法には大きな違いがあります。ここでは、低価法と原価法の違いについて、わかりやすく解説いたします。
1. 低価法とは?
低価法は、商品やサービスの価格を決定する際に、競合他社が設定している価格を基準にする方法です。つまり、価格をできるだけ低く設定して、顧客を引きつけることを目指します。この方法は、特に競争が激しい市場でよく使われます。
2. 原価法とは?
原価法は、商品の製造や提供にかかるコストを基に価格を決定する方法です。具体的には、原材料費、労務費、経費など、すべてのコストを計算し、その上に利益を加えた価格を設定します。原価法は、コスト管理が重要視される業界でよく利用されます。
3. 低価法と原価法の比較
| 特徴 | 低価法 | 原価法 |
|---|---|---|
| 価格設定の基準 | 競合他社の価格 | 製造コスト |
| 目指す目的 | 市場シェアの拡大 | 利益確保 |
| 向いている業種 | 競争の激しい業種 | コスト管理が重要な業種 |
4. どちらが企業にとってメリット?
低価法は短期的には顧客を引きつけやすいですが、長期的には利益が減少する可能性があります。一方、原価法は安定した利益が見込める一方で、価格が高くなりがちです。そのため、企業によって使うべき方法は異なります。
5. まとめ
低価法と原価法にはそれぞれ特徴があります。企業は、自社の戦略や市場の状況に応じて、最適な価格設定方法を選ぶことが大切です。価格設定は、企業の売上や利益に直接影響するため、注意深く考える必要があります。
低価法について少し深掘りしてみましょう
低価法は、確かに競争が激しい市場で使われるのですが、時にはイメージを悪化させることもあります
安いから質が悪いと思われたり、企業のブランド価値が下がるといったことがあるんです
それに対して、原価法は安定した利益を見込めますが、価格が高いと顧客が離れるリスクもあるんです
このように、単純に低価法か原価法かを選ぶだけではなく、それぞれのメリット・デメリットを考慮して選ぶのが大切です
次の記事: 使用可能期間と耐用年数の違いをわかりやすく解説! »