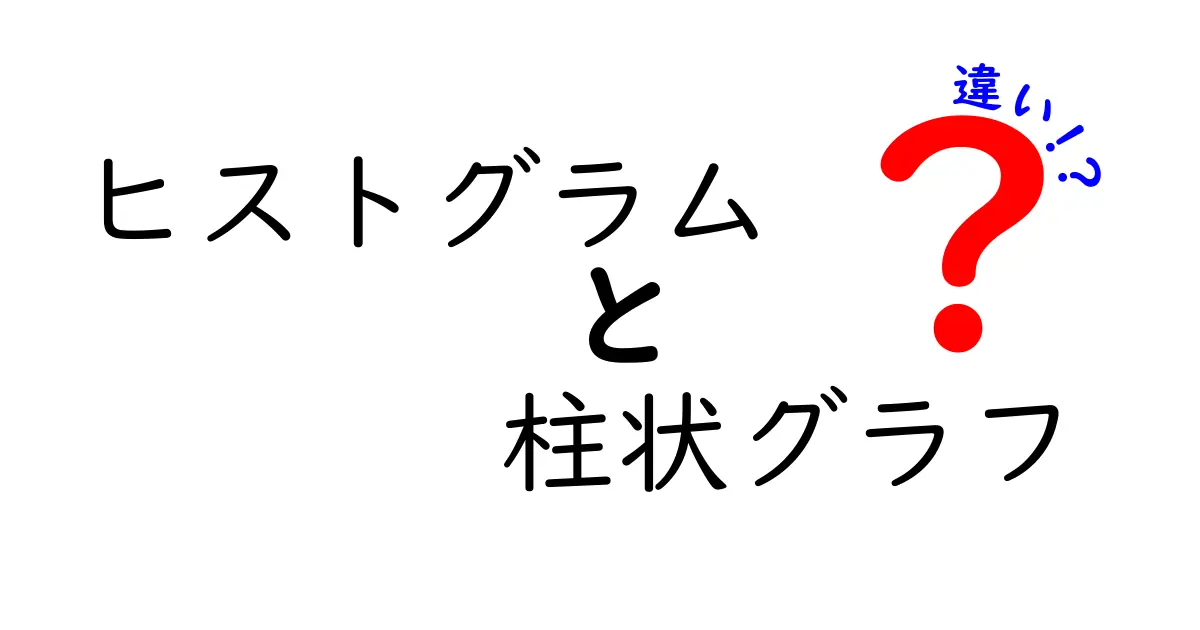
ヒストグラムと柱状グラフの違いを徹底解説!
データを視覚的に理解するために、ヒストグラムと柱状グラフがよく使われますが、実はこの二つには明確な違いがあります。それぞれの特徴や用途を見ていきましょう。
ヒストグラムとは?
ヒストグラムは、連続したデータを範囲ごとにグループ化し、各グループごとのデータの頻度を表示するグラフです。例えば、テストの点数を区切って、その区間にどれだけの生徒がいるのかを示すことができます。横軸にはデータの範囲、縦軸にはその範囲に含まれるデータの数を表します。
柱状グラフとは?
一方で、柱状グラフは異なるカテゴリのデータを比較するために使用されます。例えば、各クラスの生徒数や、各商品の売上を比較するのに適しています。横軸には異なるカテゴリ、縦軸にはそれぞれの数値が示されます。
ヒストグラムと柱状グラフの主な違い
| 特徴 | ヒストグラム | 柱状グラフ |
|---|---|---|
| データの種類 | 連続データ | 離散データ |
| 使用目的 | データの分布を確認 | 異なるカテゴリの比較 |
| バー同士の関係 | 隣接している | 離れている |
| 例 | テストの点数分布 | クラス毎の生徒数 |
まとめ
ここまで、ヒストグラムと柱状グラフの違いについて詳しく説明しました。データを視覚的に表現する際には、どちらのグラフを使うか考えた上で、適切なグラフを選ぶことが大切です。どんなデータを扱うのかを理解し、自分の意図を正しく伝えるために、有効に活用してください。
ヒストグラムの特徴の一つは、データの「分布」を見ることができる点です
例えば、ヒストグラムを使うと、テストの点数がどの範囲に集中しているかが一目でわかります
これによって、どのレベルの生徒が多いか、逆に落ちこぼれの生徒がどの程度いるかもわかります
データを分析する上で、ヒストグラムは非常に役立つツールです
それから、例えば個人の身長や体重のデータを集めてヒストグラムを作成すると、みんなの身長や体重の傾向もパッと見ることができて面白いですよ!
前の記事: « ヒストグラムと度数分布表の違いを簡単に解説!どちらを使うべき?
次の記事: ヒストグラムと確率密度関数の違いをわかりやすく解説! »





















