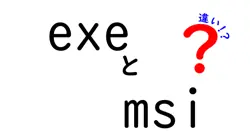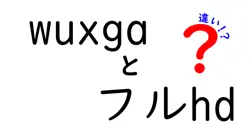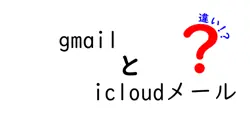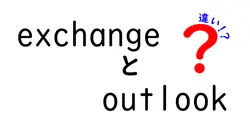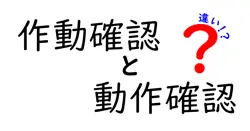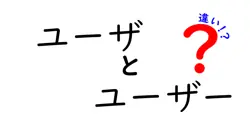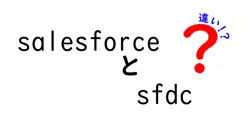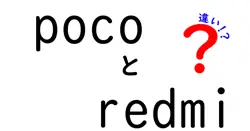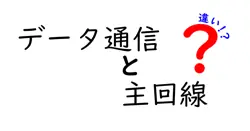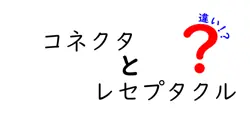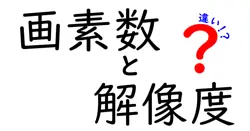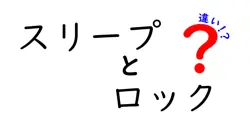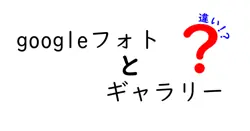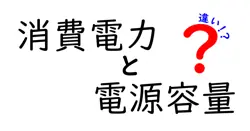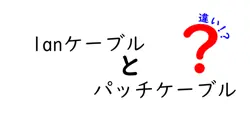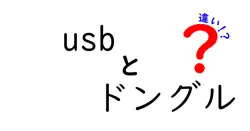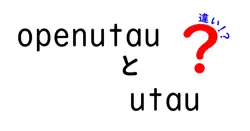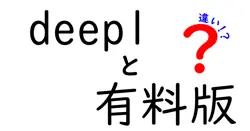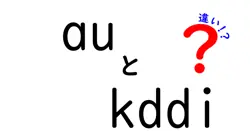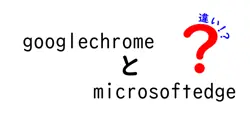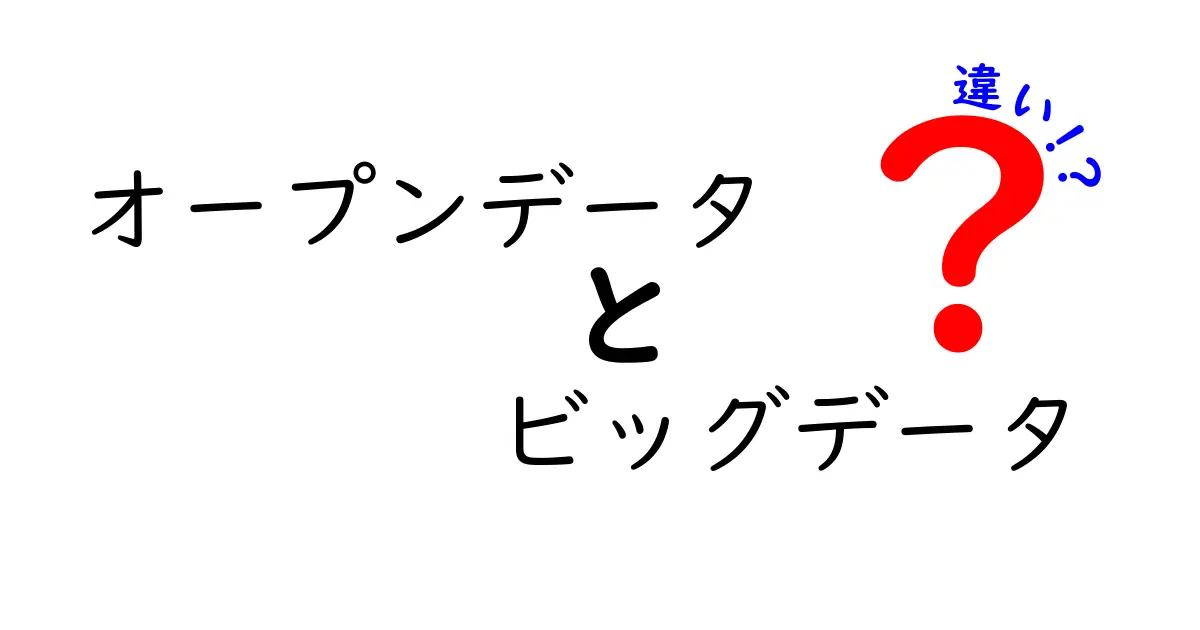
はじめに
最近、オープンデータとビッグデータという言葉をよく耳にしますが、これらは似ているようで実は異なる概念です。ここでは、中学生でもわかるように、オープンデータとビッグデータの違いについて詳しく解説していきます。
オープンデータとは?
オープンデータとは、誰でも自由にアクセスできる形で提供されているデータのことです。これには、政府や企業、研究機関が公開している様々な種類のデータが含まれます。例えば、気象データや交通データなどがオープンデータの一例です。これらのデータは、一般の人々が自分の目的に合わせて利用することができます。
ビッグデータとは?
一方、ビッグデータとは、非常に大規模で複雑なデータのことを指します。ビッグデータは、通常のデータベースでは扱いきれないほどのデータ量であり、分析には高度な技術が必要です。ビッグデータは、SNSの投稿、センサーデータ、取引データなど、様々な形で生成されます。
オープンデータとビッグデータの違い
| 項目 | オープンデータ | ビッグデータ |
|---|---|---|
| 定義 | 自由にアクセスできる公開データ | 非常に大規模で複雑なデータ |
| 利用目的 | 広く一般に共有するため | 分析や予測に利用 |
| データの形式 | CSVやJSONなどのオープンフォーマット | 構造化・非構造化データ |
| 例 | 政府の統計情報 | SNSのユーザー行動データ |
まとめ
オープンデータは、誰でも利用できる公開データであり、ビッグデータは多様な情報を持つ大規模データです。どちらも重要なデータの形ですが、それぞれの特徴と利用方法を理解することで、より効果的に活用できます。
オープンデータと聞くと、政府が提供している情報を思い浮かべるかもしれません
実は、オープンデータは単なる情報の公開にとどまらず、例えば地域のイベント情報や交通機関の運行状況など、さまざまな分野で利用されています
こうしたデータをうまく組み合わせれば、新たなサービスが生まれることも珍しくありません
面白いのは、オープンデータを利用することで地域の活性化に繋がる事例も増えてきている点です!あたなの住んでいる地域もオープンデータをうまく活用してみたら、もっと便利になるかもしれませんね
前の記事: « iniとマッチアップの違いとは?ゲームの戦略と運の要素を解明する