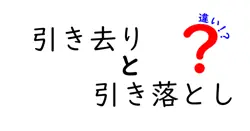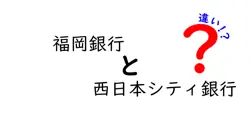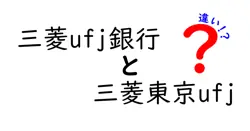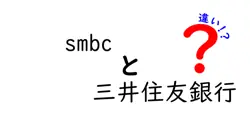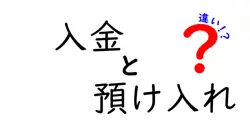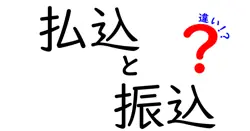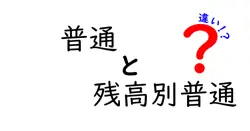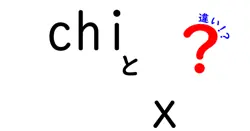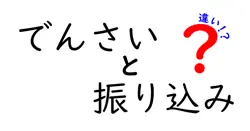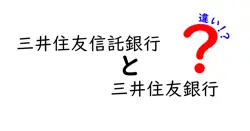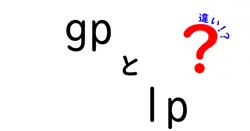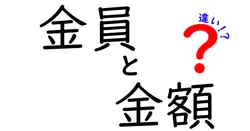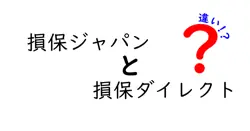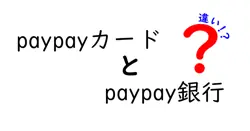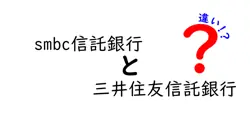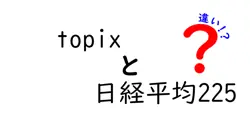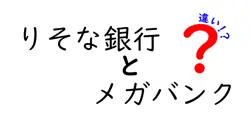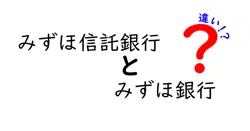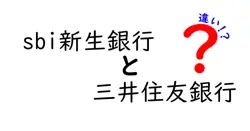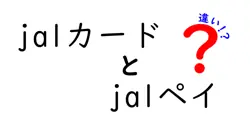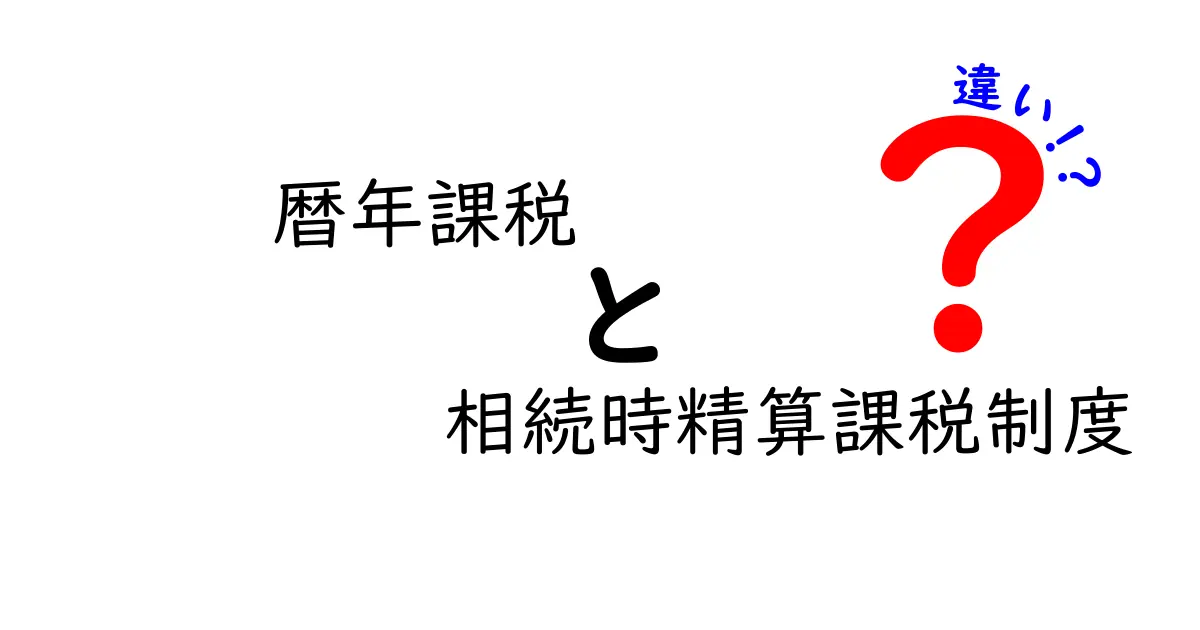
暦年課税と相続時精算課税制度の違いをわかりやすく解説!
税金について考えるとき、特に相続に関連するものは難しく感じることがありますよね。その中でも、暦年課税と相続時精算課税制度について理解することはとても大切です。ここでは、この2つの課税制度の違いについて詳しく説明します。
まず、暦年課税とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間にわたり、贈与を受けた金額に基づいて課税される制度です。日本では、毎年110万円までの贈与は非課税とされています。これを超える金額を贈与された場合、その超えた部分に対して贈与税がかかります。
一方、相続時精算課税制度は、相続時に相続財産の全体を一度に課税する方式です。この制度を選択すると、生前に財産を贈与した場合も、相続財産としてその贈与額を合算して税金が計算されます。つまり、相続時に「精算」されるということです。
暦年課税と相続時精算課税制度の比較
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税制度 |
|---|---|---|
| 適用期間 | 毎年1月1日から12月31日 | 相続発生時 |
| 非課税枠 | 110万円 | 2,500万円 |
| 課税方式 | 贈与ごとに課税 | 相続時に精算 |
| 受け取れる額 | 毎年贈与可能 | 一度に大きな額 |
このように、暦年課税と相続時精算課税制度にはそれぞれの特徴があります。どちらの制度を選ぶかは、受け取り手の状況や贈与する側の方針によって異なりますので、よく考えることが大切です。
さらに、相続時精算課税制度は特に高額な贈与に対して有利です。つまり、大きな資産を持っている場合、相続税を計算する際に生前贈与が影響してくるのです。したがって、将来の相続に備えて慎重に選択しましょう。
税金の計算や制度の選択は複雑ですが、しっかりと理解を深めて、無駄のない贈与や相続を考えていきましょう。
相続時精算課税制度の面白いところは、ある意味で大きな贈与を受けやすくする制度であるという点です
特に、贈与者が故人になることが多い相続の場面では、残された家族が生前にどれだけ贈与を受けていたかが重要になります
これにより、贈与者から受け取ったものの総額が、後の相続財産にどのように影響するかをしっかり考えなければならないのです
こうした制度を理解することで、将来の金銭的な負担を軽減することができるかもしれませんね
前の記事: « 暦年課税と相続時精算課税の違いをわかりやすく解説!
次の記事: 収入証明書と給与明細の違いをわかりやすく解説! »