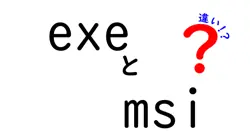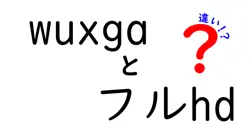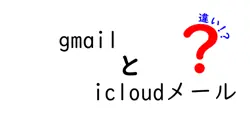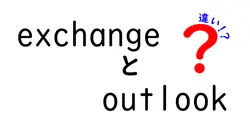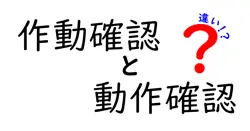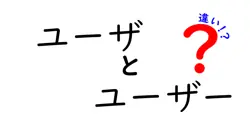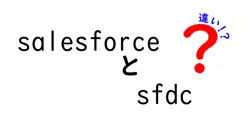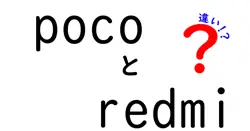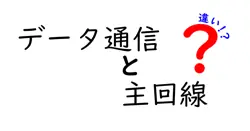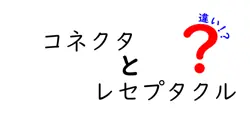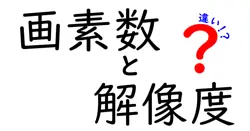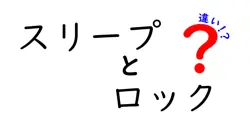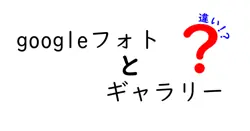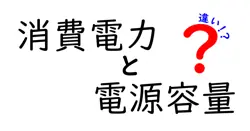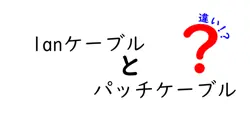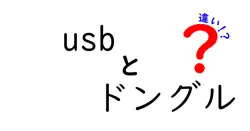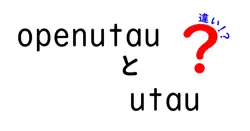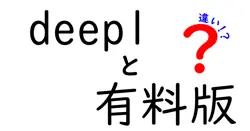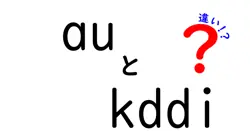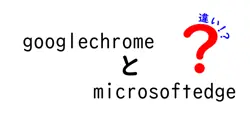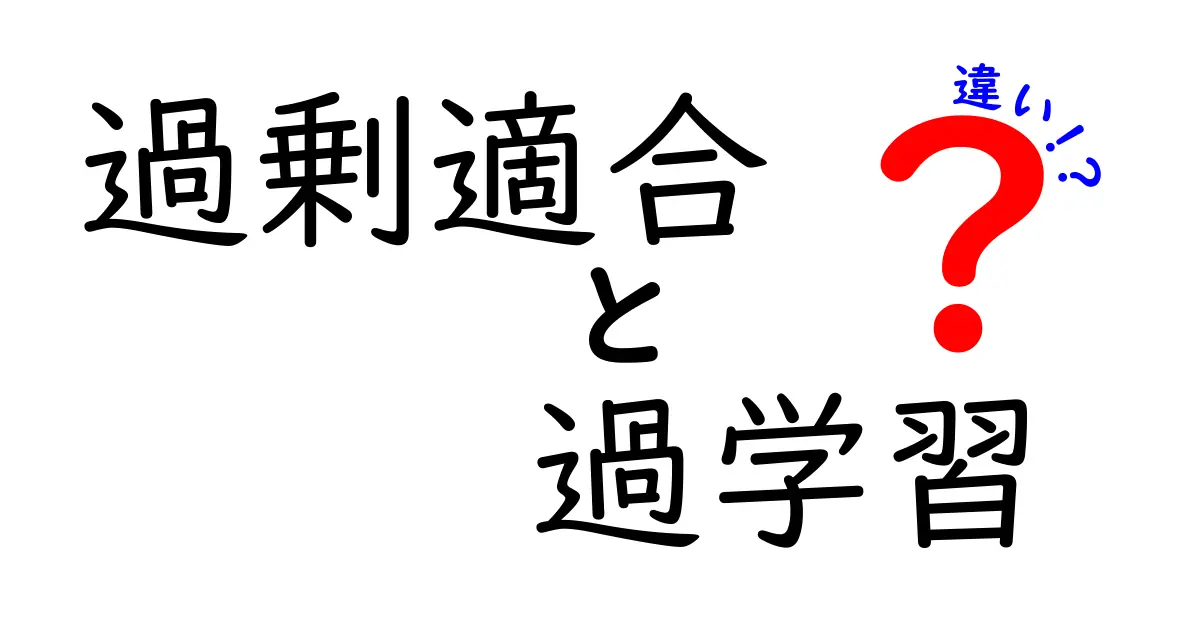
過剰適合と過学習の違いをわかりやすく解説!
データ分析や機械学習の分野でよく耳にする「過剰適合」や「過学習」という言葉は、初心者には少し難しいかもしれません。しかし、これらは非常に重要な概念であり、特にモデルを作成するときに注意が必要です。この記事では、過剰適合と過学習の違いについて、具体的な例を交えながら説明していきます。
過剰適合とは?
過剰適合(かじょうてきごう)は、モデルが訓練データに非常に適合しすぎてしまい、一般化能力が失われる現象です。つまり、モデルが学習したデータには高い精度を持つ一方で、新しいデータに対しては悪いパフォーマンスを示すことになります。
例
例えば、学生がテストのために暗記をしたとして、同じ問題が出ると完璧に解けるものの、応用問題や異なる問題には全然答えられないといった状態です。これが過剰適合です。
過学習とは?
過学習(かがくしゅう)は、モデルがデータに対して必要以上に学習をしてしまうことを指します。これも過剰適合と似ていますが、少し異なる点があります。過学習は、モデルがノイズや例外的なデータパターンを学習してしまい、これが影響して新しいデータに対する予測精度が低下することを意味します。
例
例えば、天気予報が特定の日の湿度の変化に過度に依存してしまうと、その日が特別な条件であったため、次の日の予測が全く外れてしまうことがあります。これが過学習です。
過剰適合と過学習の違い
| 特徴 | 過剰適合 | 過学習 |
|---|---|---|
| 定義 | 訓練データに対する適合が過剰になる現象 | ノイズや異常値を学習してしまう現象 |
| 影響 | 一般化能力が低下する | 新しいデータへの予測精度が低下する |
| 例え | テスト問題を完璧に暗記するが、別の問題に不適応 | 特定の湿度データに過剰依存する天気予報 |
まとめ
過剰適合と過学習は、機械学習やデータ分析において注意すべき重要な概念です。特に、これらに注意していないと、モデルは新しいデータに対して適切に機能しなくなってしまいます。これらの違いを理解することで、高品質なモデル作成が可能となります。
過学習についてちょっと気になったことがあるんだけど、よく考えてみると、私たちの日常生活にも似たようなことがあるよね
例えば、友達とのコミュニケーションで、ちょっとした言い回しや流行語を使いすぎると、「あ、この子はそれしか言えない」と思われて、他のことが通じなくなっちゃう
これって、まさに過学習と同じかも
だから、いろんな言葉や状況に対応できるように気をつける必要があるよね!
前の記事: « 独立性と適合度の違いを分かりやすく解説
次の記事: ホールドアウトと交差検証の違いをわかりやすく解説! »