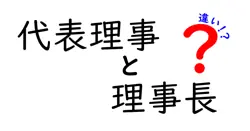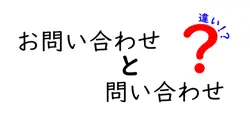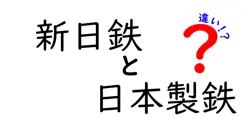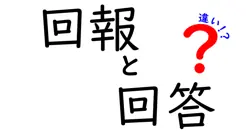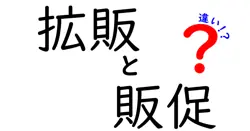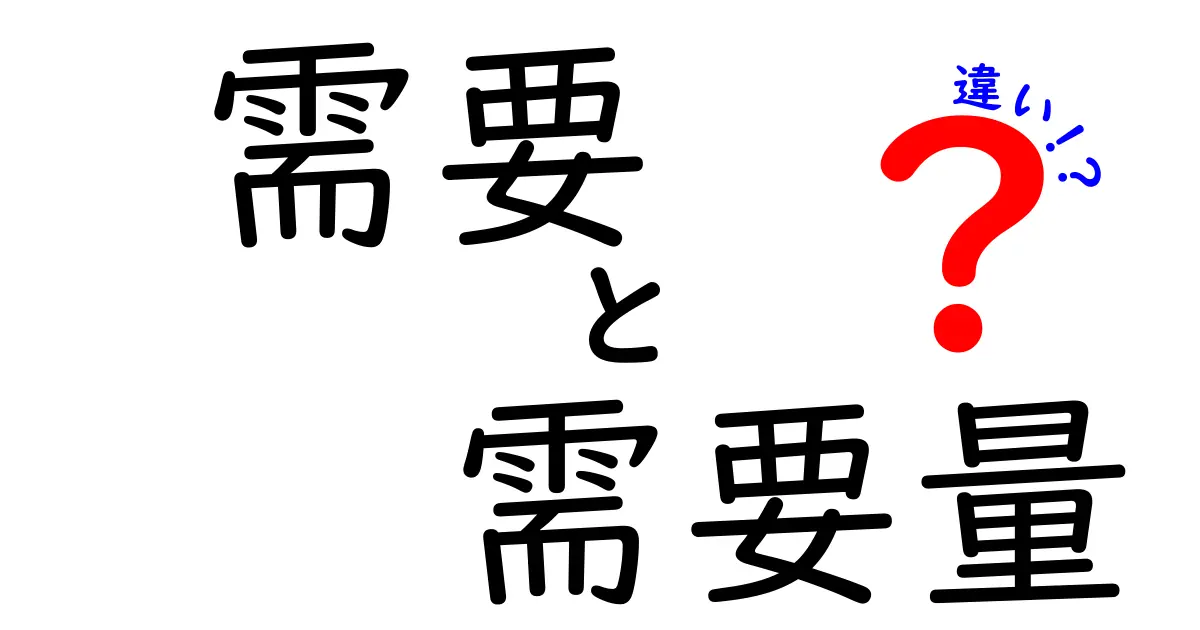
需要と需要量の違いとは?わかりやすく解説します!
みなさんは「需要」と「需要量」という言葉を聞いたことがありますか?これらは経済の基本的な概念ですが、実は意味が全く異なります。今日はこの二つの言葉の違いについて、中学生でもわかりやすく解説していきます。
需要とは?
まず「需要」とは、ある商品やサービスに対して、消費者が購入したいと思う気持ちのことを指します。需要は、商品がどれだけ欲しいかという「意欲」や「必要性」を示すもので、価格が上がると通常は需要が減ります。逆に価格が下がると需要は増える。これを需要の法則と言います。
需要量とは?
次に「需要量」ですが、これは特定の価格の下で消費者が実際に購入したいと思う商品の数量を指します。需要量は、一定の価格に対してどれだけの量が求められるのかを示すもので、需要曲線上では価格と数量の関係が表現されます。
需要と需要量の違い
| 項目 | 需要 | 需要量 |
|---|---|---|
| 定義 | 購入したいという気持ち | 特定の価格における購入数量 |
| 影響要因 | 価格、好み、収入など | 価格の変化 |
| 例 | みんながアイスクリームを食べたいと思うこと | 価格が100円の時に、みんなが10個食べたいと思っていること |
まとめ
いかがでしたか?「需要」と「需要量」は似ているようで、実は異なる概念です。需要は「欲しい」という気持ち、需要量は特定の価格における「購入の数量」です。理解が深まることで、経済をもっと楽しむことができるでしょう!
ピックアップ解説
「需要」という言葉を聞いたとき、何を思い浮かべますか?たくさんの人が同じものを欲しがる状況を想像するかもしれません
面白いのは、需要は人々の気持ちに影響されるため、同じ商品でも季節や流行によって大きく変わることです
例えば、冬になるとコートの需要が増え、夏になるとアイスクリームの需要が上がります
人々の気持ちや環境を考えると、需要はまるで生き物のように変わるんですよ!
前の記事: « 自動車車庫と駐車場の違いを徹底解説!あなたはどちらが必要?
次の記事: 3sとMeta Quest 3の違いを徹底解説!VR体験の新時代 »