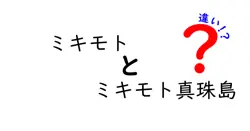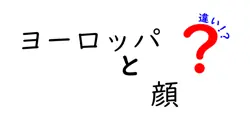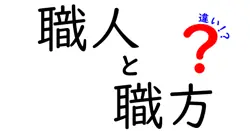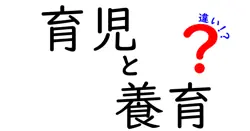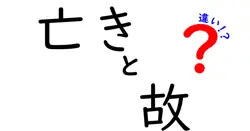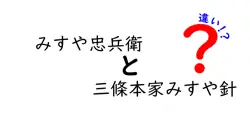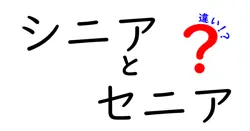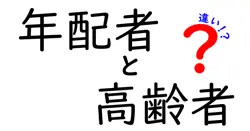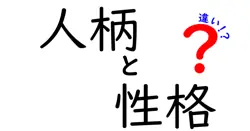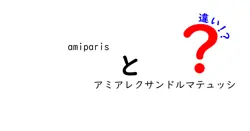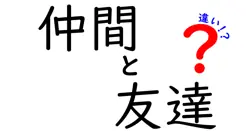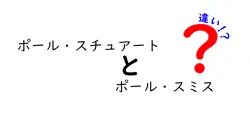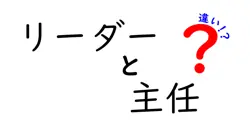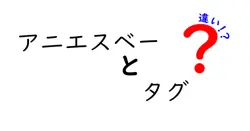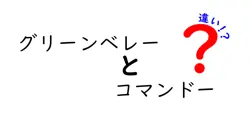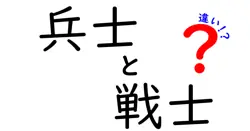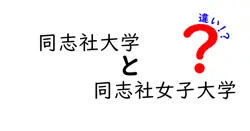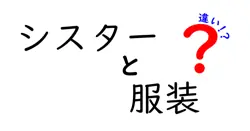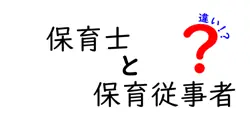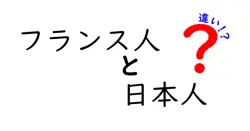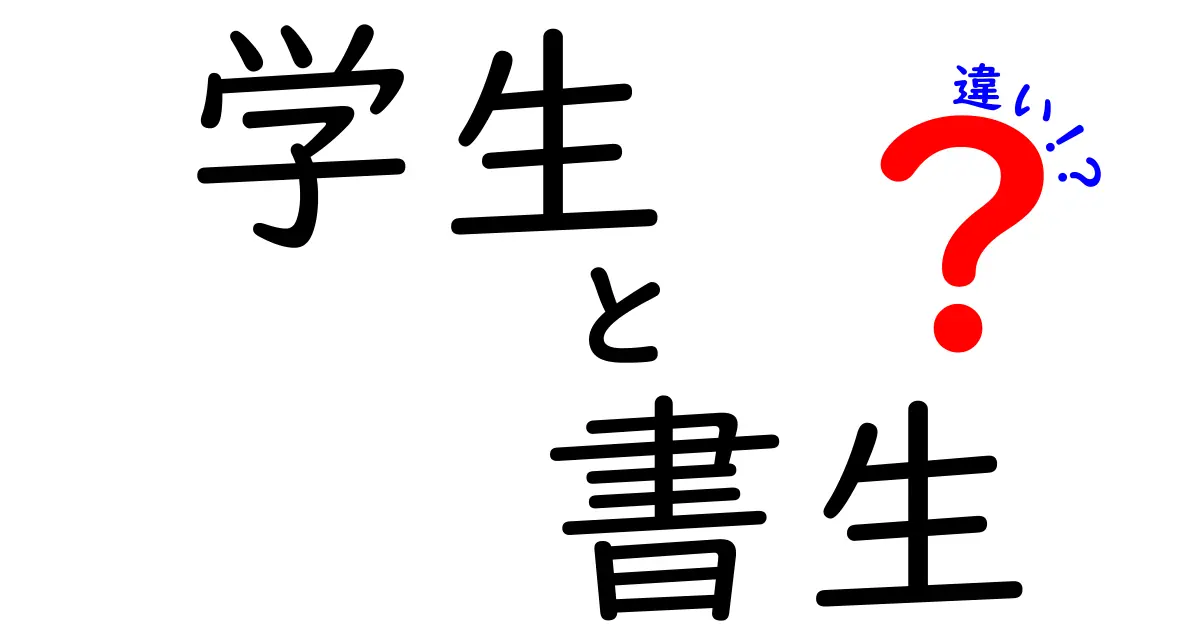
「学生」と「書生」の違いとは?教育の形態と文化背景を探る
私たちが普段何気なく使っている「学生」という言葉。しかし、「書生」という言葉はあまり耳にすることがないかもしれません。この二つの言葉の違いについて理解を深めていきましょう。
学生とは
一般に「学生」というのは、学校や大学に正式に入学し、学問を学ぶ人を指します。義務教育を受け終えた後、高等学校や大学などの教育機関に通っている人々が含まれます。日本では、幼稚園から始まり、義務教育を経て高校、大学、さらには大学院という形で教育を受け続けるのが一般的です。
書生とは
一方で「書生」という言葉は、日本の伝統的な教育制度の一環として使われていました。もともとは、武士のもとで学ぶ人物を指していましたが、明治時代以降、官吏や教師を目指す人々が、正式な教育機関に通うことなく学問をする際に用いられることが多くなりました。ただし、書生は特定の教育機関に在籍していない場合がほとんどで、そのため自由な形で学問を追求することができました。
学生と書生の主な違い
| 項目 | 学生 | 書生 |
|---|---|---|
| 定義 | 学校や大学に在籍し、学問を学ぶ人 | 特定の教育機関に依存せず学問を探求する人 |
| 教育形態 | 正式なカリキュラムと教員がいる | 自由な学習スタイル |
| 歴史的背景 | 近代の教育制度 | 伝統的な教育制度に起源 |
| 目的 | 資格取得や就職活動 | 自己成長や知識探求 |
まとめ
このように、「学生」と「書生」という言葉は、教育の形態や目的、歴史的背景において大きな違いがあります。最近では、学生が外部の教育機関やオンラインでの学びを取り入れるなど、教育の形態は多様化しています。それでも、学生は依然として学校や大学という枠組みの中での学びを重視される一方、書生はより自由な形で知識を追求する姿勢が求められています。
「書生」という言葉、実は昔の日本では非常に重要な役割を果たしていました
特に江戸時代や明治時代の日本では、武士の家に住み込みで学んでいた若者たちが「書生」と呼ばれていました
そして、彼らは学問を学びながら、同時に家の仕事も手伝っていたのです
そのため、書生はただの学生とは異なり、生活全般にわたって様々な経験を積むことができました
今でこそ学生は学校に通うのが一般ですが、昔は生活を共有しながら学ぶスタイルが主流だったのです
前の記事: « 内容と項目の違いをわかりやすく解説!