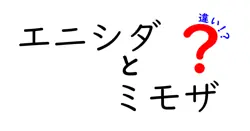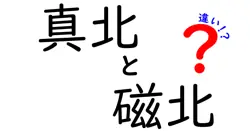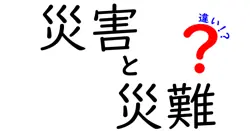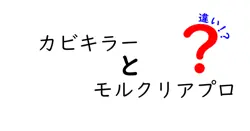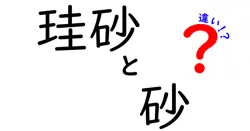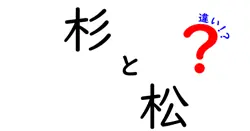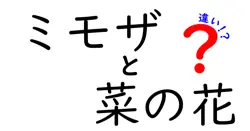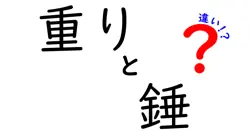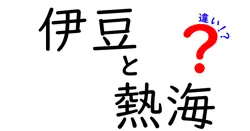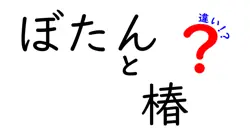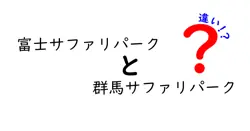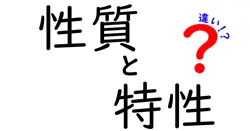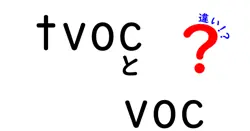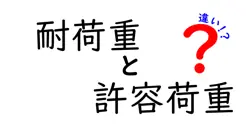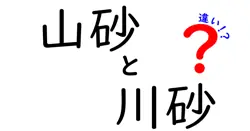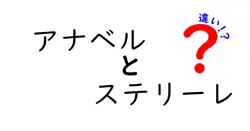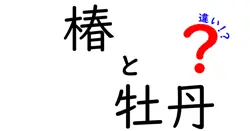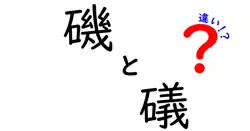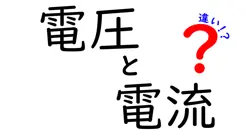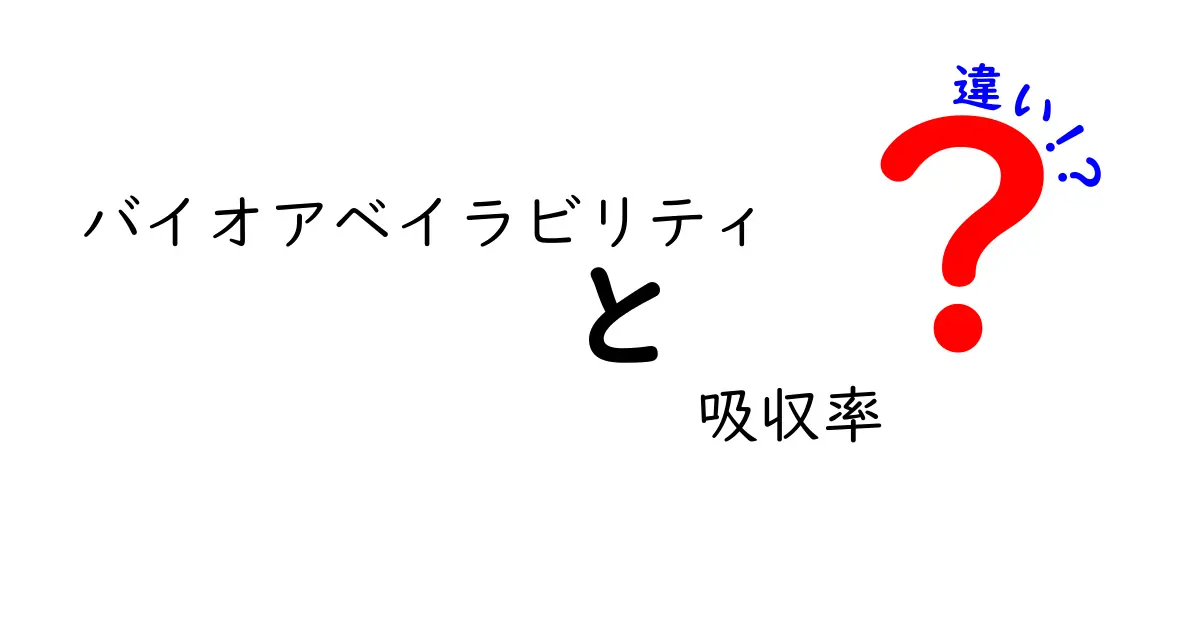
バイオアベイラビリティと吸収率の違いを徹底解説!
皆さん、こんにちは!今日は「バイオアベイラビリティ」と「吸収率」という言葉についてお話しします。これらは主に健康や栄養に関する分野でよく使われる言葉ですが、実は意味が少し違います。仲間のようにも見えますが、しっかりとした違いがあるんですよ。
バイオアベイラビリティとは?
まず、「バイオアベイラビリティ」について説明します。この言葉は、体内で実際に利用できる栄養素の量を指します。たとえば、ある食べ物からどれくらいの栄養分が身体に吸収され、エネルギーや他の活動に使われるかということです。バイオアベイラビリティが高いということは、食べたものが体にとって役立つ割合が高いということですね。
吸収率とは?
次に「吸収率」についてお話ししましょう。吸収率は、食べ物から栄養素がどれだけ体に吸収されるかの割合を表します。具体的には、胃や腸を通った後、血液に入った栄養素の量を基に計算されます。このため、吸収率は食品によって異なりますし、調理方法や食べ合わせによっても変化することがあります。
バイオアベイラビリティと吸収率の違い
では、バイオアベイラビリティと吸収率の違いを整理してみましょう。以下の表をご覧ください。
| 項目 | バイオアベイラビリティ | 吸収率 |
|---|---|---|
| 定義 | 利用可能な栄養素の量 | 実際に吸収された栄養素の量の割合 |
| 測定方法 | 食品中の栄養素がどのくらい使われるかを見る | 食べ物からどれだけの栄養が血中に入るかを見る |
| 影響要因 | 消化器官の健康、加工方法 | 調理法、食べ合わせ、個人の状態 |
このように、バイオアベイラビリティは「栄養素の利用効率」、吸収率は「吸収の割合」といった違いがあります。両方とも、食べ物から得られる栄養に影響を及ぼす大切な要素です。
まとめ
今回の話で、バイオアベイラビリティと吸収率について少しでも理解が深まったでしょうか?食べ物の効果的な摂取方法を考える上で、これらの知識はとても役立ちますので、ぜひ覚えておいてください!
バイオアベイラビリティって、なんだか難しそうに聞こえますが、実は身近な例がたくさんあります
例えば、野菜と果物を同時に食べると、栄養の吸収が良くなることがあるんです
これは、ビタミンやミネラルが協力して働くから
だから、食事のバランスを考えると、より多くの栄養を体に取り入れやすくなるんですよ
それに、自分に合った食べ方を見つけるのも楽しいですよね!
前の記事: « ツヤと透明感の違いとは?美しさの秘密を探る
次の記事: 乳製品と乳酸菌の違いを徹底解説!それぞれの役割と健康への影響 »