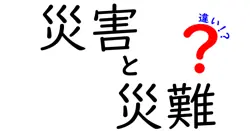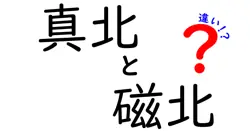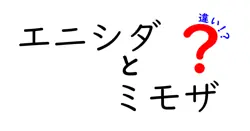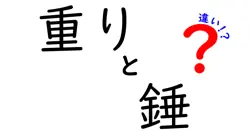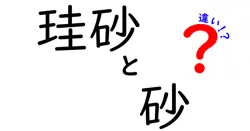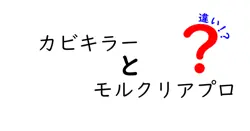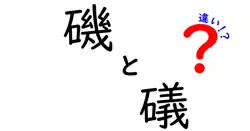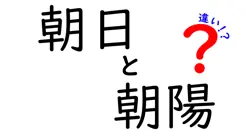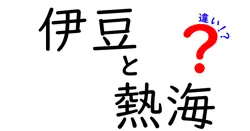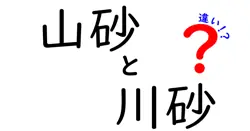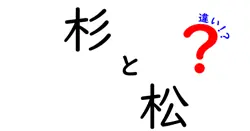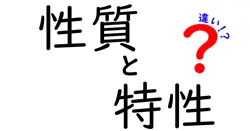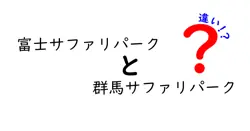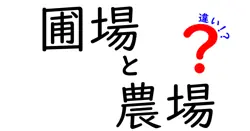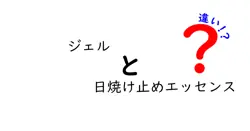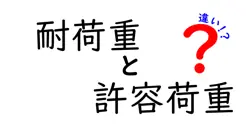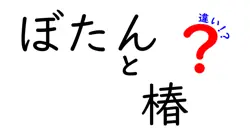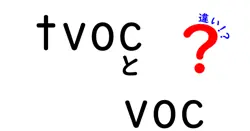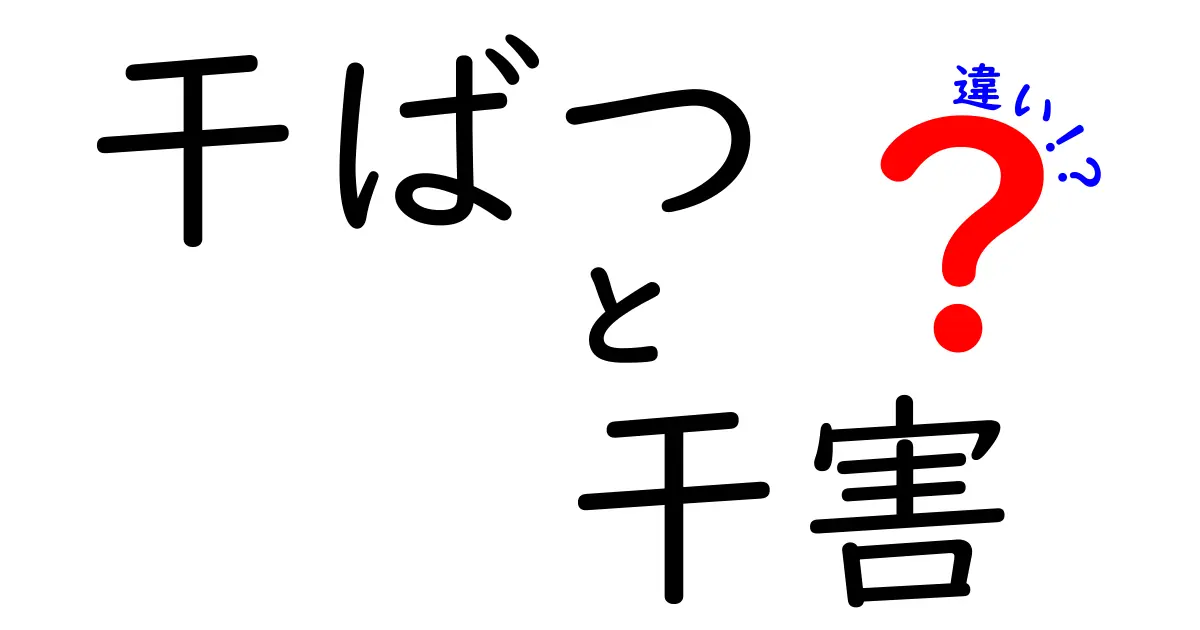
干ばつと干害の違いとは?
私たちの生活に密接に関わる自然現象である「干ばつ」と「干害」。どちらも水不足に関連している言葉ですが、それぞれの意味は異なります。今回は、この二つの違いについて、詳しく解説していきます。
干ばつとは?
まず、「干ばつ(かんばつ)」について考えてみましょう。干ばつとは、ある地域において長期間にわたって降雨が少なく、水源が枯渇してしまう現象を指します。気候変動や自然災害が原因で、特定の地域に雨が降らない状態が続くと、農作物や水供給に大きな影響を与えることになります。
干害とは?
次に、「干害(かんがい)」について見ていきましょう。干害は、干ばつによって起こる農作物や生態系への悪影響のことを指します。乾燥が続くことにより、農作物が枯れてしまったり、生態系が崩れたりすることで、食料の不足や生物の絶滅危惧が生じるのです。
| キーワード | 定義 | 影響 |
|---|---|---|
| 干ばつ | 長期間の降雨不足 | 水源枯渇、農業への影響 |
| 干害 | 干ばつによる農作物への被害 | 作物の枯渇、食糧不足 |
まとめ
要するに、干ばつは降雨が極端に少なくなること自体を指し、その結果として干害が発生します。両者は密接に関わっていますが、意味は異なるのです。私たちの生活において、これらの現象を理解することは重要です。特に、農業においては、持続可能な水管理が求められています。
ピックアップ解説
干ばつが続くと、農業だけでなく、私たちの生活にも影響が出ることがあるって知っていましたか?たとえば、家庭で使う水の量も制限されることがあるんです
逆に、雨が多すぎると洪水が起き、土壌が流されることもあります
このように、気候が安定しないと、私たちが普段何気なく使っている水の大切さを再認識させられますね
前の記事: « 「人員」と「人数」の違いを徹底解説!その意味と使い方は?
次の記事: 干ばつと日照りの違いを徹底解説!知っておきたい自然の現象 »