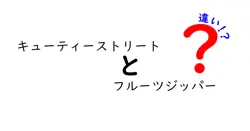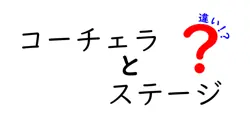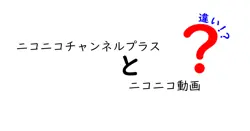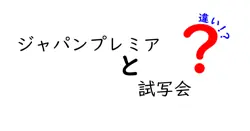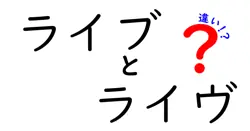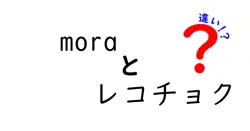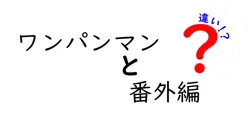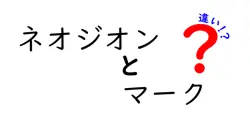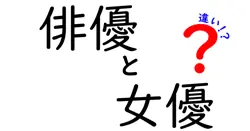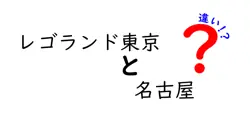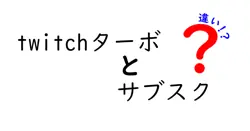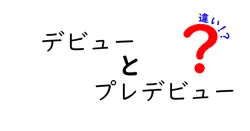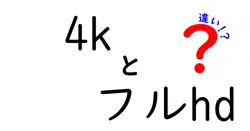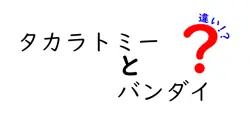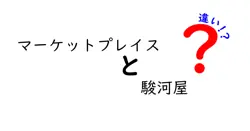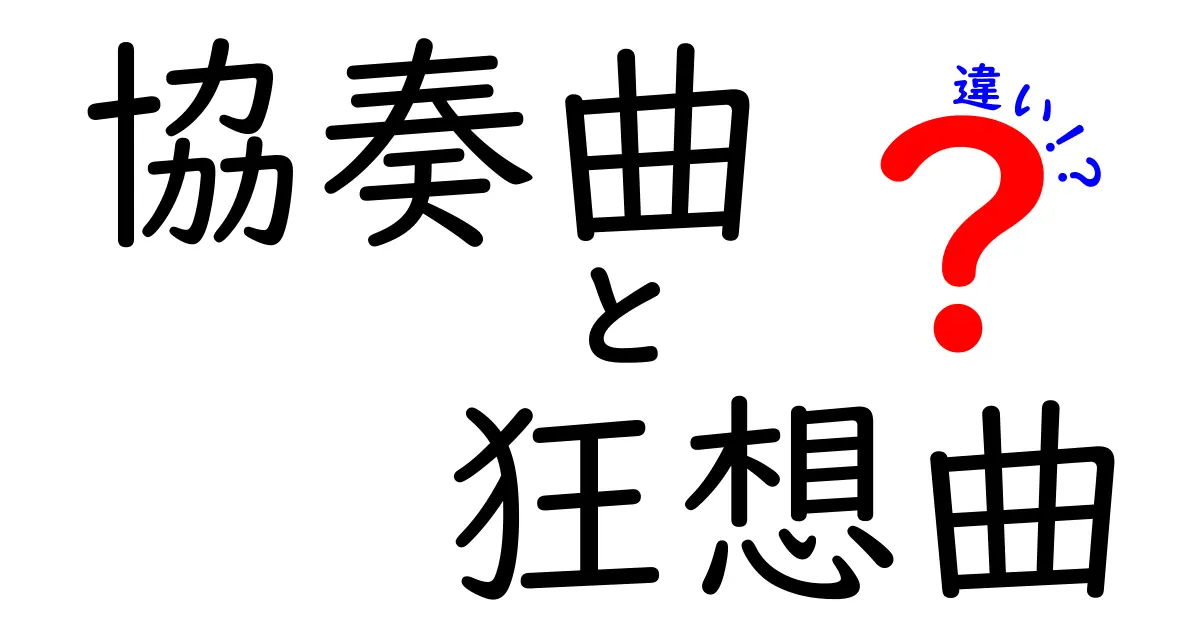
協奏曲と狂想曲の違いとは?音楽の世界を探る
音楽の世界には多くの楽曲の形式がありますが、特に「協奏曲」と「狂想曲」という用語を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。では、これら二つの言葉は一体何が違うのでしょうか?今回はこの二つの違いについて、中学生でもわかりやすく解説していきます。
協奏曲とは何か?
まず、協奏曲について見ていきましょう。協奏曲は、一般的に一つの楽器がオーケストラをバックにして演奏する形式の楽曲です。特に、ピアノ協奏曲やバイオリン協奏曲など、特定の楽器が主役となることが多いです。協奏曲は、3つの楽章(曲の部門)から構成されることが一般的で、テンポや感情の変化が豊かに表現されます。
狂想曲とは何か?
次に、狂想曲について説明します。狂想曲は、特定の形式にとらわれず、自由な発想で作られた楽曲です。個々の楽器のソロパートが強調されることもありますが、オーケストラ全体のハーモニーが重視されることもあります。狂想曲は、複数の音楽のスタイルを組み合わせたり、テーマを自由に変化させたりするため、非常に表現が豊かです。
協奏曲と狂想曲の違い
| 特性 | 協奏曲 | 狂想曲 |
|---|---|---|
| 構造 | 3つの楽章に分かれていることが多い | 構造は自由、決まった形式がない |
| 楽器の役割 | 特定の楽器が主役 | 楽器のソロやハーモニーを問わない |
| 表現の幅 | テーマに沿った豊かな表現 | 自由な発想による多様な表現 |
まとめ
このように、協奏曲と狂想曲はそれぞれ異なる特性を持っています。協奏曲は特定の楽器が主役となり、決まった形式を持ち合わせています。一方、狂想曲は自由な発想で作られ、形式にとらわれず様々なスタイルを楽しめます。それぞれの楽曲形式の違いを理解することで、音楽をもっと楽しめるでしょう。
協奏曲は通常、ソロ楽器とオーケストラの対話が主なテーマです
例えば、ピアノ協奏曲ではピアノがメインで、オーケストラがそのバックアップをします
しかし、なぜこのような形式が生まれたのでしょうか?それは、ソロの魅力を引き立てるため、演奏者がオーケストラの力を借りることで、より深い音楽体験を生むためです
音楽の歴史の中で、数多くの素晴らしい協奏曲が書かれていますが、これらはすべて異なる楽器や時代背景に応じて独自の色を持っているのです
前の記事: « ドイツ人とフランス人の違いを徹底解説!文化や習慣を比べてみよう