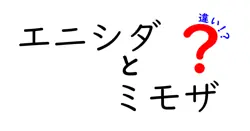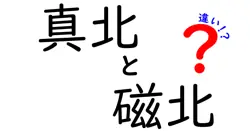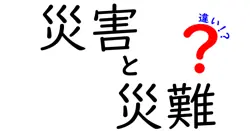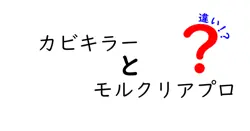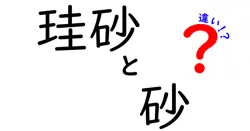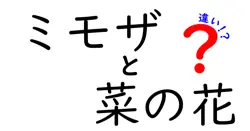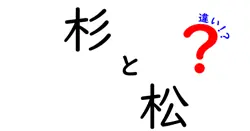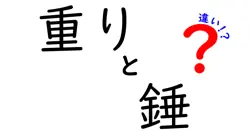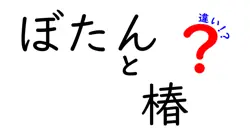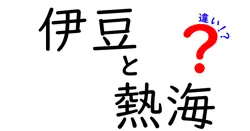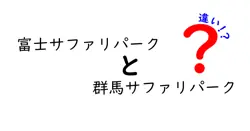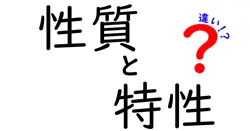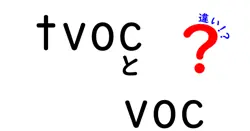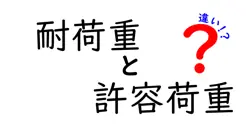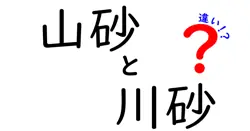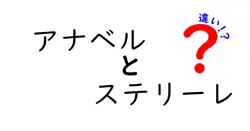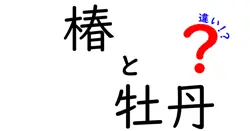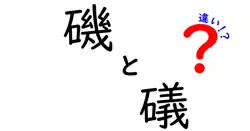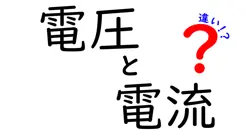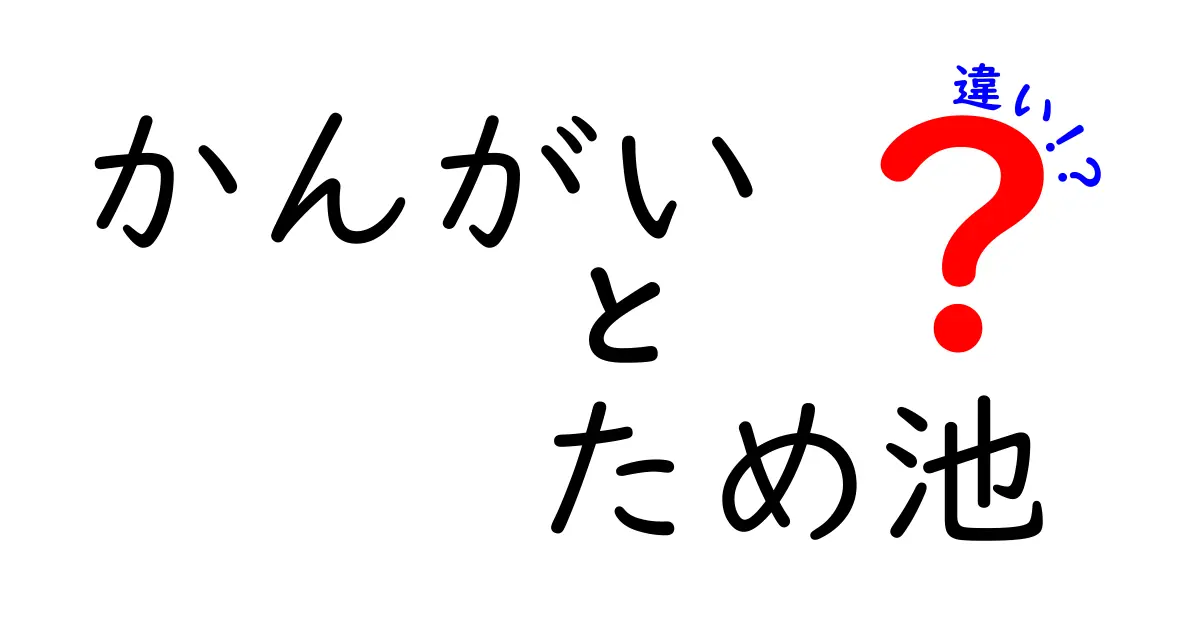
かんがいとは?ため池との違いをわかりやすく解説!
「かんがい」と「ため池」という言葉を最近耳にすることが増えました。これらは農業や水資源管理に関わる重要な要素ですが、それぞれが持つ意味や役割は異なります。この記事では、それぞれの違いを詳しく解説していきます。
かんがいとは
かんがいは、農作物を育てるために水を適切に供給することを指します。日本の農業は、雨水だけでは不十分な場合が多いため、意図的に水を管理する技術が必要です。これには、井戸や水路、ため池などの水源を利用して、均等に水を農地に行き渡らせる方法が含まれます。
ため池とは
ため池は、その名の通り、水をためるために作られた池のことです。これは自然の地形を利用して作られる場合もあれば、人工的に作られることもあります。ため池は主に、降雨によって集まった水を保持する役割を果たします。また、灌漑用水の貯水だけでなく、地域の生態系を支えたり、レクリエーションの場としても利用されています。
かんがいとため池の違い
| 項目 | かんがい | ため池 |
|---|---|---|
| 定義 | 農作物に水を供給すること | 水をためる池 |
| 目的 | 農業の生産性を上げる | 水資源の管理、保全 |
| 構造 | 特定の水源から水を配分 | 自然または人工で作られた水の貯蔵場 |
このように、かんがいとため池は密接に関係していますが、それぞれ独自の役割を持っていることがわかります。農業の生産には、かんがいが欠かせないものであり、そのための水をためる場所としてため池が存在しています。
まとめ
これからの農業を支えるためには、かんがい技術とため池の適切な管理が重要です。地域の特性を活かしつつ、持続可能な農業を目指していきましょう。
ため池について少し雑談をしましょう
皆さん、ため池はただ水をためる場所だと思っていませんか?実は、ため池は地域の生態系にも大きく影響を与えるんです
ため池には、さまざまな生物が住んで、例えばカエルや昆虫などが共生しています
そのため、ただの水の貯蔵場所ではなく、地域の生物多様性が保たれる重要な存在といえるでしょう
これからは、その役割についても考えながら、ため池の大切さを認識していきたいものですね
前の記事: « 記録簿と議事録の違いを徹底解説!どちらが何のために使われるのか?
次の記事: 「そのほか」と「その他」の違いを徹底解説!何が違うの? »