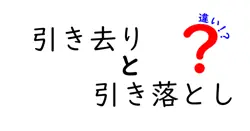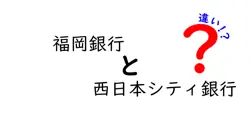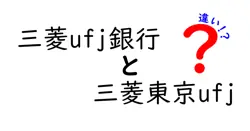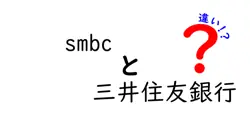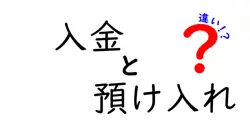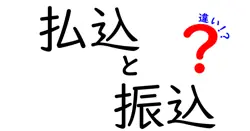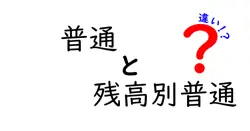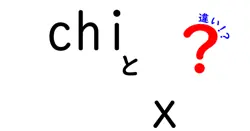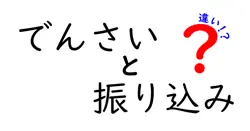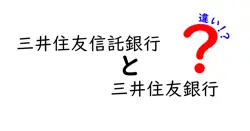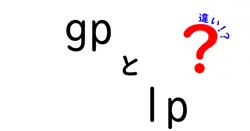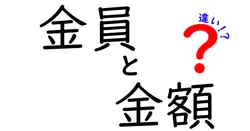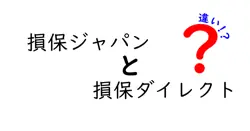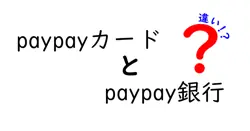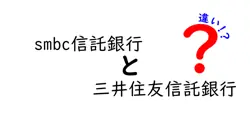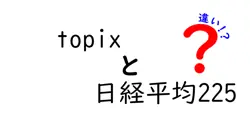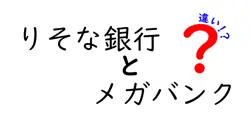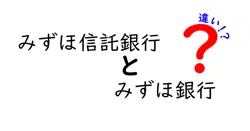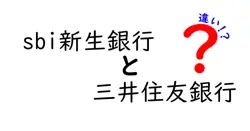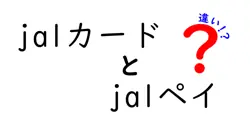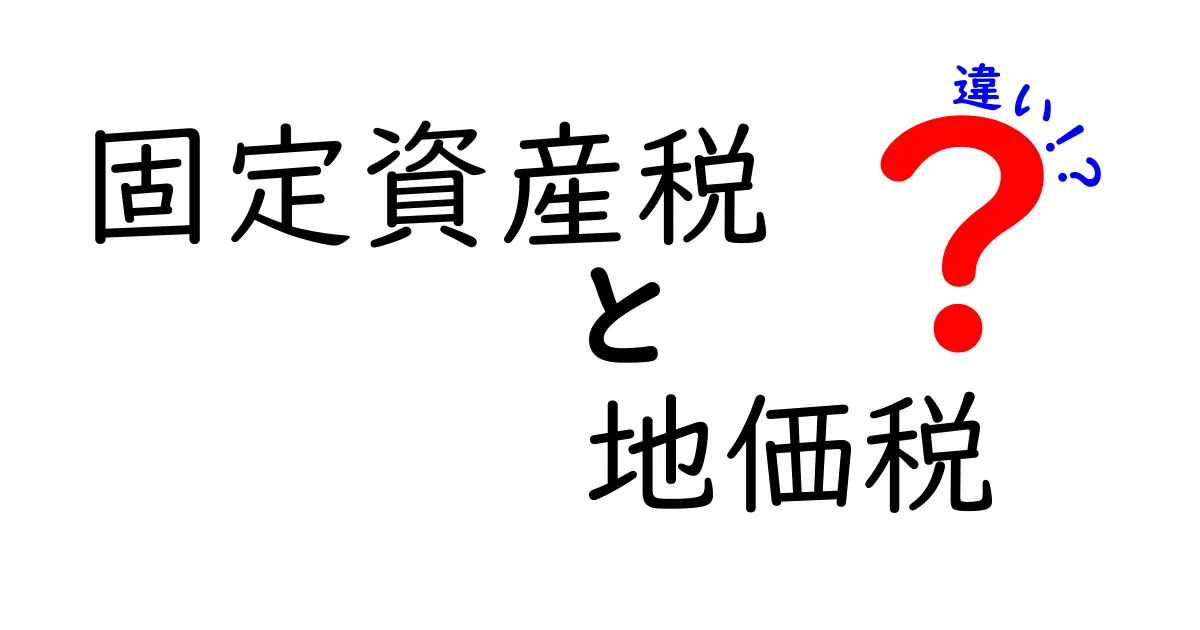
固定資産税と地価税の違いをわかりやすく解説
私たちが住んでいる地域では、さまざまな税金が存在しますが、特に「固定資産税」と「地価税」は重要な役割を果たしています。これらの税金の違いを理解することで、自分たちの資産やお金の使い方をより良く計画することができるでしょう。では、具体的にどのような違いがあるのでしょうか?
固定資産税とは?
固定資産税は、土地や建物などの固定資産にかかる税金です。これは毎年課税され、地域の自治体がその収入を利用して公共サービス(例えば、道路の維持や学校の運営など)を提供しています。固定資産税は、固定資産の評価額に応じて計算されます。
地価税とは?
地価税は、土地の値段の上昇を促す目的で課税される税金です。特に都市部では土地の価値が上がる傾向があり、そのための調整として地価税が導入されています。地価税も地域の自治体によって異なるものですが、一般的には土地の評価額に基づいて課税されます。
固定資産税と地価税の違い
| 特徴 | 固定資産税 | 地価税 |
|---|---|---|
| 課税対象 | 土地・建物 | 土地のみ |
| 目的 | 公共サービスの資金調達 | 土地価格の調整 |
| 計算方法 | 固定資産の評価額に基づく | 土地の評価額に基づく |
まとめ
固定資産税と地価税は、どちらも土地や資産に関連する税金ですが、課税対象やその目的が異なります。正確に理解し、自分の資産をしっかり管理するためにも、これらの税金について知識を深めていきましょう。
ピックアップ解説
固定資産税を支払う時期は、毎年決まっていますが、地域によって異なることもあるんです
たとえば、ある地域では4月に支払いが必要で、別の地域では6月というように、自治体ごとに異なります
固定資産税の納付書が届くと、毎年ドキドキする人も多いでしょう
でも、実はそのお金が地方の公共サービスの維持に使われていると思うと、ちょっと感謝の気持ちが湧いてきますよね!
前の記事: « 告示と建築基準法の違いを改めて考える
次の記事: 固定資産税と地租の違いをわかりやすく解説! »