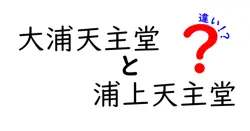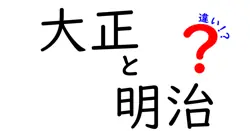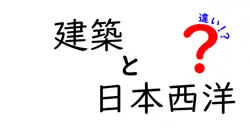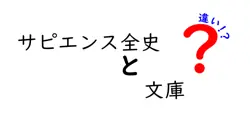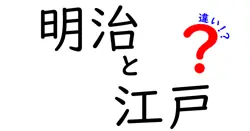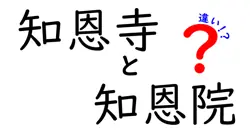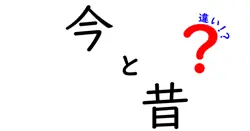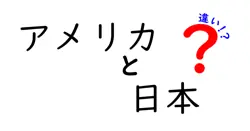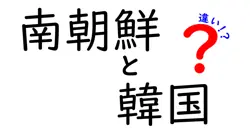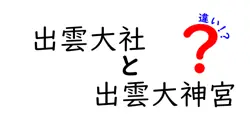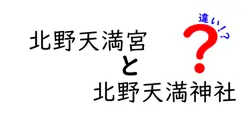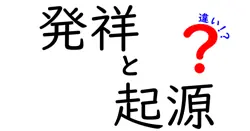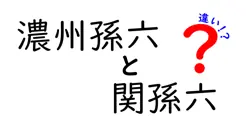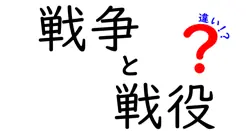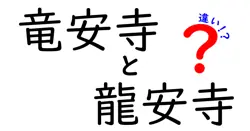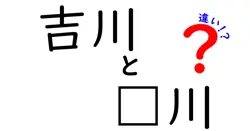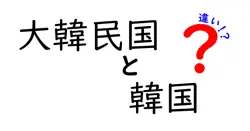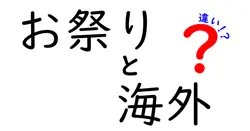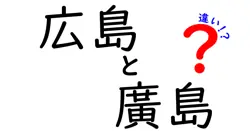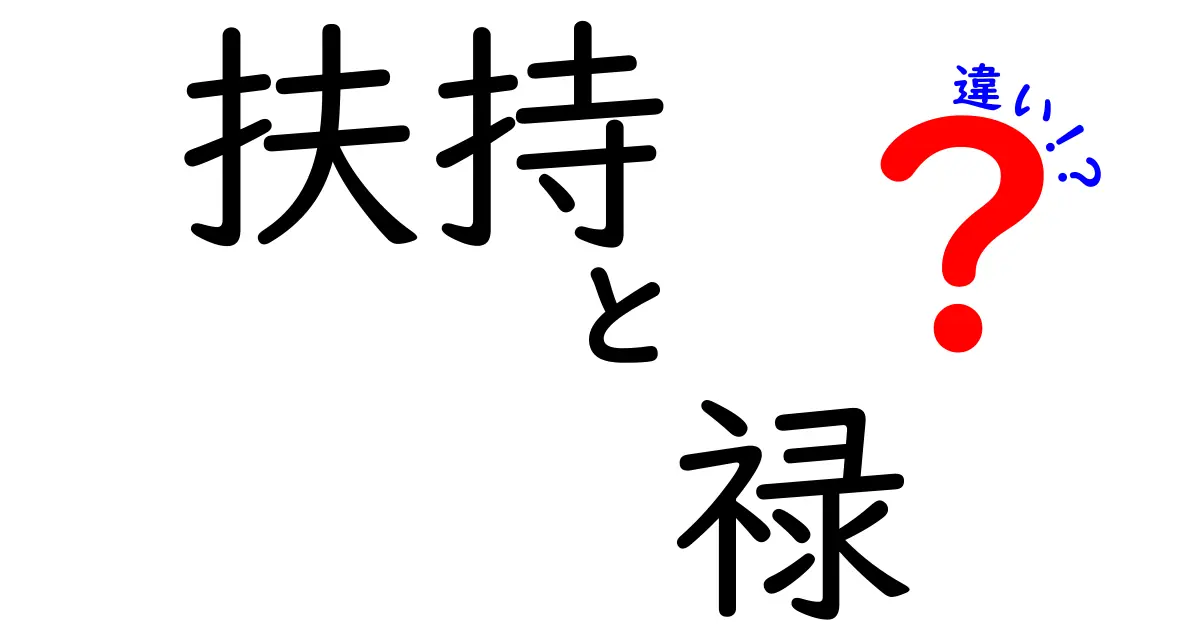
扶持と禄の違いを解説!歴史的背景と意味を徹底比較
私たちが普段使う言葉の中には、似ているようで実は意味が全く異なる言葉もたくさんあります。その一つが「扶持(ふち)」と「禄(ろく)」という言葉です。これらの言葉は特に日本の歴史において重要な役割を果たしてきましたが、その意味や使われ方についてはあまり知られていないかもしれません。今回は、扶持と禄の違いについて、わかりやすく解説していきます。
扶持とは?
扶持という言葉は、特に時代劇や歴史の本などでよく耳にする言葉です。扶持とは、主に「生活を支えるための食糧や資金」を意味します。武士や農民などの生活を支えるために朝廷や大名から与えられたもので、具体的には米やお金として支給されました。
禄とは?
一方で禄という言葉は、主に「官職に就くことで得られる俸禄(ほうろく)」を指します。これは、官職に従事している人が仕事の対価として受け取る給料や年俸のことです。禄は扶持と違い、個人の職業や地位に基づいて支給されるため、特定の職業に従事しないと得られないものです。
| 扶持 | 禄 |
|---|---|
| 生活を支えるための食糧や資金 | 官職に就くことで得られる給料 |
| 主に農民や武士に支給される | 特定の職業に従事する人が得る |
| 朝廷や大名から与えられる | 政府や組織から支給される |
扶持と禄の違いまとめ
扶持と禄は、どちらも「与えられるもの」という点では共通していますが、その意味や目的は異なります。扶持は生活のために直接的に支給されるものであるのに対し、禄は職業に基づくもので、職務の対価として支給されるものです。そのため、扶持は主に農民や武士、禄は官職に就く人々に関連しています。
このように、扶持と禄という言葉を理解することで、日本の歴史や文化をより深く知ることができます。ぜひ知識として活用してみてください。
扶持という言葉は、平安時代から江戸時代にかけて特に注目されていた概念です
例えば、江戸時代の商人たちは扶持を受けるために大名や藩に対して商売を行い、その生活を支えていました
一方で、禄の制度もまた重要で、武士たちは高い禄を得るために多くの手段を使いました
実は、禄の高さがその武士の地位を決める大きな要因だったんですよ
ここで面白いのは、使われた扶持と禄の言葉の背景に、当時の政治や社会の状況が強く影響を与えているということなんです
前の記事: « 半生と生焼けの違いを知って美味しい料理を作ろう!