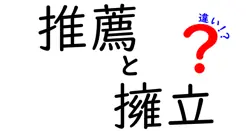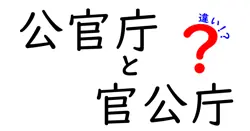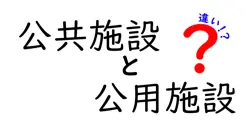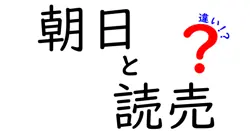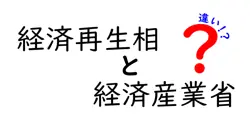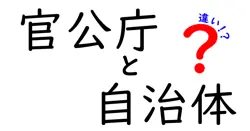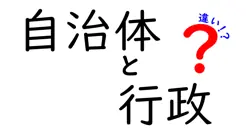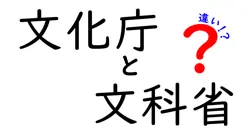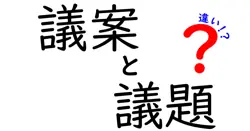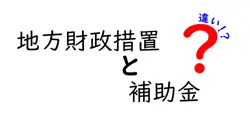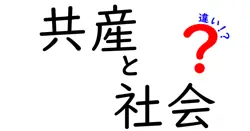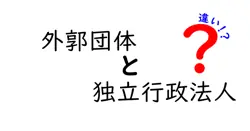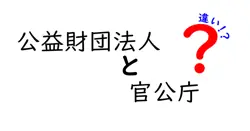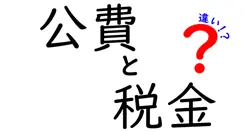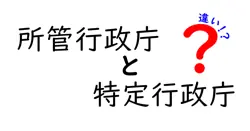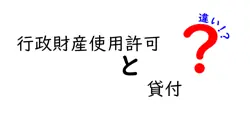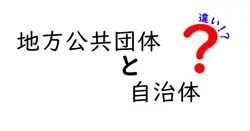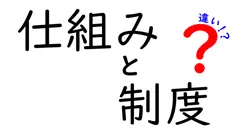税制と税法の違いを徹底解説!知っておきたい基礎知識
私たちの生活に深く関わっている「税金」。しかし、「税制」と「税法」の違いを知っている人は少ないかもしれません。このふたつの言葉は、税金に関する重要な要素ですが、意味や役割は異なります。今回は、中学生でもわかりやすく、税制と税法の違いについて解説していきます。
税制とは
まず「税制」という言葉から見ていきましょう。税制とは、国や地方自治体がどのように税金を徴収し、どのように使うかを定めた仕組みのことを指します。これには、税率、課税対象、控除制度などが含まれ、多くの法律や規則に基づいています。
税法とは
次に「税法」について説明します。税法とは、税金に関する法律のことを言います。つまり、具体的にどのように税金を徴収するか、税金の計算方法、納付期限などを定めた法令のことです。税法は、税制の中核をなすもので、税制の運用を可能にするルールとなっています。
税制と税法の主な違い
| 項目 | 税制 | 税法 |
|---|---|---|
| 定義 | 税金の徴収と使用方法の仕組み | 税金に関する実際の法律 |
| 範囲 | 包括的な制度 | 具体的なルール |
| 例 | 消費税制、所得税制など | 所得税法、消費税法など |
このように、税制は全体の枠組みを作るものであり、税法はその枠組みの中で具体的に税金をどう扱うかを決めるものです。
まとめ
税制と税法は、税金に関する大事な概念ですが、その内容は異なります。税制は税金の制度全体を指し、税法はそれを運用するための具体的な法律です。この違いを理解することで、税金に関する情報をより深く理解できるようになるでしょう。
税金に関することを考えると、「税制」と「税法」という言葉が出てきますが、普段はあまり意識しないですよね
税制は国や自治体がどのように税金を管理するかの全体の仕組み、税法はそのために必要な法律です
例えば、日本の消費税は税法によって決められていますが、その税率や支出の使い道は税制に関わっています
少し難しいかもしれませんが、税金について考えるときには、このふたつの言葉を意識してみるといいかもしれませんね
税の仕組みを理解することで、身近な問題にも目が向くかもしれません!
前の記事: « 特定用途と非特定用途の違いを簡単に解説!