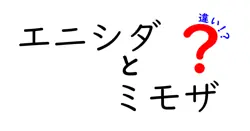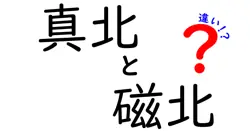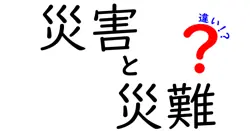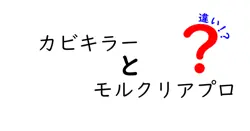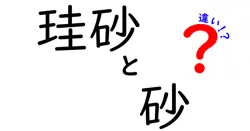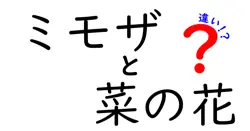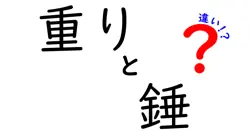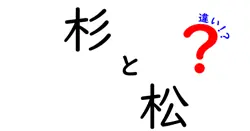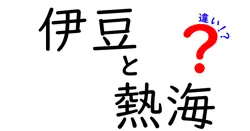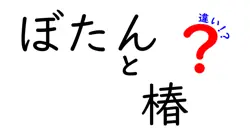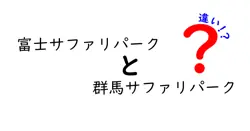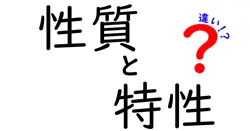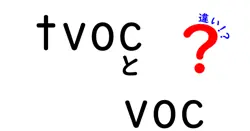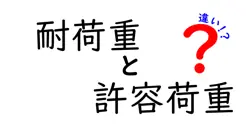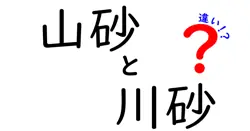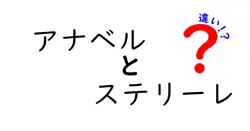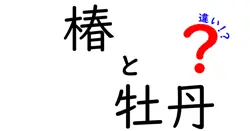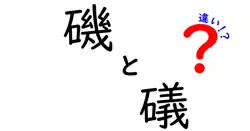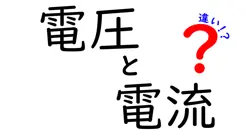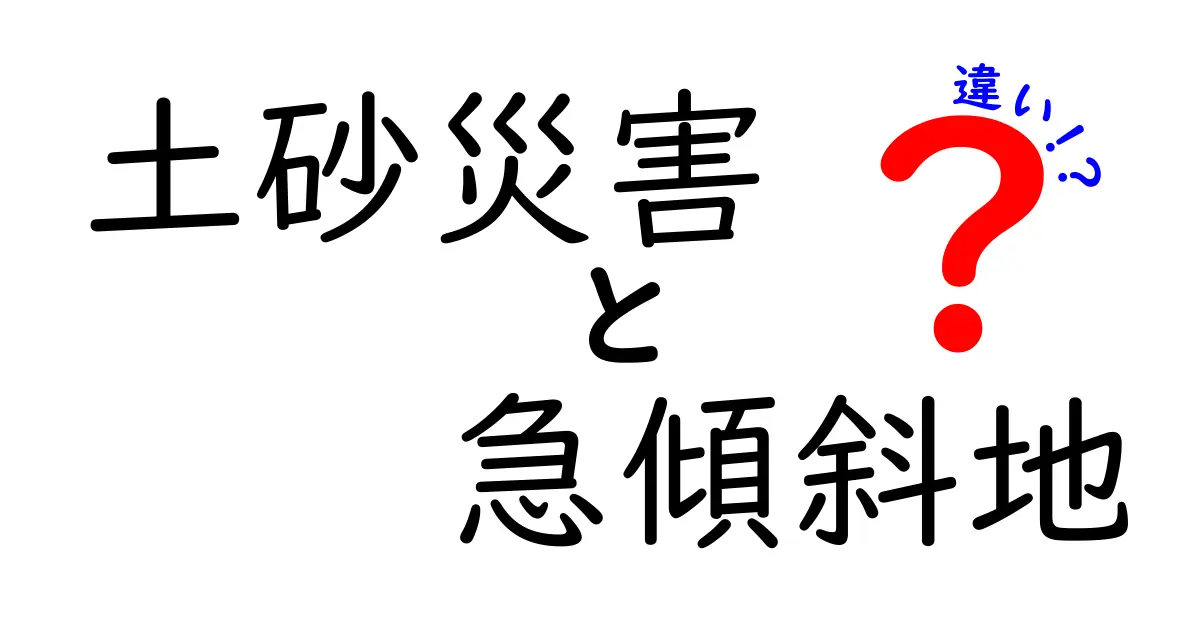
土砂災害と急傾斜地の違いをわかりやすく解説!
私たちの生活において、時折耳にする「土砂災害」と「急傾斜地」という言葉。これらは似たような印象を持ちますが、実はそれぞれ異なる概念を表しています。この記事では、その違いについて詳しく見ていきましょう。
土砂災害とは?
土砂災害とは、地震や豪雨などの自然現象が原因で、土砂や岩石が崩れ落ちたり流れ出たりする現象を指します。日本では、特に梅雨や台風の時期に発生しやすく、住宅地や道路に甚大な被害をもたらすことがあります。土砂災害には、土石流、地すべり、崩落などが含まれます。これらの現象は、地面が急激に変化するため非常に危険です。
急傾斜地とは?
急傾斜地は、地形の特徴を示す言葉です。一般的に、傾斜が30度以上の土地を指します。このような土地は土砂災害が発生しやすい環境が整っていることが多く、農業や住宅の建設には注意が必要です。急傾斜地に住宅を建てると、例えば大雨の後に土砂崩れが起こるリスクが高まります。
土砂災害と急傾斜地の違い
| 項目 | 土砂災害 | 急傾斜地 |
|---|---|---|
| 定義 | 土砂が崩れ落ちる現象 | 傾斜が急な土地 |
| 原因 | 主に自然災害(雨、地震など) | 地形の特徴 |
| リスク | 豪雨や地震による被害 | 土砂災害に巻き込まれる可能性 |
| 例 | 土石流、地すべり | 山間部の急な崖 |
まとめ
このように、「土砂災害」と「急傾斜地」は異なる意味を持つ言葉です。土砂災害は自然現象による危険を示し、急傾斜地はその危険が生じやすい地形を示しています。私たちが安全に暮らすためには、これらの違いを理解し、日頃から自然災害への備えを怠らないことが大切です。
急傾斜地の理解には、身近な例を考えるとわかりやすいです
例えば、高い山の登山道や、住んでいる家の裏に急な崖があるとします
雨が降ると、その崖の土が緩むことがありますね
この土が崩れもするし、実際その崖の近くに家があると、土砂災害による危険が高まります
だからこそ、急傾斜地は土砂災害が発生する可能性がある場所ということを知っておくのが大切なんです
前の記事: « 土砂災害と山地災害の違いとは?知っておくべき基本知識
次の記事: 土砂災害と水害の違いを分かりやすく解説!その影響と対策について »