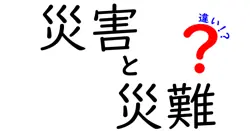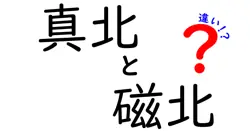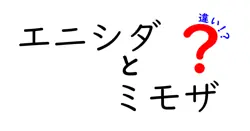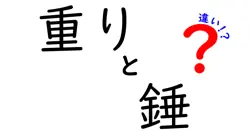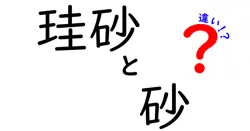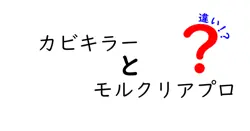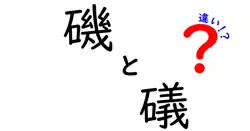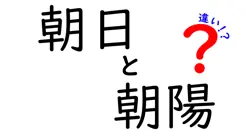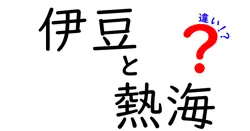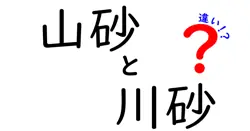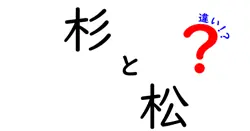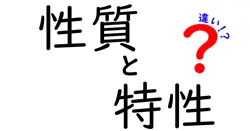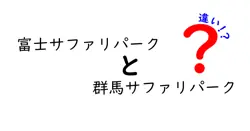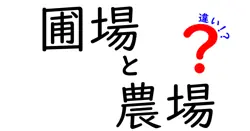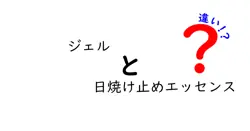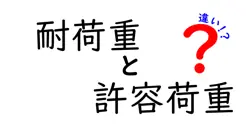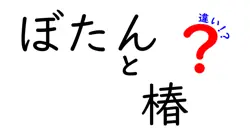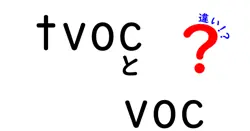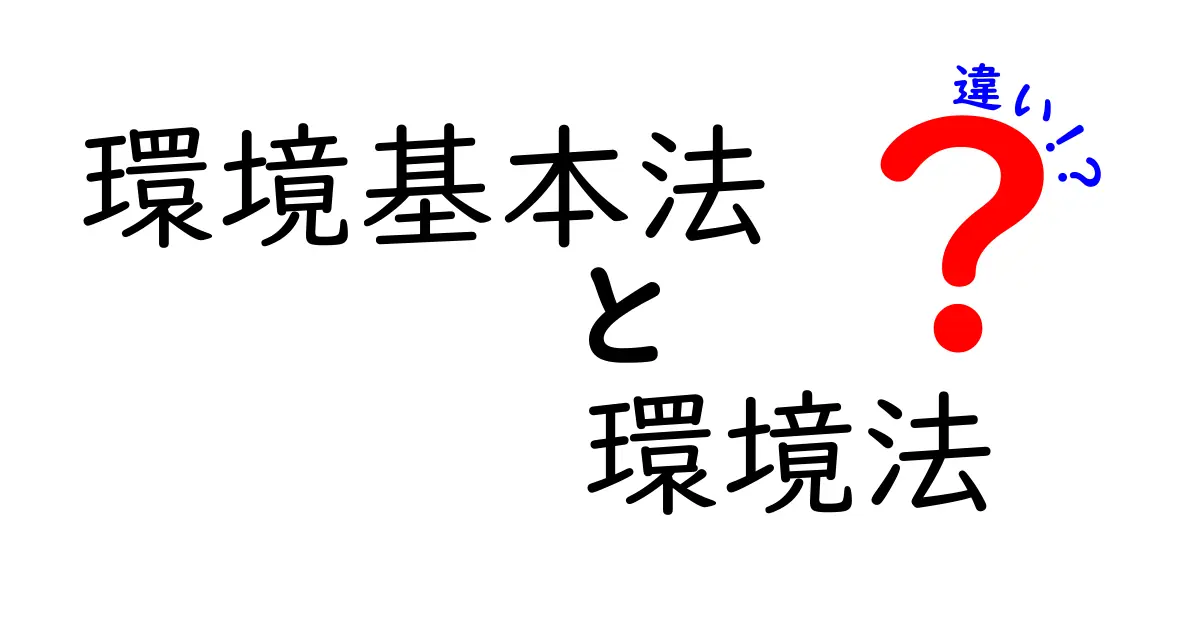
環境基本法と環境法の違いとは?わかりやすく解説します!
環境問題は私たちの生活に密接に関係しています。特に「環境基本法」と「環境法」という言葉は、しばしば混同されることがあります。しかし、実際にはそれぞれ異なる目的や役割を持っています。ここでは、これらの法律の違いについて詳しく見ていきましょう。
環境基本法とは?
環境基本法は、1993年に制定された日本の法律です。この法律の主な目的は、環境保全に関する基本的な方針を定めることで、持続可能な社会の実現を目指しています。環境基本法では、環境の保全と創造、環境に関する情報の提供、国民の立場からの意見の反映などが重視されています。
環境法とは?
一方、環境法は「環境基本法」を含む、環境に関連する広範な法律や規制の総称です。これには、廃棄物処理法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法など、個別の環境問題に対処するための法律も含まれます。環境法は、具体的な環境保護のためのルールや基準を設け、実際の施策や取り組みを進めるための枠組みを提供しています。
環境基本法と環境法の違い
| 項目 | 環境基本法 | 環境法 |
|---|---|---|
| 目的 | 環境保全に関する基本方針を定める | 環境問題への具体的な対策を定める法律の総称 |
| 制定年 | 1993年 | 複数の法律を含む |
| 重要性 | 国の環境政策の根幹をなす | 具体的な環境保護のルールを提供 |
まとめ
このように、環境基本法と環境法は目的や内容が異なります。環境基本法は基本的な方針を定める重要な法律であり、環境法はその延長線上にある、環境問題に対処するための具体的な法律群です。私たち一人ひとりが環境問題を理解し、日常生活での行動に生かすことが大切です。
環境基本法は日本の環境政策の基礎となる大切な法律ですが、環境法という言葉を聞くと、さまざまな規制や方針が含まれていて広範に感じるでしょう
実は、環境法の中には特定の問題に焦点を当てた法律がたくさんあります
例えば、廃棄物に関する法律や大気の質を守るための規制など、身近で具体的な問題を処理するために作られています
つまり、私たちの生活をより安全で持続可能なものにするために、これらの法律は欠かせない存在なのです
前の記事: « 耐火性と難燃性の違いを知ろう!どちらが安全なの?