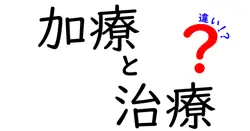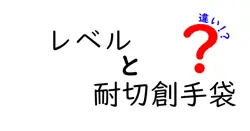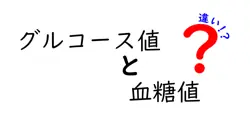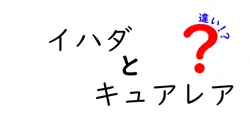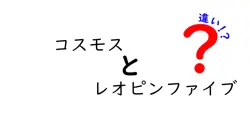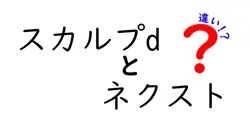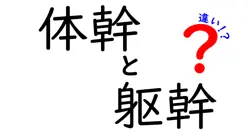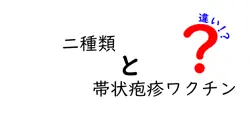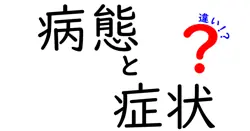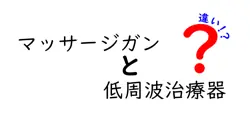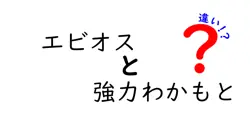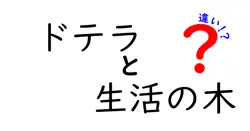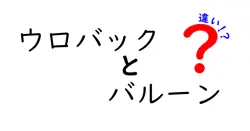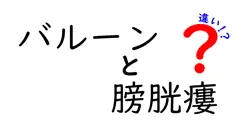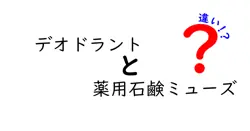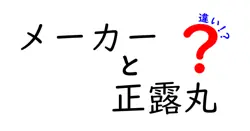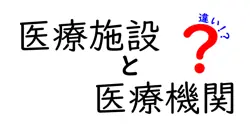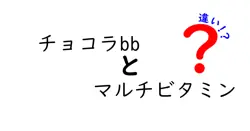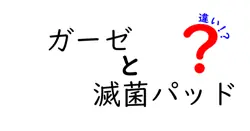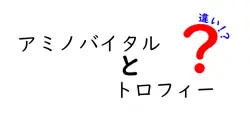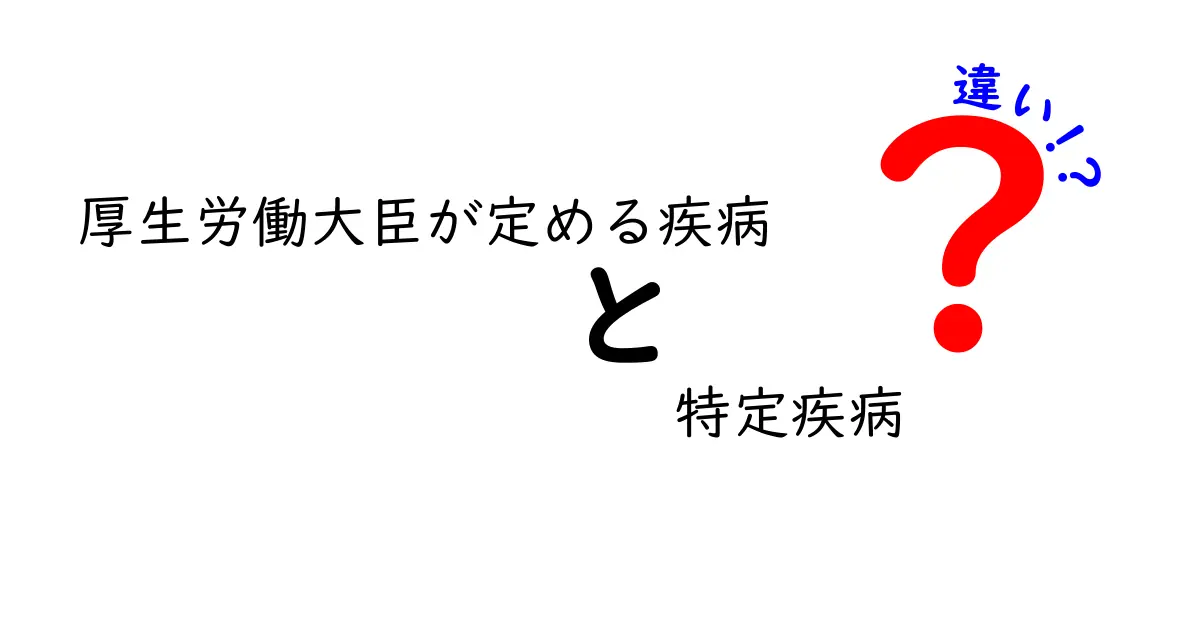
厚生労働大臣が定める疾病と特定疾病の違いとは?分かりやすく解説!
私たちの健康に関わる言葉として「厚生労働大臣が定める疾病」と「特定疾病」という言葉がありますが、これらの違いについて考えたことはありますか?今日はこの2つの用語について詳しく解説します。
厚生労働大臣が定める疾病とは
厚生労働大臣が定める疾病とは、日本の法律に基づいて、特定の病気や健康状態が正式に認められたものを指します。これらの疾病は、医療や保健施策において特に重要視されています。
特定疾病とは
特定疾病は、一般的にその病気が重く、長期的な治療や支援が必要なものを指します。特定疾病に指定されることで、患者は特別な医療サービスや補助金を受けることができるため、日常生活の質が向上することがあります。
厚生労働大臣が定める疾病と特定疾病の比較
| 項目 | 厚生労働大臣が定める疾病 | 特定疾病 |
|---|---|---|
| 定義 | 法律に基づき認められた病気 | 重い症状を持ち長期的な支援が必要な病気 |
| 目的 | 医療施策の基盤を作る | 患者の生活支援を目的とする |
| 例 | がん、糖尿病、心疾患など | 慢性腎不全、重度障害など |
おわりに
厚生労働大臣が定める疾病と特定疾病は、それぞれの定義や目的、指定される内容が異なります。病気によっては、特定疾病として扱われることもあり、こうした知識を持つことで自分や他人の健康を守る手助けにもなるでしょう。
ピックアップ解説
特定疾病について考えるとき、私たちはどうしてもその病気の症状や治療法に目が行きがちですが、実はその背後には多くの支援制度が存在します
例えば、ある特定疾病にかかると、医療費が減免されることがあります
これはどういうことかというと、特定疾病の方に対して政府が特別な配慮を行っているからです
その制度を利用することで、治療にかかる負担が少なくなるのです
こうした制度は、多くの方の生活を支えるために作られているので、ぜひ知識を増やして、必要なときに活用していきたいですね
前の記事: « 別表7と特定疾病の違いを知ろう!その特徴と影響を解説