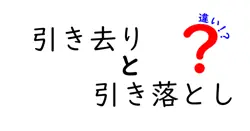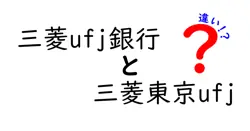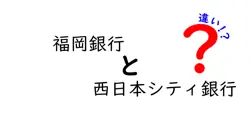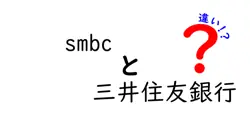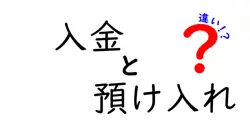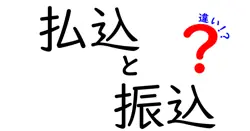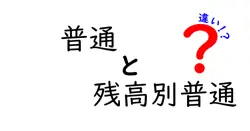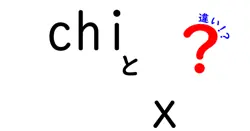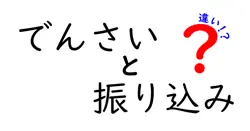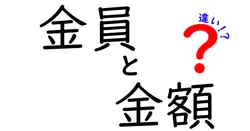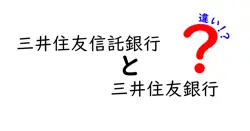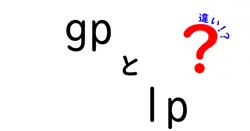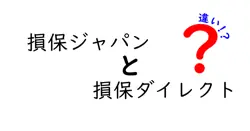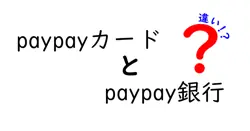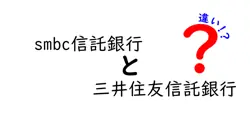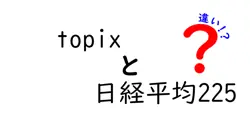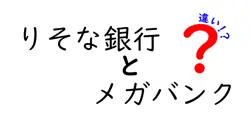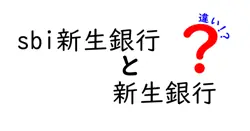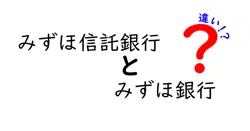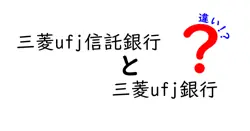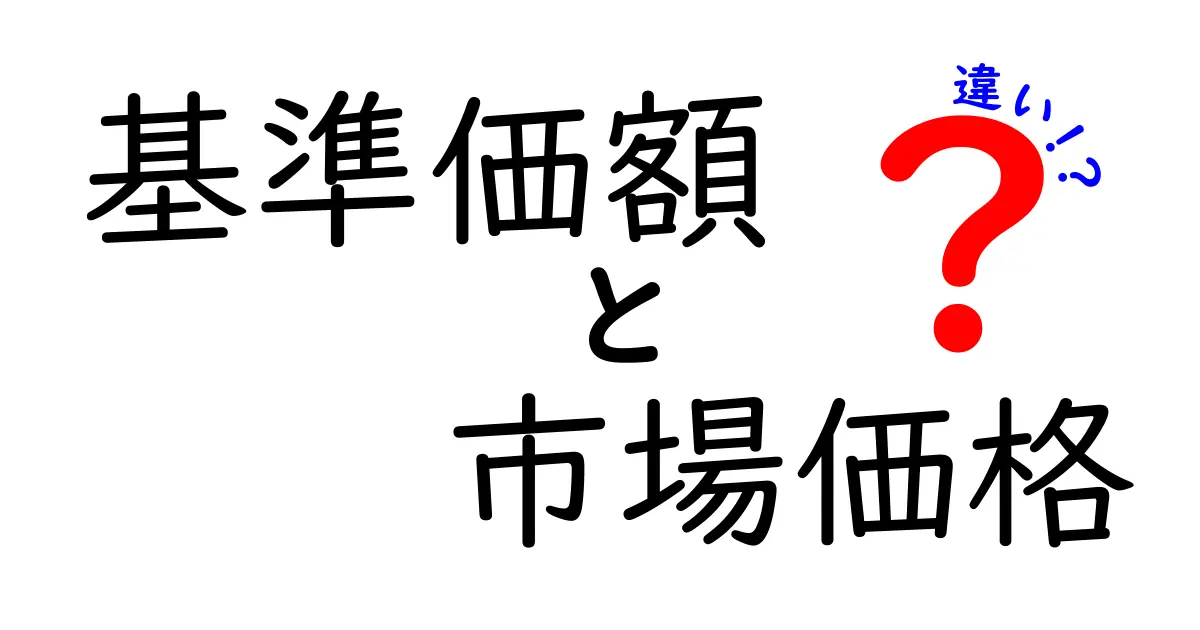
基準価額と市場価格の違いをわかりやすく解説!
投資や金融の世界では、多くの用語が使われますが、その中で特に重要なものの一つが「基準価額」と「市場価格」です。これら二つの言葉は、資産を評価する際に欠かせない情報ですが、しばしば混同されがちです。
基準価額とは?
基準価額とは、投資信託やETF(上場投資信託)の一口あたりの価値を示す金額です。これは、その投資信託やETFが保有する資産の総額を、発行済みの口数で割ることで求められます。たとえば、投資信託が1億円の資産を持っていて、発行済みの口数が100万口であれば、基準価額は100円となります。
市場価格とは?
一方、市場価格とは、投資信託やETFが実際に取引されている価格のことです。これは株式市場での需要と供給によって決まるため、基準価額とは異なることがあります。市場価格は、時には基準価額以上になることもあれば、逆に下回ることもあります。
基準価額と市場価格の違い
| 基準価額 | 市場価格 |
|---|---|
| 投資信託やETFの一口あたりの価値 | 実際に取引されている価格 |
| 基準日ごとに計算される | リアルタイムで変動する |
| 資産の価値に基づく | 市場の需給による |
どちらを重視するべきか?
投資家がファンドに投資する際、基準価額は重要な指標ですが、市場価格も見逃せません。たとえば、基準価額が好調なファンドでも、市場価格が低い場合、実際の取引は難しくなります。逆に、基準価額が高くても、市場価格が低くなれば、安く買えるチャンスが生まれることもあります。
まとめ
基準価額と市場価格は、それぞれ異なる役割を果たしています。基準価額は資産の価値を測る指標であり、市場価格は実際の取引における価格です。投資を行う際は、この二つの違いを理解することが重要です。
基準価額というと、一般的には投資信託やETFの「一口あたりの価値」というイメージが強いですが、実は基準価額はその時点での資産の評価を示すもので、過去の実績や予想に基づいて変わることがあります
あるファンドが基準価額を上げていると、投資家は「このファンドはいい兆しだ!」と思いやすくなりますが、実際の市場ではその評価が必ずしも反映されているわけではないのが面白いところです
だから市場価格も見とく必要がありますね
前の記事: « 均衡価格と市場価格の違いを分かりやすく解説!
次の記事: 売上予測と需要予測の違いをわかりやすく解説! »