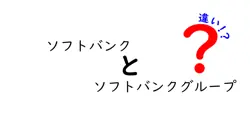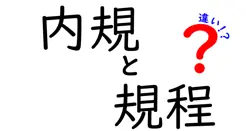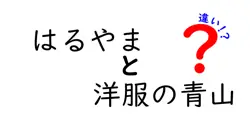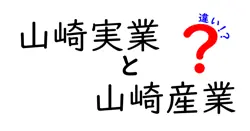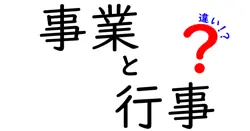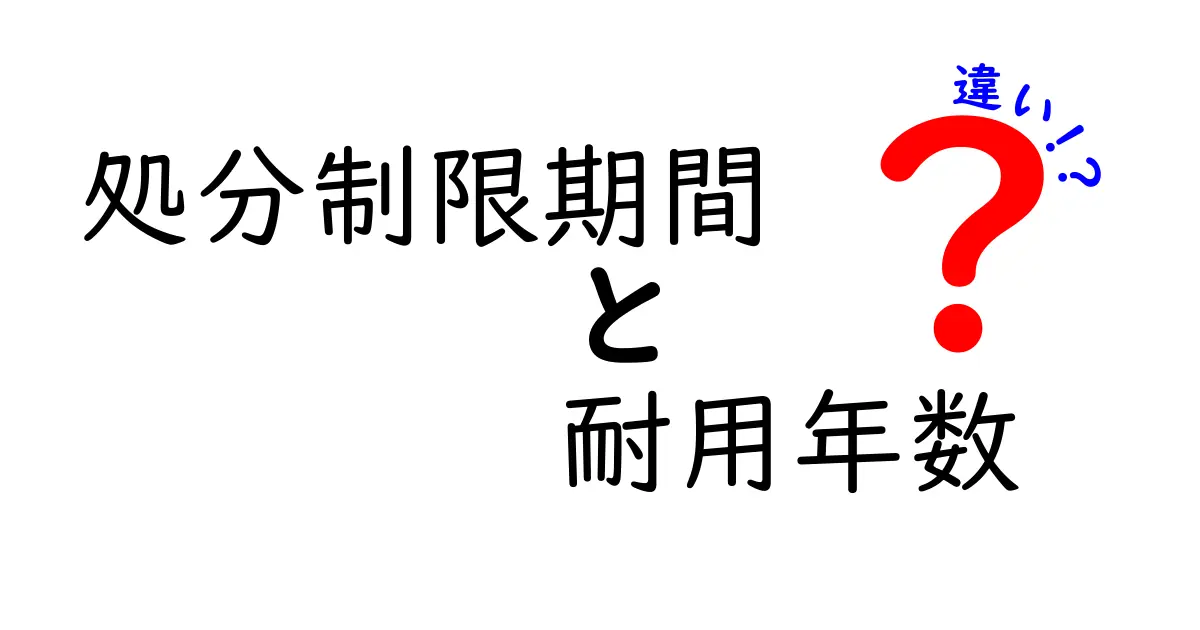
処分制限期間と耐用年数の違いを徹底解説!理解しておくべきポイント
私たちの生活の中では、さまざまな法律や規則が存在し、その中でも「処分制限期間」と「耐用年数」という言葉は特に重要です。しかし、これらの言葉は何を意味し、どのように異なるのでしょうか。今回は中学生でも理解できるように、処分制限期間と耐用年数の違いについて解説します。
処分制限期間とは?
処分制限期間とは、特定の物や権利について、その対象を処分(譲渡、売却、廃棄など)することが制限される期間を指します。簡単に言えば、法律や契約によってその期間中はその物や権利を勝手に売ったり、処分したりすることができないということです。
耐用年数とは?
一方、耐用年数とは、ある資産が経済的に使用できるとされる期間のことで、税務上の処理や企業の経営においてとても重要です。たとえば、設備や備品を購入した際、その物をどれくらいの年数使えるかを示す指標です。耐用年数が設定されることで、設備投資のコストをコントロールすることができます。
| 用語 | 意味 | 活用例 |
|---|---|---|
| 処分制限期間 | 特定物の処分が制限される期間 | 資金調達の際の担保物件 |
| 耐用年数 | 資産が使用可能な期間 | 減価償却の計算に利用 |
処分制限期間と耐用年数の違い
この二つの言葉は、その意味や目的が大きく異なります。処分制限期間は、物や権利の扱いに関する法的な制約を示すものであり、主に法律的な観点から考えられます。一方で、耐用年数は、資産の経済的な使用期間を示し、主に経営や税務の観点から考える必要があります。
たとえば、ある機械を購入した場合、その耐用年数は通常5年とされることが多いですが、その機械が特定の契約のもとで処分制限を受ける場合、その契約の期間が過ぎないと物理的にその機械を売却することができません。このように、どちらも関連はしていますが、それぞれの目的が異なるため、混同しないように注意が必要です。
まとめ
処分制限期間と耐用年数は、一見似たような言葉かもしれませんが、実際には異なる意味を持っています。処分制限期間は法的な制約、耐用年数は経済的な指標として考えることができるでしょう。これからも、法律や税務について理解を深めていくことが大切です。
処分制限期間について考えると、意外と身近に感じることがあります
例えば、親が家を買った時、購入資金の一部を銀行から借りることがあるでしょう
この時、銀行は家を担保にお金を貸します
担保にされた家は処分制限されているので、もしお金を返せなければ、銀行がその家を売却する権利を持ちます
だから、私たちの生活の中でも、処分制限期間は重要な役割を果たしているんですね!
前の記事: « 元本と簿価の違いを徹底解説!お金の世界を知ろう