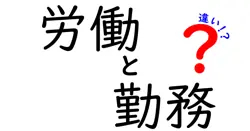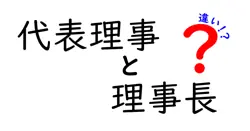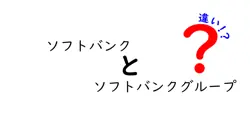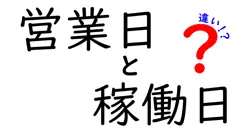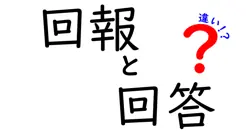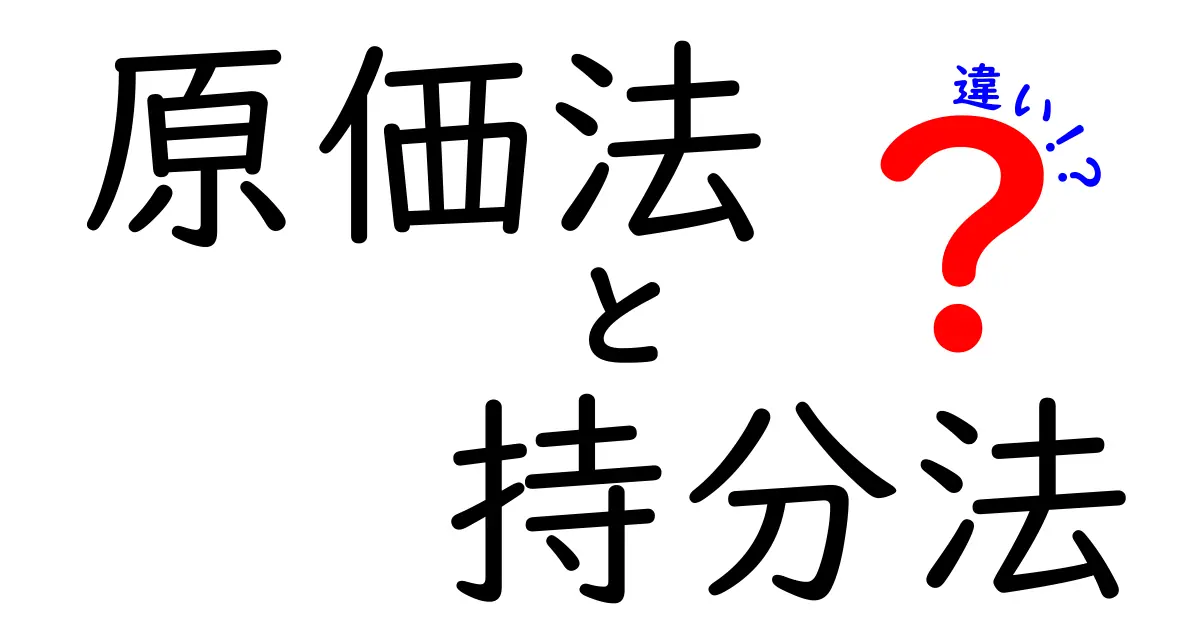
原価法と持分法の違いをわかりやすく解説
経済やビジネスの世界でよく使われる「原価法」と「持分法」。これらは会計処理の方法ですが、それぞれの特徴や違いについて詳しく解説していきます。まずはそれぞれの方法について簡単に説明しましょう。
原価法とは
原価法は、企業が製品やサービスの原価をもとにして財務諸表を作成する方法です。一般的には製品やサービスの製造にかかった直接的なコストをカウントし、それに関連する間接的なコストを含めて計算します。たとえば、材料費や人件費、工場の維持費などがこの原価法の対象です。
持分法とは
持分法は、企業が他の企業に投資を行った場合に、その持分をもとに経営成績を記録する方法です。持分法では、投資先の企業の利益や損失の変動が自社の業績に反映されます。具体的には、自社の投資割合に応じた収益を計上し、投資先の企業が赤字であればその分だけ自社の業績も悪化します。
原価法と持分法の違い
| 項目 | 原価法 | 持分法 |
|---|---|---|
| 定義 | 製品やサービスの原価を計算する方法 | 投資先の企業の経営成績を反映する方法 |
| 対象 | 自社の製品やサービス | 他社への投資 |
| 影響 | 直接的なコストの影響 | 持分に応じた投資先の業績の影響 |
| 例 | 製造業や小売業 | 持株会社や企業グループ |
まとめ
原価法と持分法はそれぞれ異なる目的と方法で使用されますが、ビジネスを行う上ではそれぞれのメリット、デメリットを理解することが重要です。原価法は製品の価格設定や収益性を向上させるために有用で、持分法は他の企業との連携や投資戦略を考える上で役立ちます。これらの知識を活用して、あなたのビジネスをより効果的に運営していきましょう。
原価法と持分法は、会計や経営の世界では重要な概念ですが、実はその背景には歴史的な変遷があります
原価法は、製造業が発展する中で生まれた方法で、製品のコストを正確に算出することが求められるようになりました
一方、持分法は、企業同士の連携が増えてきた現代において、より重要性を増しています
特に、グローバル化が進む今、持分法の理解は国際的なビジネスを行う上で不可欠です
さあ、これからもこうした会計法を駆使して、賢いビジネスライフを送りましょう!
次の記事: 原価法と時価法の違いを解説!どちらが適切? »