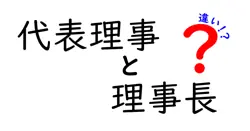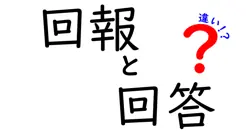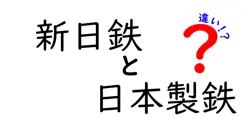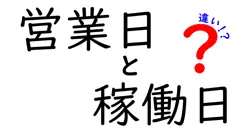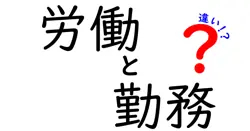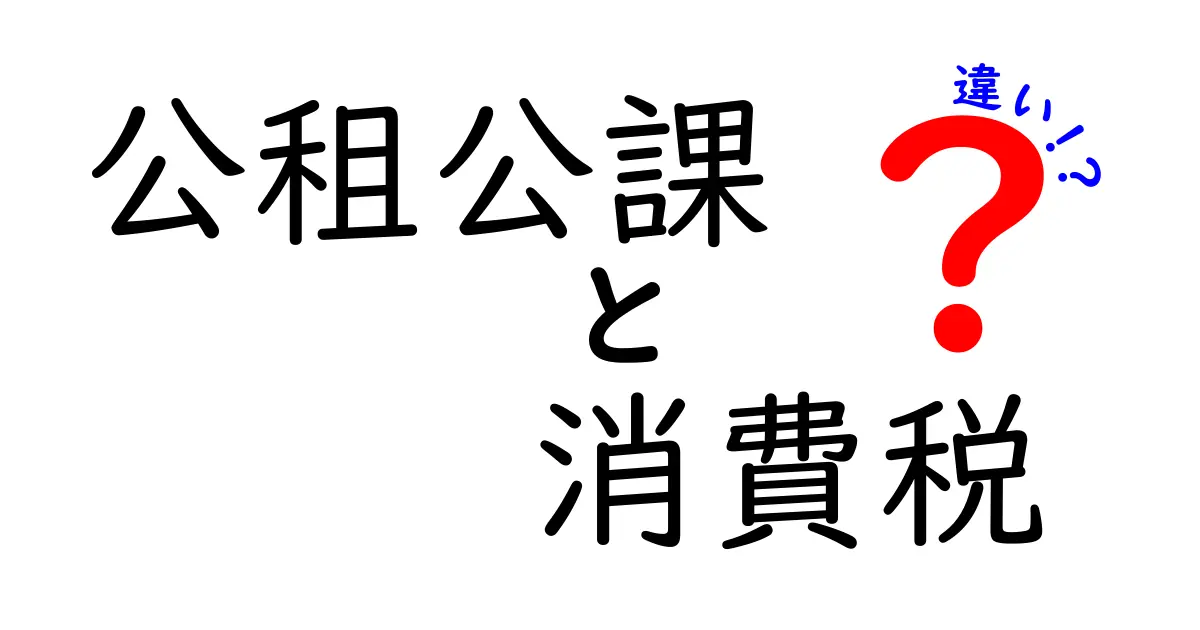
公租公課と消費税の違いをわかりやすく解説!
私たちが日常で支払うお金の中には、さまざまな税金が含まれています。「公租公課」と「消費税」の違いを知ることは、私たちの生活にとても役立つことです。この2つがどのように異なるのか、わかりやすく説明します。
公租公課とは?
公租公課(こうそこうか)という言葉は、基本的に公共のサービスに関連する税金のことを指します。具体的には、地方自治体が徴収する税金や、国に納める税金のことです。例としては、所得税や住民税、固定資産税などがあります。これらの税金は、社会の基盤を支えたり、公共サービスを提供するために使用されます。
消費税とは?
一方で、消費税(しょうひぜい)は、商品の購入やサービスの利用時に支払う税金です。日本では、消費税は販売価格に対して一定の割合(現在は10%)が課されます。消費税も公的サービスを支えるための大切な財源となっていますが、その性質は公租公課と異なります。
| 特徴 | 公租公課 | 消費税 |
|---|---|---|
| 納税の対象 | 主に所得や資産 | 商品の購入やサービス利用 |
| 利用先 | 地方自治体や国 | 国及び地方自治体 |
| 税率 | 地域により異なる | 一律(現在10%) |
公租公課と消費税の使い道
公租公課としての税金は、教育や医療、インフラ整備など、私たちの生活に直接関わるさまざまなサービスに使われます。それに対して、消費税も同様に公共サービスの資金源となるのですが、一般的には他の税金よりも使途が明確にされていないことが多いです。
まとめ
公租公課と消費税は、税金という点で共通していますが、納税の対象や性質、使い道が異なります。それぞれが私たちの生活に与える影響を理解し、税金についての知識を深めることが重要です。
消費税は10%で、私たちが何か商品を買うときには必ずその税金が上乗せされますが、ほんの少し前までは8%でした
税率が8%から10%に上がったとき、多くの人が「消費税が高くなったな」と感じたことでしょう
このように税率が変わることで、私たちの生活に直接的な影響を与えるのが消費税の特徴です
でも実際、税率が上がるとどれくらいの影響があるのか、厳密に計算しないと実感できないことも多いのが面白いところです
前の記事: « 賃貸契約書と重要事項説明書の違いをわかりやすく解説!
次の記事: 公租公課と租税の違いを徹底解説!何がどう違うの? »