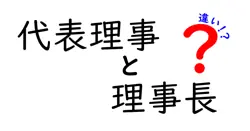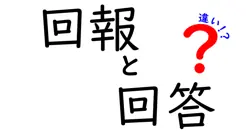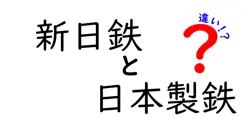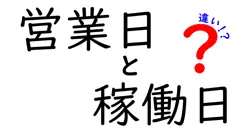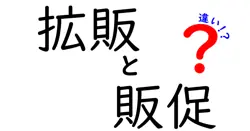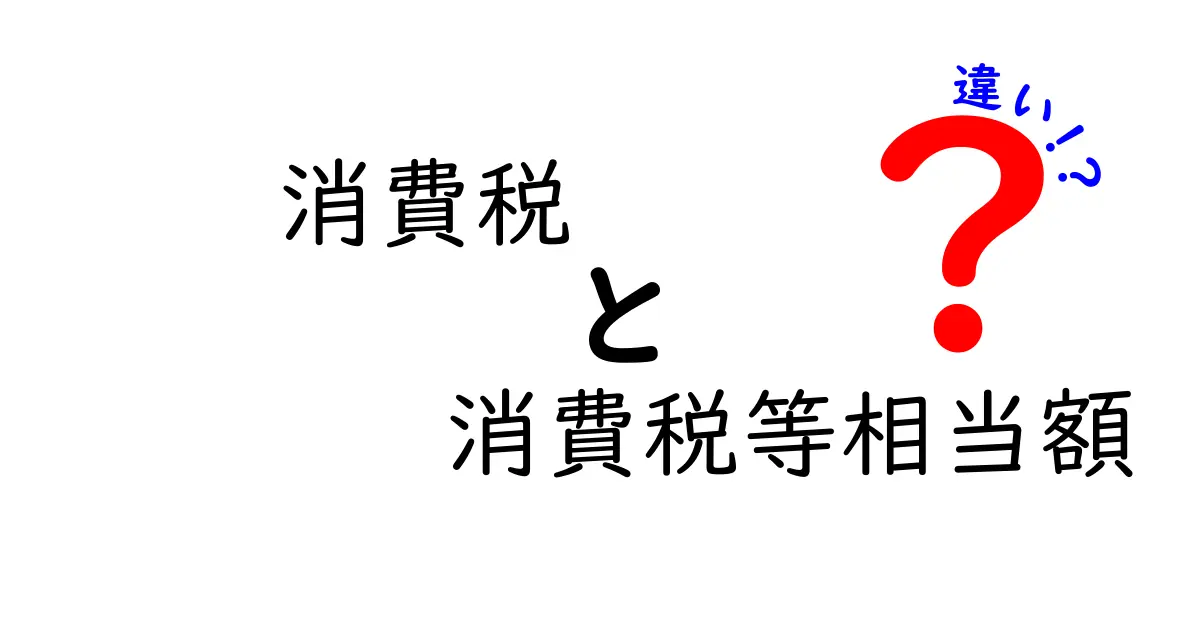
消費税と消費税等相当額の違いを徹底解説!知っておくべきポイント
消費税と消費税等相当額という言葉は、日常生活でもよく目にしますが、実はその意味を正確に理解している人は少ないかもしれません。ここでは、この2つの違いやそれぞれの特徴について詳しく解説します。
消費税とは?
消費税は、商品やサービスの購入に課される税金の一つです。日本では、一般的に10%の税率が適用されることが多いですが、一部の食品や飲料などには軽減税率が適用され、8%となることもあります。消費税は、最終的に消費者が負担することになりますが、実際に販売業者が国に納める仕組みになっています。
消費税等相当額とは?
消費税等相当額とは、具体的には「消費税」「地方消費税」など、消費に関連する税金を総称したものを指します。これは、消費税以外にも地方税があるため、税金全体を考慮に入れた場合に重要な要素となります。消費税だけでなく、消費に関連する全ての税金を含むため、より広い概念といえるでしょう。
消費税と消費税等相当額の違い
| 項目 | 消費税 | 消費税等相当額 |
|---|---|---|
| 定義 | 商品やサービスに課される税金 | 消費に関連する全税金の総称 |
| 例 | 一般的な消費税率(10%) | 消費税、地方消費税など |
| 負担者 | 消費者 | 消費者(計算上) |
| 意義 | 特定の税金の認識 | 税全体の把握 |
まとめ
消費税と消費税等相当額には明確な違いがあります。消費税は特定の税金ですが、消費税等相当額はそれに加えて他の関連税金も含む総称です。この違いを理解することで、税金に対する知識が深まることでしょう。
ピックアップ解説
消費税の計算は途中で難しく感じることがありますが、実際には簡単です
例えば、1000円の商品を買った場合、消費税が10%とすると、税金が100円加わって1100円になります
面白いことに、税金が上がると購入意欲が減ることもあるんです
これが消費に与える影響は政府も注意深く見るポイントです
前の記事: « 懲戒処分と罰則の違いを徹底解説!知っておくべきポイントはこれだ!
次の記事: 消費税と物品税の違いをわかりやすく解説! »